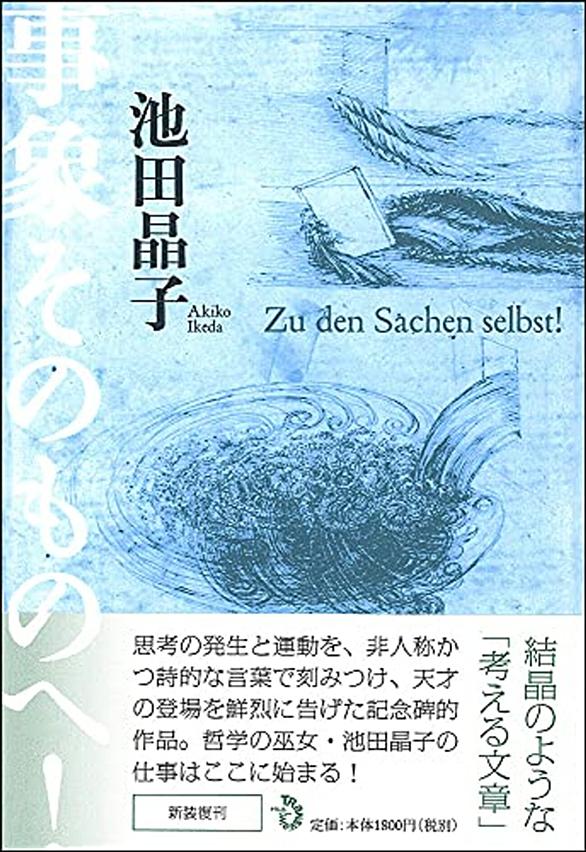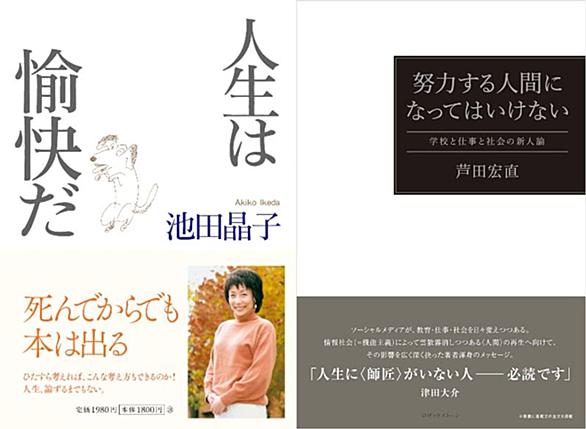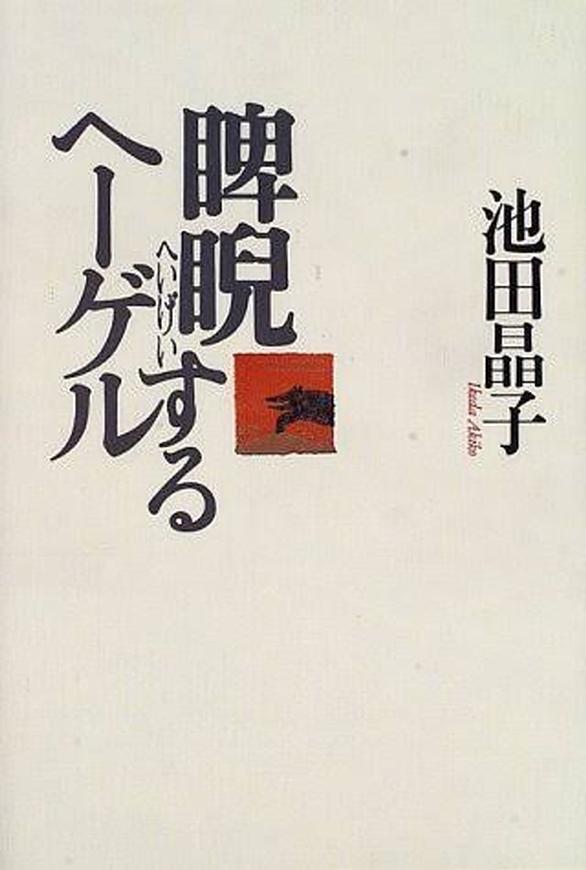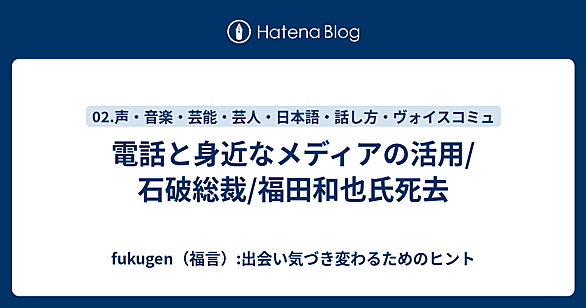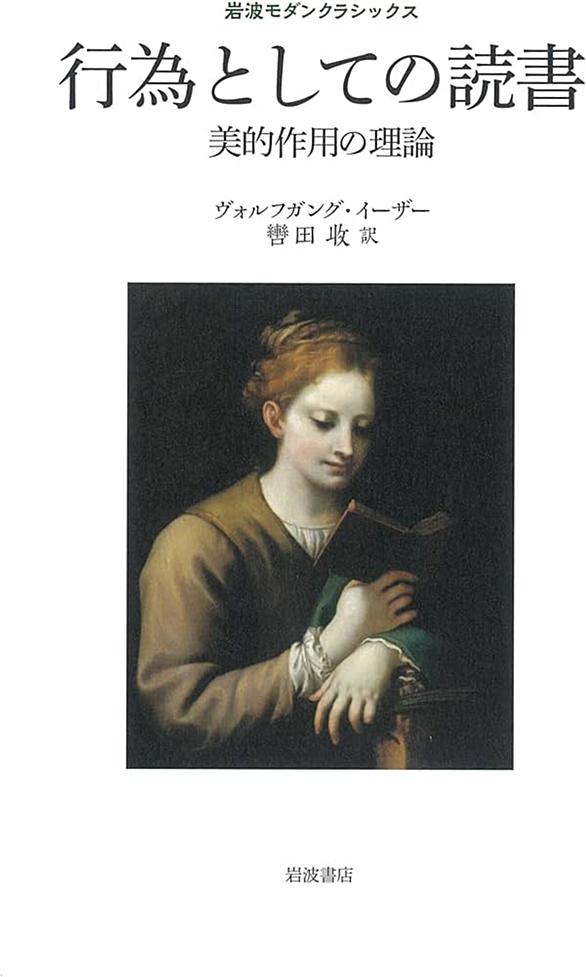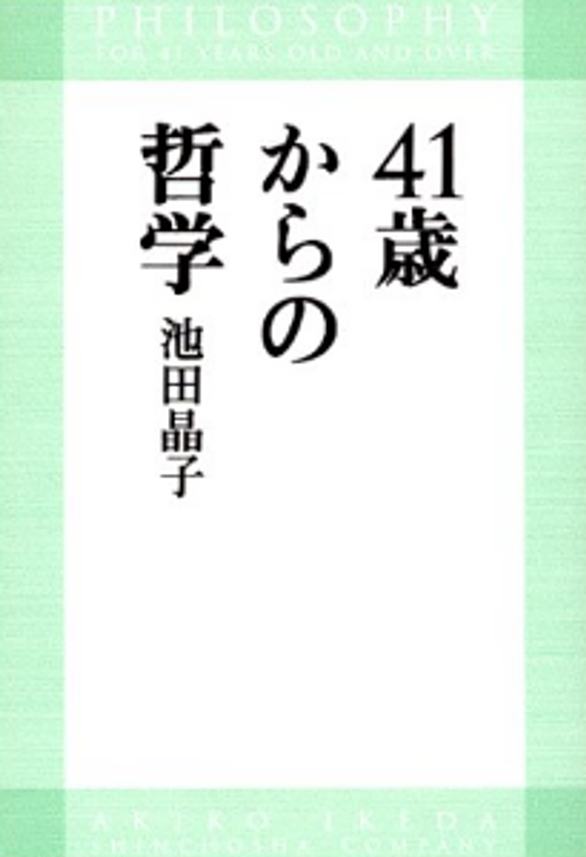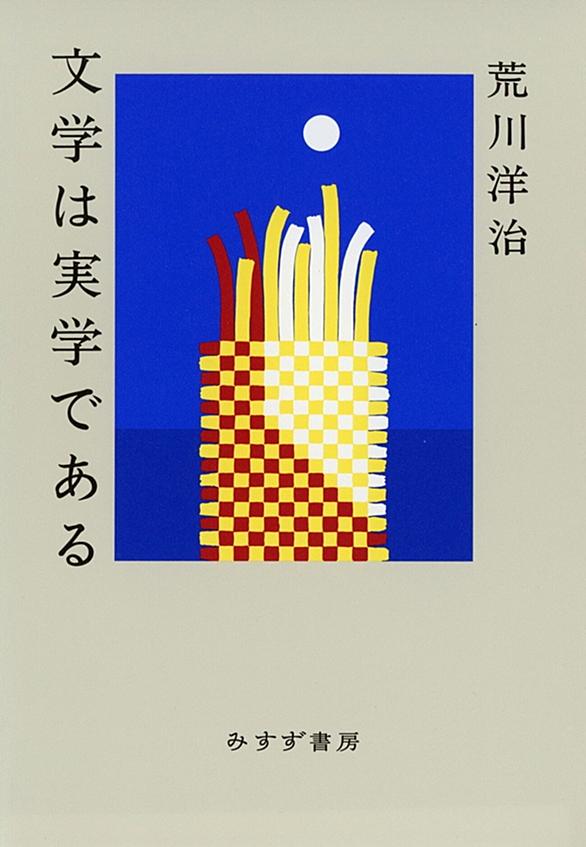池田晶子
(アニメ)
【いけだしょうこ】
アニメーター。
京都アニメーション所属(取締役)
フィルモグラフィー
- kanon(作画監督)
- 涼宮ハルヒの憂鬱(キャラクターデザイン、総作画監督)
- フルメタル・パニック!The Second Raid(作画監督)
- アニメ版AIR(作画監督)
- フルメタル・パニック?ふもっふ(作画監督)
- 犬夜叉(作画監督)
池田晶子
(読書)
【いけだあきこ】
1960年生まれ。慶応大学文学部哲学科卒業。専門用語を使わず、哲学するとはどういうことかを日常の言葉で語る。
著書「14歳からの哲学」は27万部のベストセラーとなった。
2007年2月23日、腎臓癌のため死去。46歳。
当時連載していた「週刊新潮」に死後発表されるよう手配した最終稿に自らの墓碑銘として記載されたことばは、「さて死んだのは誰なのか」であった。
著書
- 最後からひとりめの読者による「埴谷雄高」論(河出書房新社、絶版)
- 事象そのものへ(法蔵館、1991.7)
- メタフィジカ!(法蔵館、1992.4)
- 考える人 口伝(オラクル)西洋哲学史(中央公論新社、1994.9、同文庫 中公文庫、1998.6)
- 帰ってきたソクラテス(新潮社、1994.10、同文庫 新潮文庫、2002.4)
- オン! 埴谷雄高との形而上対話 (講談社、1995.7)
- 悪妻に聞け 帰ってきたソクラテス (新潮社、1996.4、同文庫(改題 ソクラテスよ、哲学は悪妻に聞け)新潮文庫 2002.9)
- メタフィジカル・パンチ 形而上より愛をこめて (文藝春秋 1996.11、同文庫 文春文庫 2005.2)
- 睥睨するヘーゲル (講談社、1997.1)
- さよならソクラテス (新潮社、1997.12、同文庫 新潮文庫 2004.4)
- 残酷人生論 ―あるいは新世紀オラクル(情報センター出版局・ISBN:4795811938、1998.3)
- 考える日々 ―One Size Fits All(毎日新聞社・ISBN:4620312754、1998.12)
- 死と生きる 獄中哲学対話(新潮社 1999.2 共著 陸田真志)
- 魂を考える (法蔵館 1999.4)
- 考える日々II ―One Size Fits All(毎日新聞社・ISBN:4620314137、1999.12)
- 考える日々III ―One Size Fits All(毎日新聞社・ISBN:4620314900、2000.12)
- REMARK (双葉社 2001.2)
- 2001年哲学の旅 (新潮社、2001.3)
- ロゴスに訊け(角川書店・ISBN:4048837478、2002.6)
- 14歳からの哲学 ―考えるための教科書―(トランスビュー・ISBN:4901510142、2003.3)
- あたりまえなことばかり (トランスビュー、2003.3)
- 新・考えるヒント (講談社、2004.2)
- 41歳からの哲学 (新潮社、2004,7)
- 勝っても負けても 41歳からの哲学 (新潮社、2005.8)
- 人生のほんとう (トランスビュー、2006.8)
- 知ることより考えること (新潮社、2006.10)
- 14歳の君へ どう考えどう生きるか (毎日新聞社 2006.12)
- 君自身に還れ 知と信を巡る対話 (本願寺出版社、2007.3 共著 大峯顕)
- 人間自身 考えることに終わりなく (新潮社、2007.4)
- 暮らしの哲学 (毎日出版社、2007.6)
- リマーク 1997-2007 (トランスビュー、2007.7)
- 人生は愉快だ (毎日出版社、2008.11)
- 魂とは何か さて死んだのは誰なのか (トランスビュー、2009.2)
- 私とは何か さて死んだのは誰なのか (講談社、2009.4)
- 死とは何か さて死んだのは誰なのか (毎日新聞社、2009.4)
- 無敵のソクラテス (新潮社、2010.1)
- 事象そのものへ! (新装版、トランスビュー、2010.2)
to be continued・・・