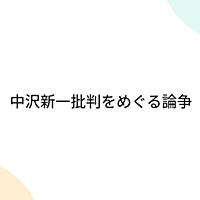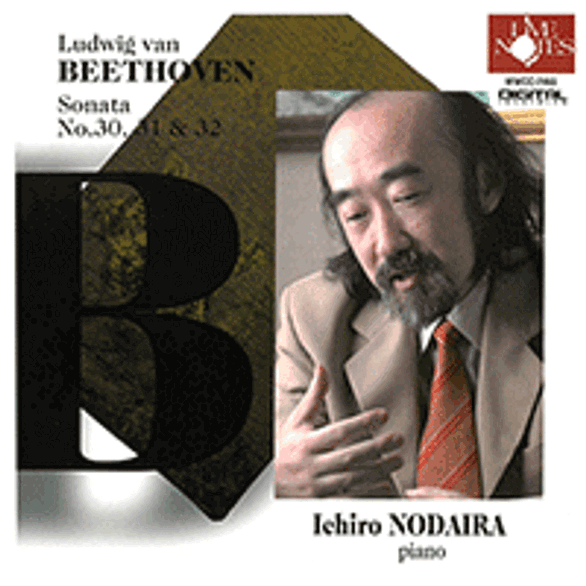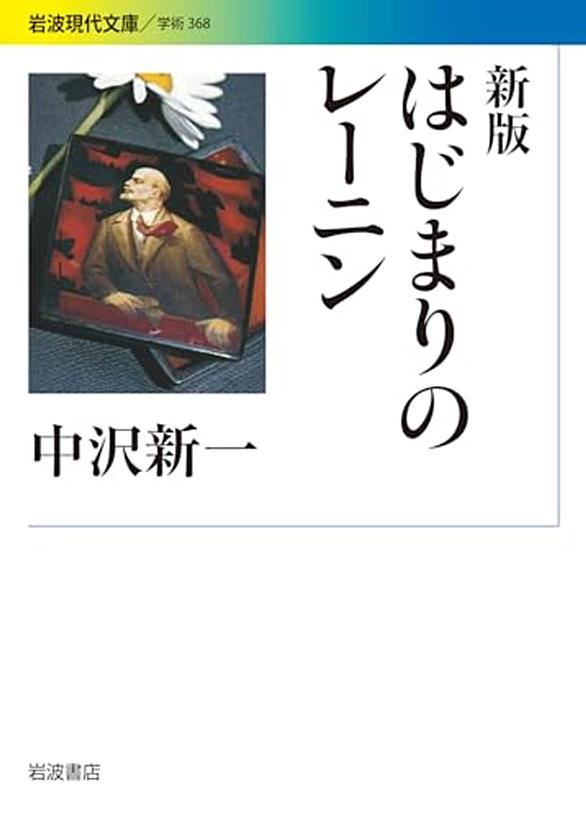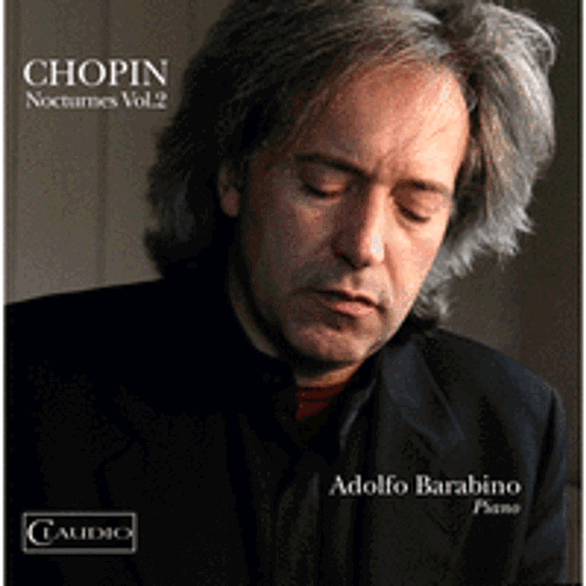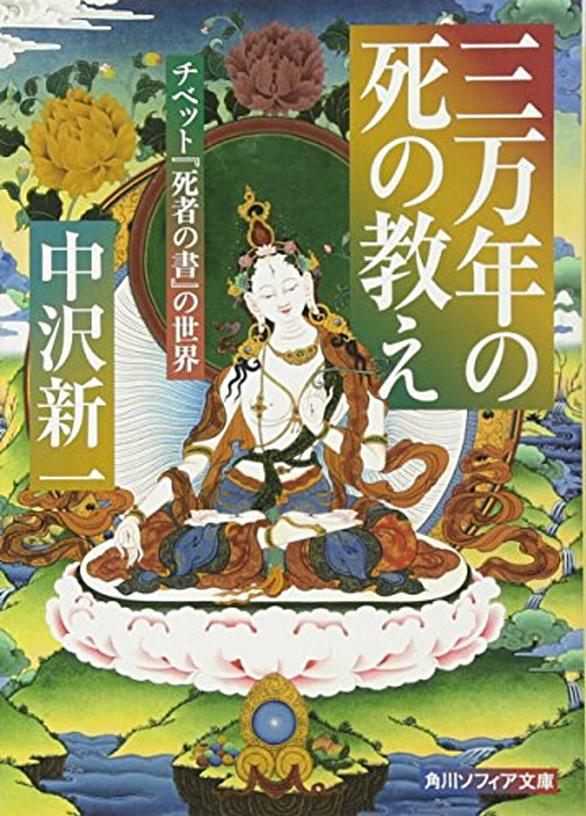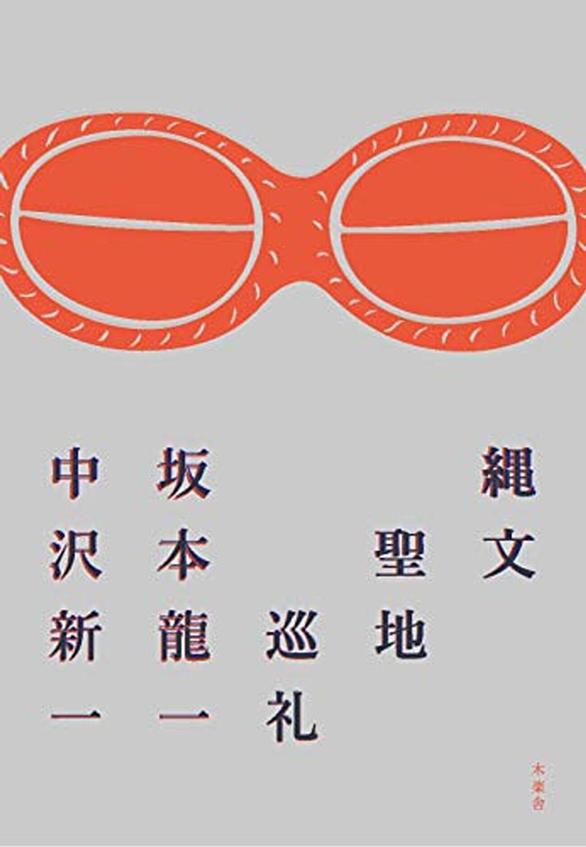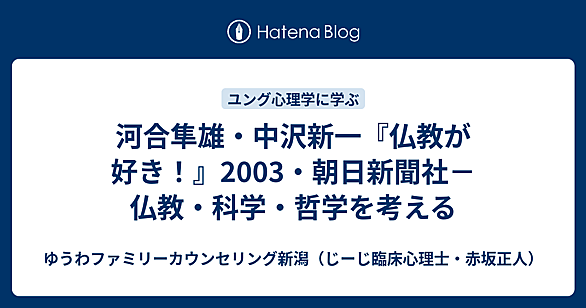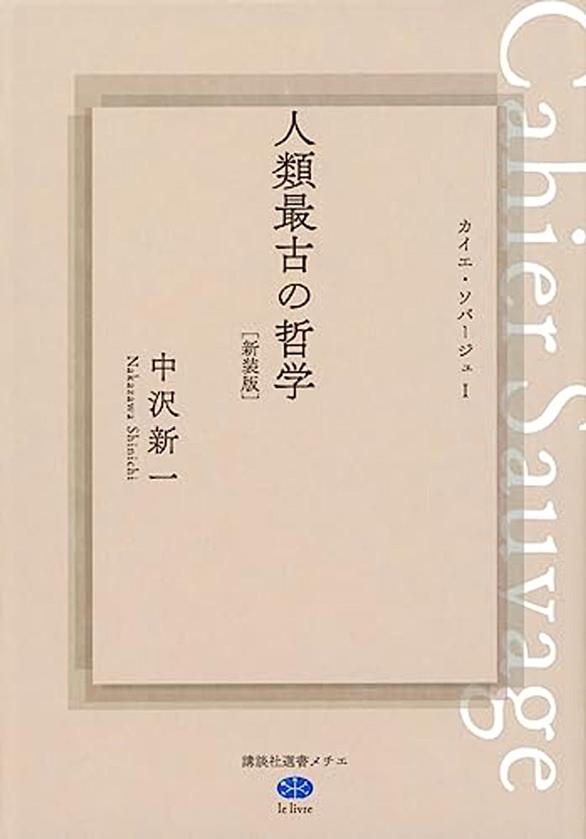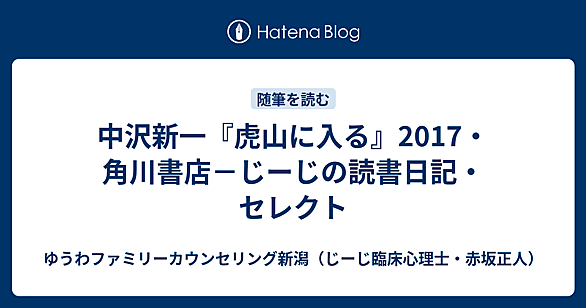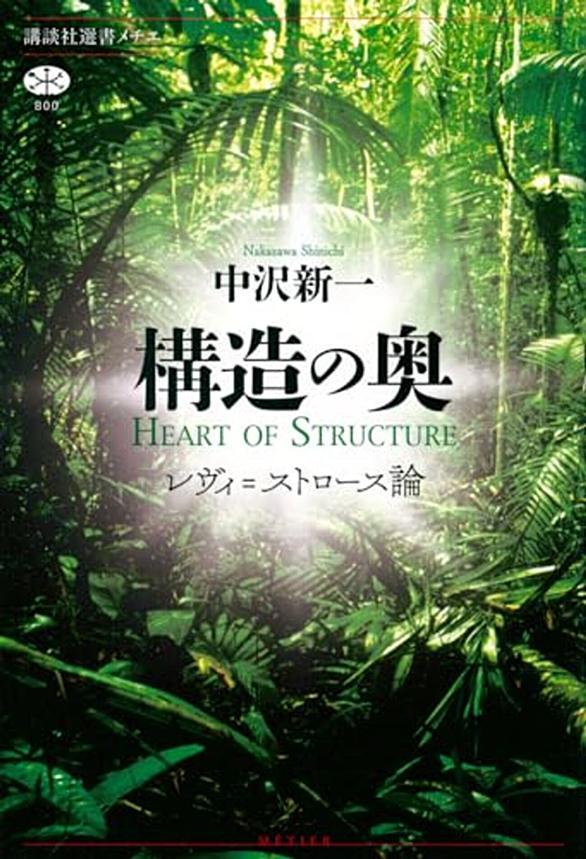中沢新一
(読書)
【なかざわしんいち】
宗教学者・人類学者。思想家。1950年、山梨県生まれ。中央大学総合政策学部教授を経て、現在、多摩美術大学美術学部教授・芸術人類学研究所所長。
大学院修士卒業後、チベットでチベット仏教の修行をした。
チベット密教とフランス構造主義を関連づけて論じ、80年代ニューアカブームの寵児となる。
「聖なるもの」といった宗教の理解に関しては定評がある。
主な著作
- 虹の階梯〜チベット密教の瞑想修行 (ラマ・ケツン・サンポとの共著 1981.7 平河出版社→中公文庫)
- チベットのモーツァルト (1983.11 せりか書房→講談社学術文庫)
- 雪片曲線論 (1985.2 青土社→中公文庫)
- 観光 (細野晴臣との共著 1985.6 角川書店→ちくま文庫)
- 野ウサギの走り (1986.5 思潮社→中公文庫)
- イコノソフィア〜聖画十講 (1986.6 河出書房新社→河出文庫)
- 虹の理論 (1987.6 新潮社→新潮文庫)
- 悪党的思考 (1988.7 平凡社→平凡社ライブラリー)
- 蜜の流れる博士 (1989.5 せりか書房)
- ブッダの箱舟 (夢枕獏、宮崎信也との共著 1989.10 河出書房新社→河出文庫)
- バルセロナ、秘数3 (1990.6 中央公論社→中公文庫)
- 東方的 (1991.3 せりか書房)
- ファンダメンタルなふたり (山田詠美との共著 1991.12 文藝春秋→文春文庫)
- ゲーテの耳 (1992.7 河出書房新社→河出文庫)
- 知天使のぶどう酒 (1992.7 河出書房新社→河出文庫)
- 森のバロック (1992.10 せりか書房)
- 幸福の無数の断片 (1992.10 河出文庫)
- 宗教入門 (1993.2 マドラ出版)
- 三万年の死の教え〜チベット「死者の書」の世界〜 (1993.9 角川書店→角川文庫ソフィア)
- はじまりのレーニン (1994.6 岩波書店→同時代ライブラリー→現代文庫)
- リアルであること (1994.9 メタローグ→幻冬社文庫)
- 哲学の東北 (1995.5 青土社→幻冬社文庫)
- 日本人は思想したか (梅原猛、吉本隆明との共著 1995.6 新潮社→新潮文庫)
- それでも心を癒したい人のための精神世界ブックガイド (いとうせいこう、すが秀実との共著 1995.12 太田出版)
- サンタクロースの秘密 (レヴィ=ストロースとの共著 1995.12 せりか書房)
- 純粋な自然の贈与 (1996.6 せりか書房)
- ポケットの中の野生 (1997.9 岩波書店→新潮文庫)
- 音楽のつつましい願い (山本容子との共著 1998.1 筑摩書房)
- ブッダの夢 (河合隼雄との共著 1998.2 朝日新聞社→朝日文庫)
- 女は存在しない (1999.11 せりか書房)
- フィロソフィア・ヤポニカ (2001.3 集英社)
- 緑の資本論 (2002.5 集英社)
- 人類最古の哲学−カイエ・ソバージュ<1> (2002.1 講談社選書メチエ)
- 熊から王へ−カイエ・ソバージュ<2> (2002.6 講談社選書メチエ)
- 愛と経済のロゴス−カイエ・ソバージュ<3> (2003.1 講談社選書メチエ)
- 神の発明−カイエ・ソバージュ<4> (2003.7 講談社選書メチエ)
- 仏教が好き! (河合隼雄との共著 2003.8 朝日新聞社)
- 精霊の王 (2003.11 講談社)
- 対称性人類学−カイエ・ソバージュ<5> (2004.2 講談社選書メチエ)
- 網野善彦を継ぐ。(赤坂憲雄との共著 2004.6 講談社)
- 僕の叔父さん網野善彦 (2004.11 集英社新書)
- モカシン靴のシンデレラ (2005.3 マガジンハウス)
- アースダイバー (2005.6 講談社)
- 狩猟と編み籠 対称性人類学2 (2008,5 講談社 芸術人類学叢書 1)