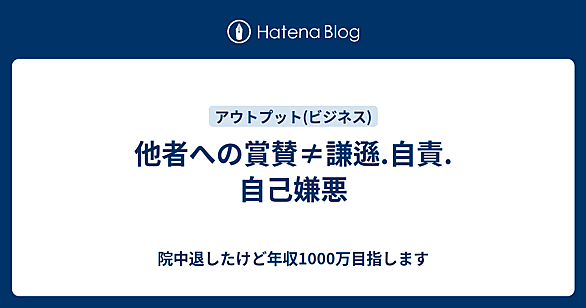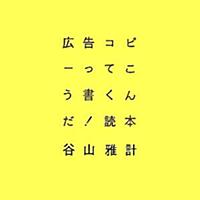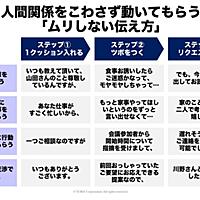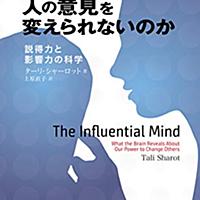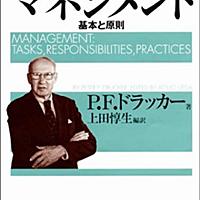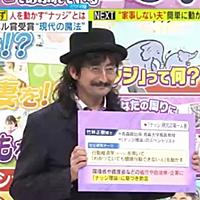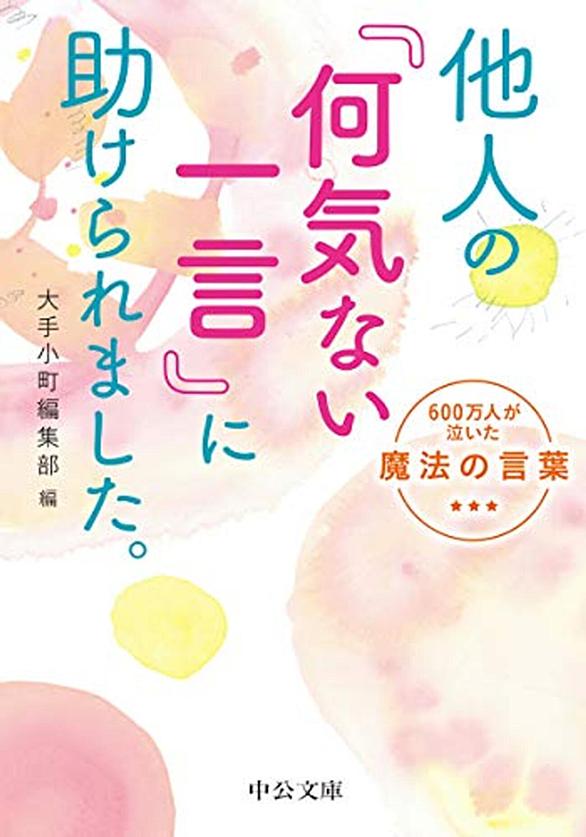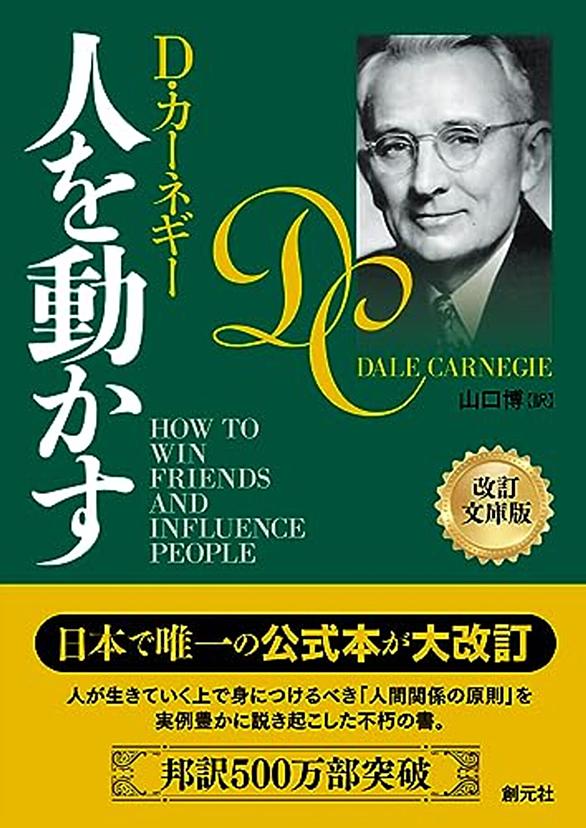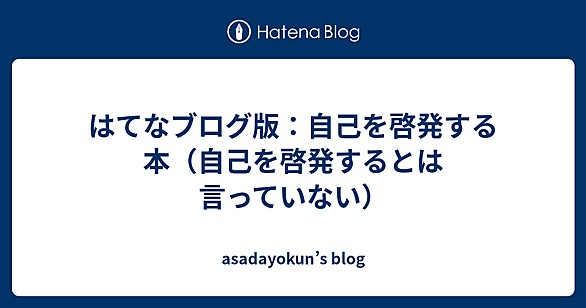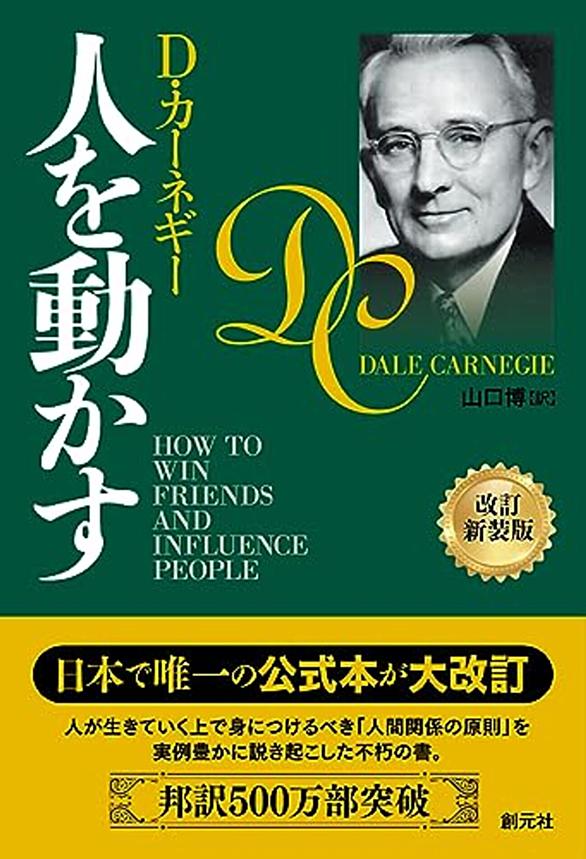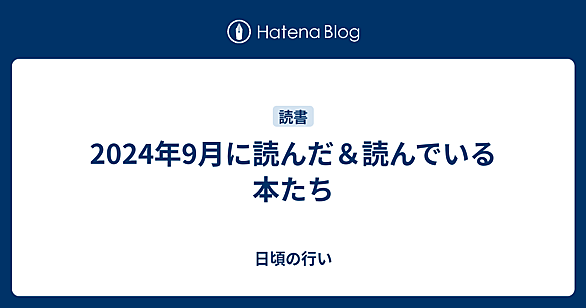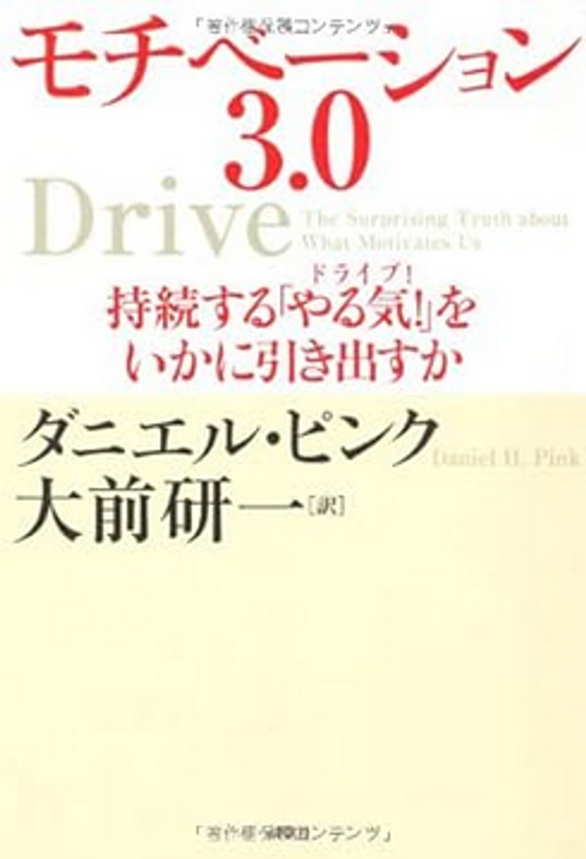人を動かす
(読書)
【ひとをうごかす】
『How to Win Friends and Influence People』
デール・カーネギーによる自己啓発書。人間関係の秘訣について、具体例を挙げながら分かりやすく示してある。現在の自己啓発書の原点とも言われている。発売から50年が過ぎた現在でも売れ続ける超ロングセラーとなっている。日本での売り上げは430万部、世界では1500万部以上。

- 作者: デールカーネギー,Dale Carnegie,山口博
- 出版社/メーカー: 創元社
- 発売日: 1999/10/31
- メディア: 単行本
- 購入: 174人 クリック: 3,319回
- この商品を含むブログ (615件) を見る