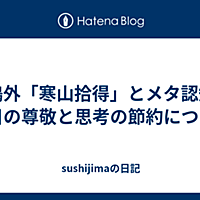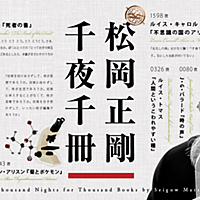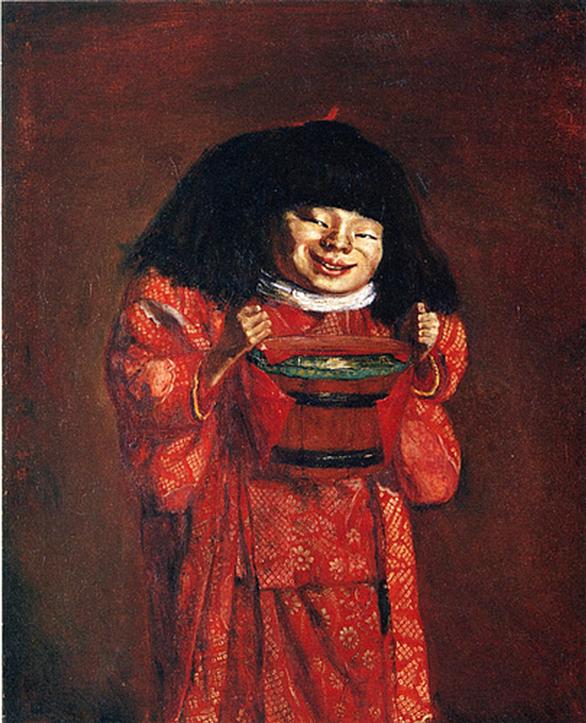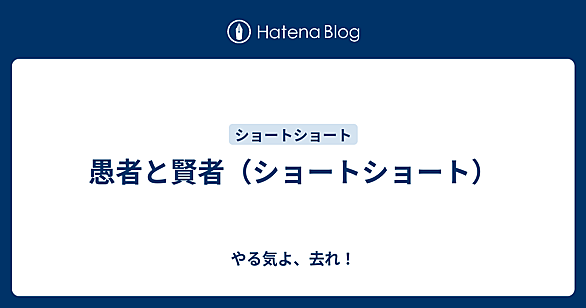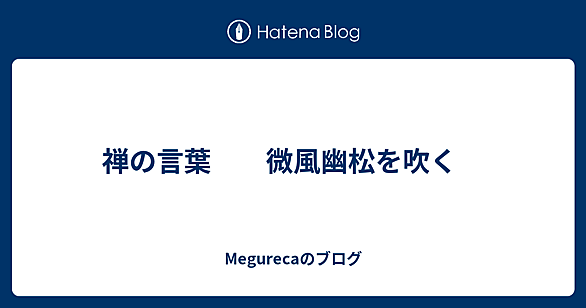寒山拾得
(読書)
【かんざんじっとく】
森鴎外の小説。初出:大正5年1月「新小説」
この小説の原拠は「寒山子詩集」序や「宋高僧伝」にある。「寒山拾得縁起」によると、子供たちにせがませてはなしてやったものを、そのまま書いたのだという。
この作品で鴎外は、本当の価値もわからずに、盲目の尊敬をする俗世間の役人たちを戯画化した。痛烈な批判である。

鴎外歴史文学集〈第4巻〉寒山拾得・細木香以・寿阿弥の手紙ほか
- 作者: 森鴎外,須田喜代次,小泉浩一郎
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2001/06/28
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 12回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 森鴎外
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1987/09
- メディア: 文庫
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る

高瀬舟,寒山拾得 CBS/SONY BOOKS ON CASSETTE 4
- 作者: 森鴎外
- 出版社/メーカー: ソニー・マガジンズ
- 発売日: 1987/07
- メディア: 文庫
- クリック: 3回
- この商品を含むブログを見る