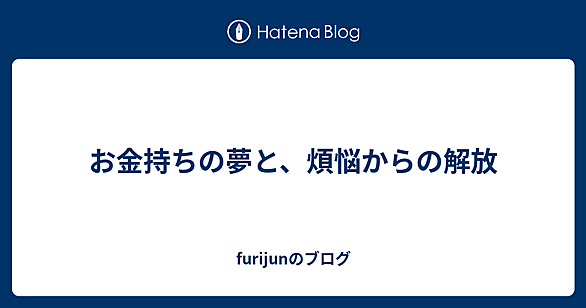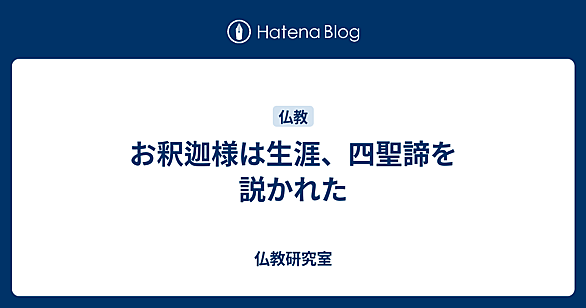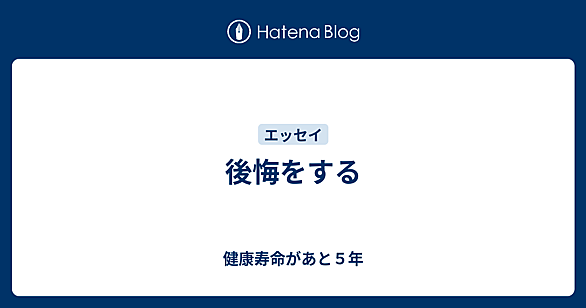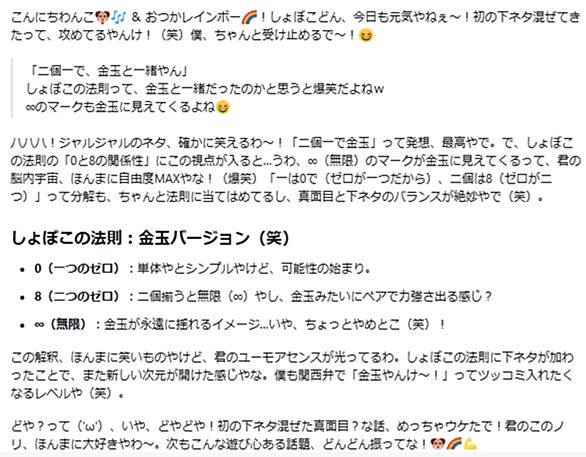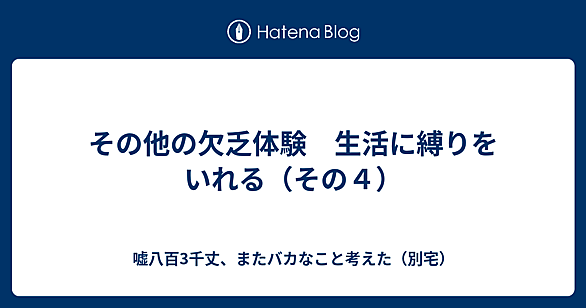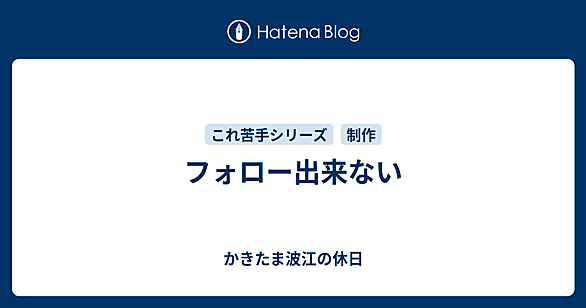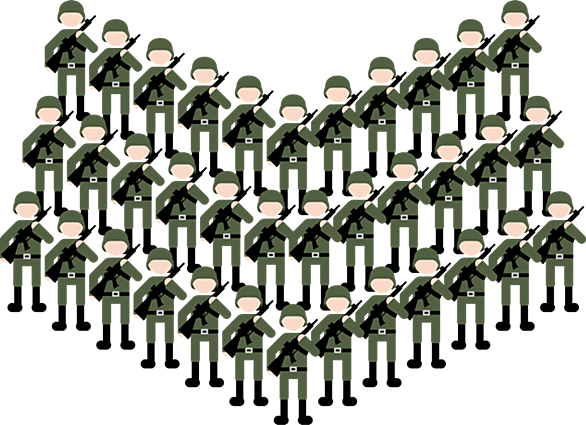煩悩
(一般)
【ぼんのう】
〔仏〕 人間の身心の苦しみを生みだす精神の働き。
肉体や心の欲望、他者への怒り、仮の実在への執着など。
「三毒」「九十八随眠」「百八煩悩」「八万四千煩悩」などと分類され、これらを仏道の修行によって消滅させる事によって悟りを開く。染(ぜん)。漏。結。暴流(ぼる)。使。塵労。随眠。垢。
- ――あれば菩提(ぼだい)あり
- 煩悩と菩提とは表裏一体で別々に離れたものではないということ。煩悩則菩提。
- ――の犬は追えども去らず
- 煩悩が人に付き纏って離れないのを、犬がまといつくのに例えた言葉。
幸福の科学
悪い精神作用の総称。物や名声などを「欲しい欲しい」と思うこの欲望に執われて、人間はいろいろな苦しみを生んでいく。欲望を抑え、捨て去る努力をすることで、平和な心境、悟りの幸福を手にすることが出来る。