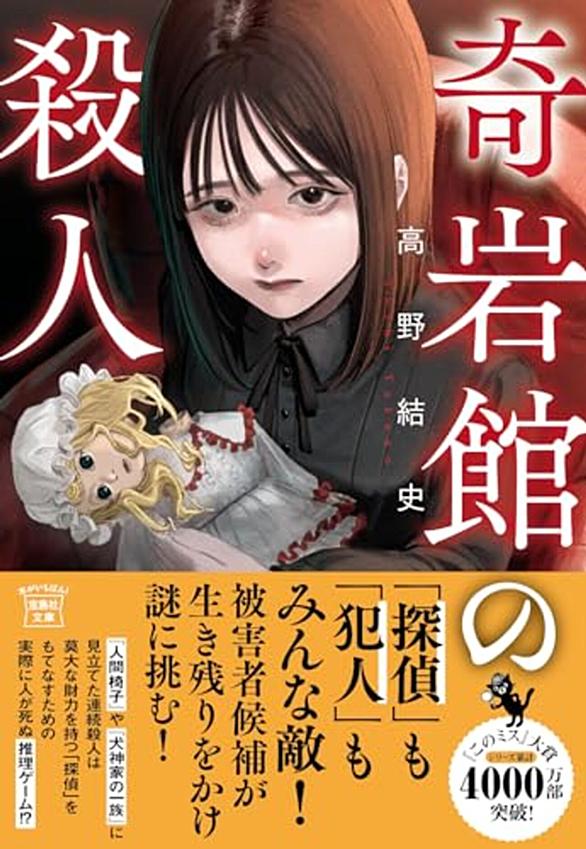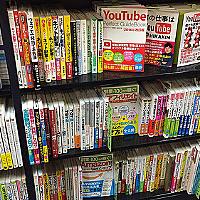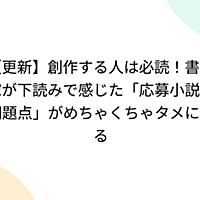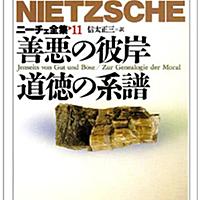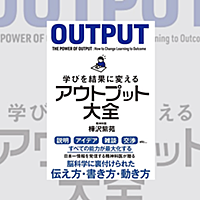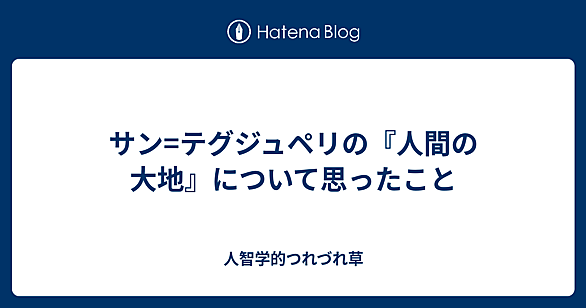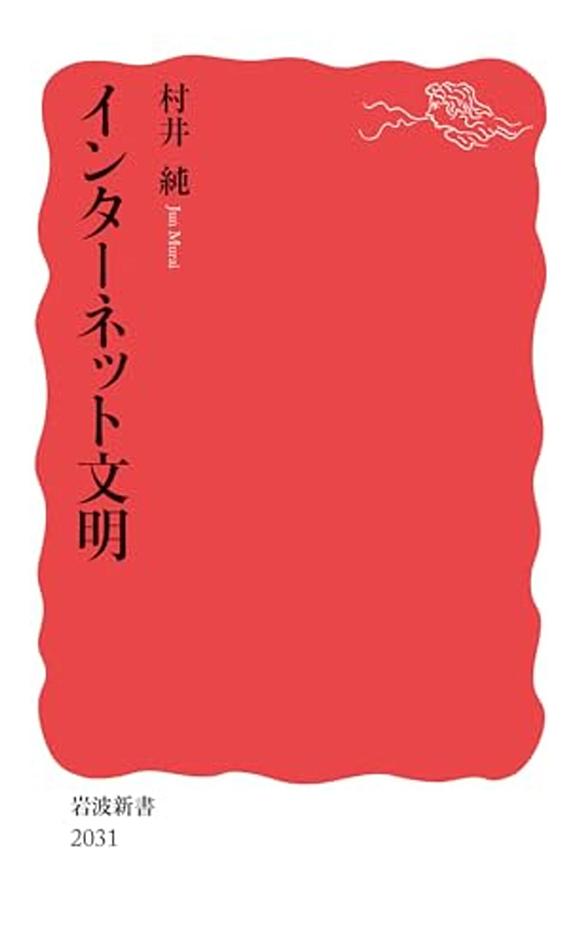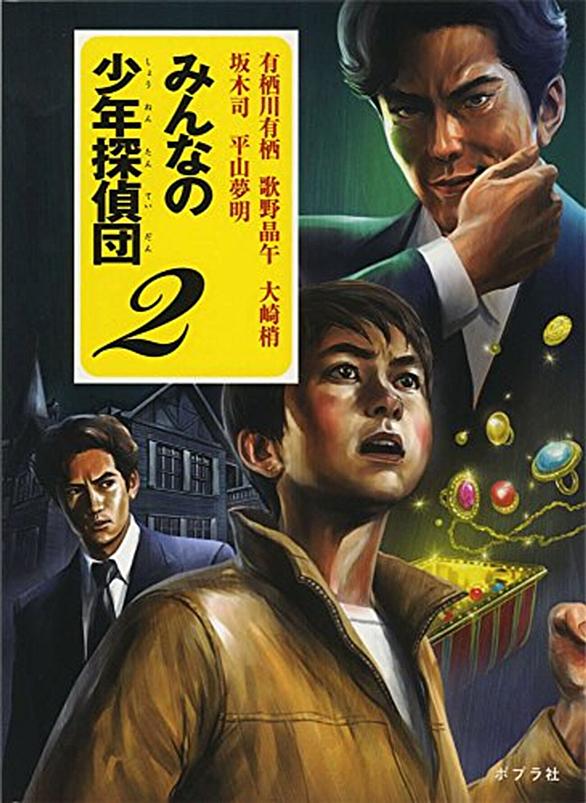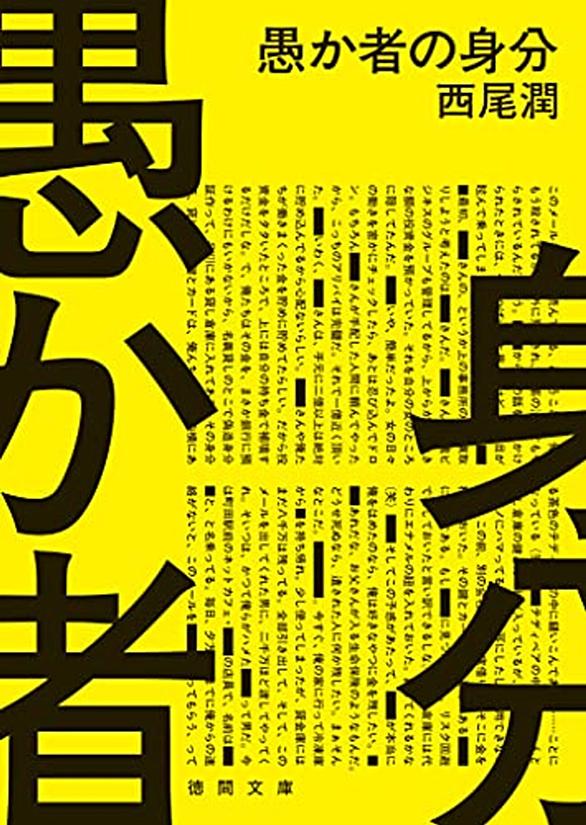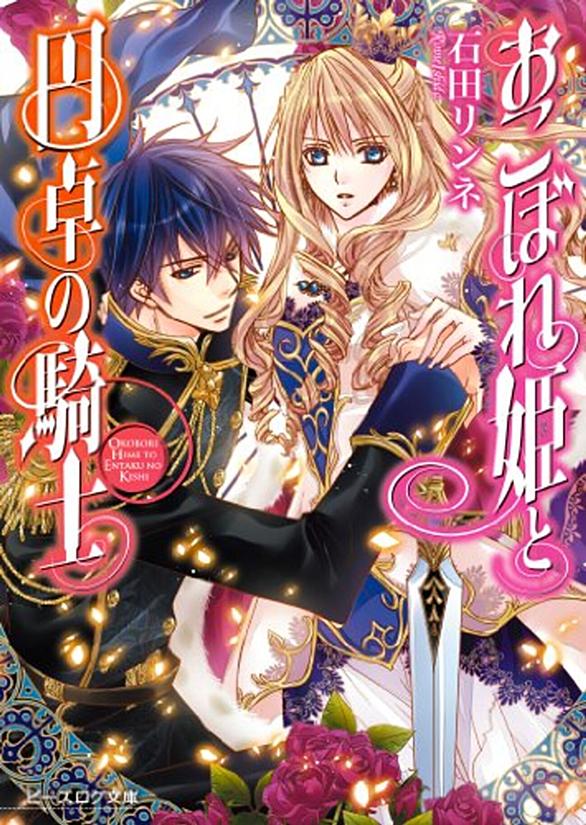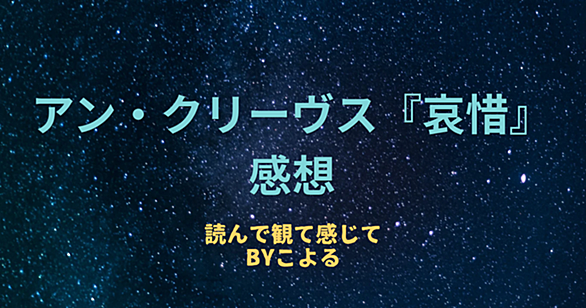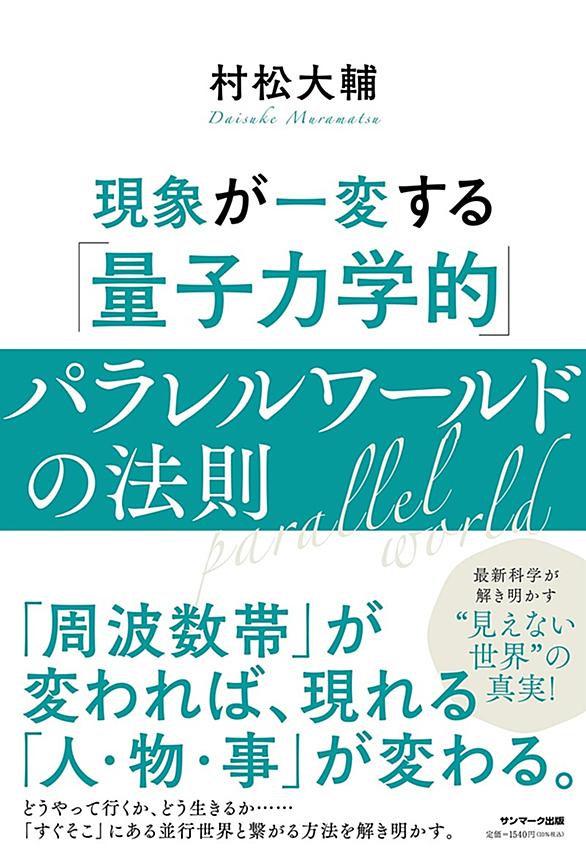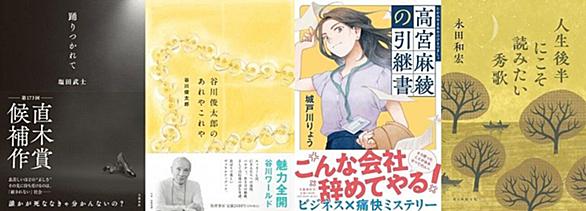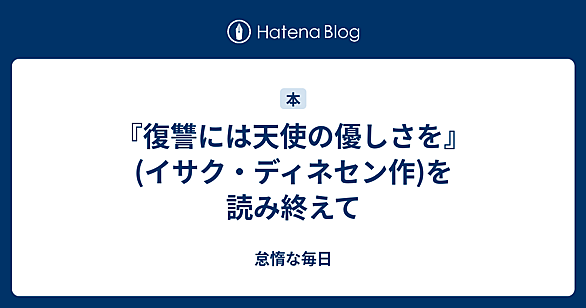書評
(読書)
【しょひょう】
本の紹介文、ブック・レビュー。
通常はいわゆる新刊本について行われることが多く、読者の書籍選びにあたって参考に供する意味を持つ。

- 作者: 豊崎由美
- 出版社/メーカー: 光文社
- 発売日: 2011/04/15
- メディア: 新書
- 購入: 3人 クリック: 165回
- この商品を含むブログ (64件) を見る
関連リンク
書評 - Wikipedia
好書好日|Good Life With Books
http://www.yomiuri.co.jp/book/review/
書評サイト-本スキ。
ビジネス書の書評・要約まとめサイト bookvinegar-ブックビネガー
HONZ - 読みたい本が、きっと見つかる!