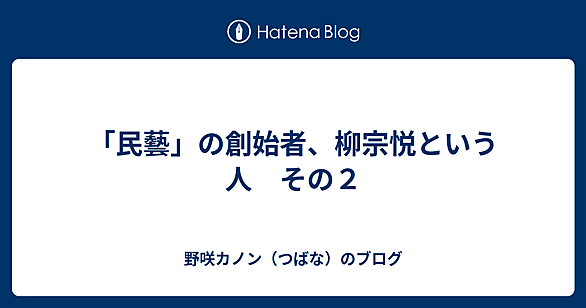民藝運動
(アート)
【みんげいうんどう】
民藝美すなわち「用の美」を提唱し、使うことに忠実に作られたものに自ずと生ずる自然で暖かみのある美しさを世に紹介し広めようとする活動。
柳宗悦らを中心に1926年(大正15年)に「日本民藝美術館設立趣意書」が発表されたのが始まりとされ、具体的に行なわれた活動は以下の通り。
- 伝統の中で形作られた古い民藝品の発掘・蒐集した。
- すたれつつあった伝統的な手仕事によりできたものを発見し、技術を復興した。
- 伝統を踏まえて時代に即した新しいものづくりを推進し、 指導者となる個人作家の支援を行った。
また、柳は活動の拠点として日本民藝館を設立、また、運動の趣旨と成果を雑誌「工藝」(雑誌「民藝」の前身) などの出版物にまとめ、発行した。
日本民藝館HP
http://www.mingeikan.or.jp/