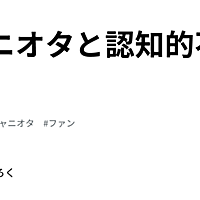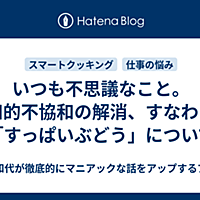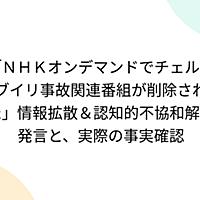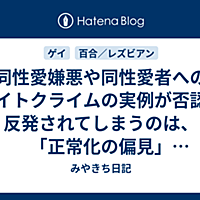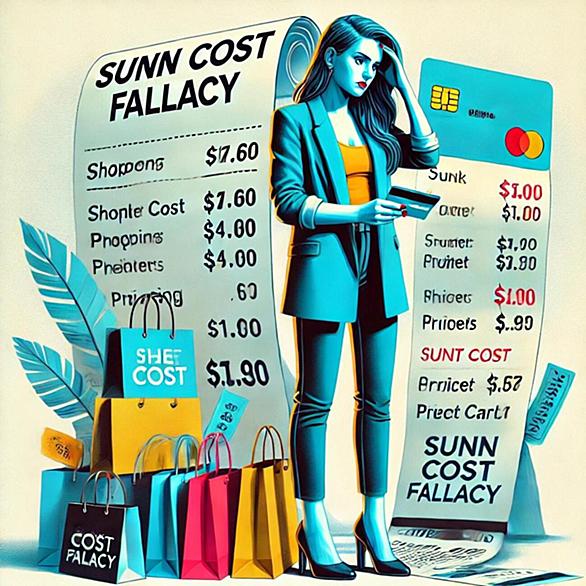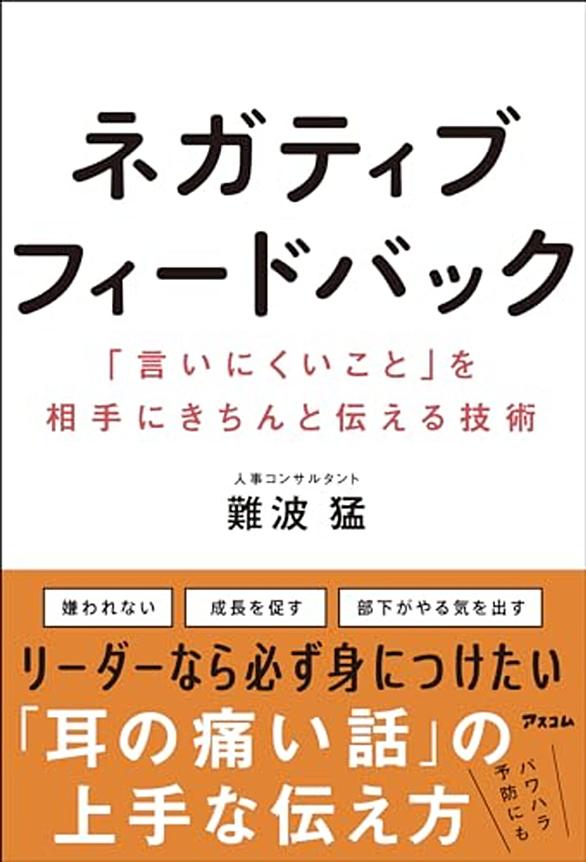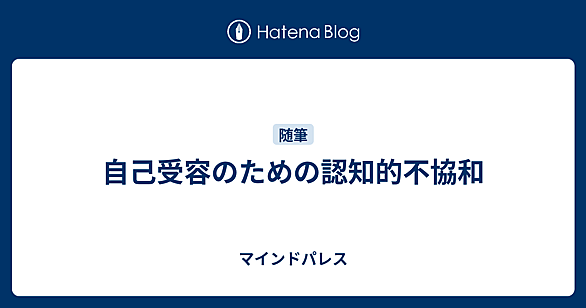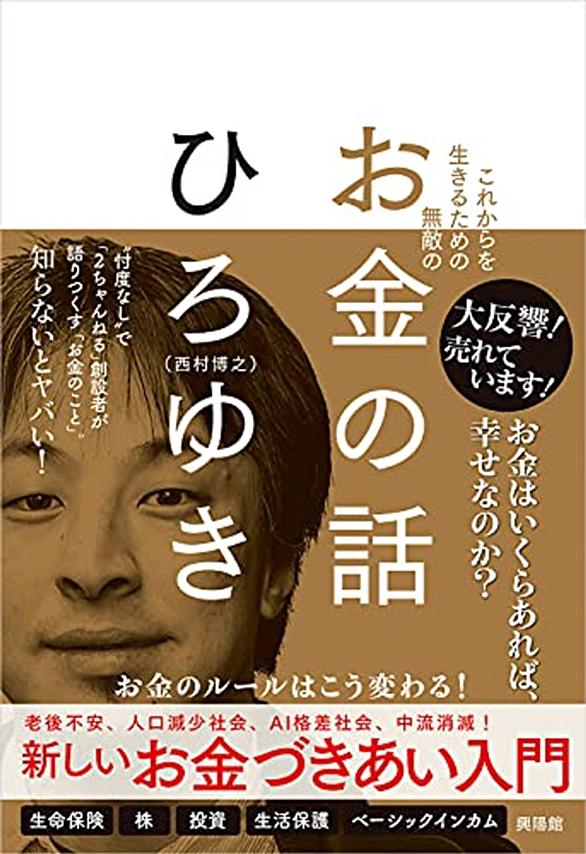認知的不協和
(サイエンス)
【にんちてきふきょうわ】
心理学の用語。
1975年、アメリカの社会心理学者フェスティンガーが提唱。
人は何らかの物事に遭遇した場合(認知)、それが自分が持っている「認知」と相容れない場合(不協和)、
その「不協和」を解消しようとすること。(不協和の逓減)
不協和の逓減《ていげん=しだいにへらすこと》には以下の3つがある。
- 「認知」を変える(現実を変えたり、考えを変える)
- 「認知」の重要性を低くする(事実を軽視したり、無視する)
- 新しい「認知」を追加する(屁理屈や問題のすりかえ)
1や2のように、「変化」をさせたり「否定」をすることはコストが高いため、
実際には、3が選択されることが多い。