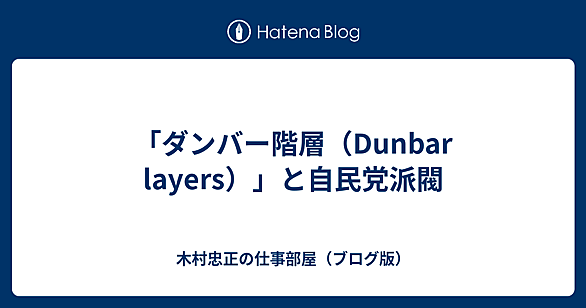ダンバー数
(サイエンス)
【だんばーすう】
「強制的な規範」や「法」を抜きに、安定した社会関係を結ぶことができる人間集団などの数として主張されている仮説。
提唱者のロビン・ダンバーは「霊長類大脳の新皮質の占める割合」と「それぞれの群れの構成数」には相関関係があると主張している。
ダンバーの論文。
http://www.liv.ac.uk/evolpsyc/Evol_Anthrop_6.pdf
そこから、人間における「ダンバー数」は「150」程度だとする主張が多く、ビジネス書などにも組織論のひとつとして引用されることがある。