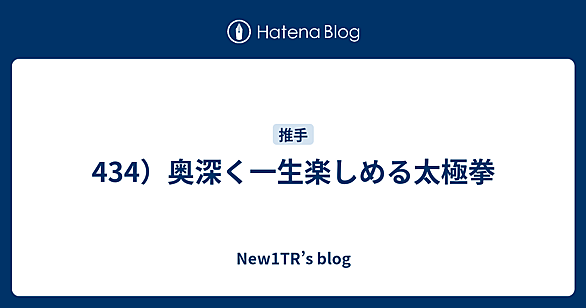化勁
(一般)
【かけい】
hua4jin4(ホァジン)
中国武術用語
相手の勁を変化させること(化、ホァ)。聴勁も参照されたし。特に太極拳で重要視される。
相手の勁を聴くこと(聴勁)ができて、自らも正しく勁を出す事(発勁)ができてはじめて化勁の必要条件が満たされる。
化勁の最初の段階では相手の勁を自分の脅威とならない方向に変化させる。さらに段階が進めば相手の勁を利用しつつ、自分の勁を加えそのまま相手を崩すことが可能になる。したがってレベルの高い太極拳家等、化勁の上級者に攻撃を当てるのは至難となる。