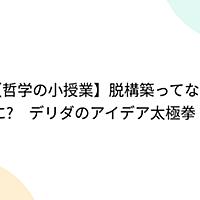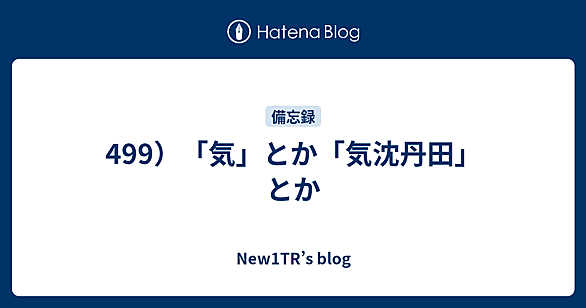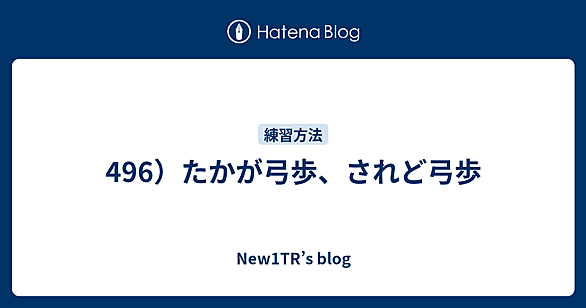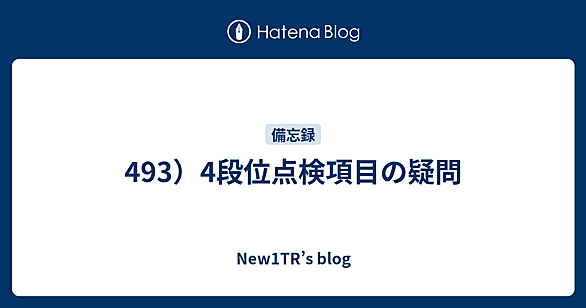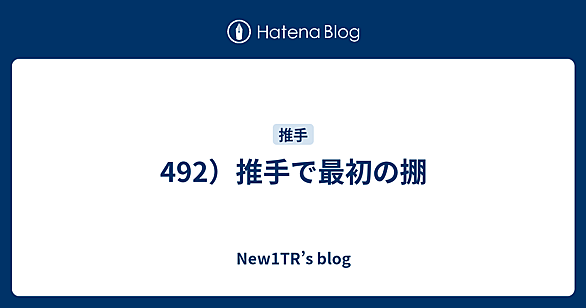太極拳
(一般)
【たいきょくけん】
Tai ji quan (英語ではtai chi)
中国武術の一種。形意拳・八卦掌とともに三宗内家拳に含まれ、少林拳と並んで中国武術二大流派に数えられる。
道教の思想を強く反映しており、(格闘技や健康法としてだけではなく)哲学的な深みも有している。世界中に修行者や愛好家が存在。
現在は陳式・楊式・呉式・孫式などの太極拳があり、更に簡化太極拳・総合太極拳など、多岐の種類に別れている。
以下はその内で代表的なものの説明。
- 陳式
- 明末清初、河南省温県陳家溝の陳王廷が創始。全ての太極拳の源流。動作は実戦的で、剛柔に富み、激しく力強い。
- 楊式
- 河北省の楊露禅が陳式を元に編纂。型がのびのびとして端正。
- 呉式
- 河北省の呉鑑泉が楊式を元に編纂。前傾、平行な足、ゆっくりと細かい動きが特徴。
- 武式
- 河北省の武兎襄が陳式・楊式を元に編纂。動きは小さく他の太極拳に比べ簡素で明快。実戦的な太極拳。
- 孫式
- 河北省の孫祿堂が武式・形意拳・八卦掌を元に編纂。動きは生き生きと変化がある。開合活歩太極拳とも称される。
- 簡化
- 中国体育委員会が健身を目的として楊式を元に編纂。24式・48式・32式剣があり、それに他の流派の風格を加えたものが88式。
- 総合
- 1989年に中国武術協会・中国武術研究院が競技用目的として陳式・楊式・呉式・孫式を元に制定した、競技用のもの。42式とも呼ばれる。1990年のアジアオリンピックで正式種目に加えられた競技「武術(うーしゅう)」の一種目でもある。
- その他
- 日本連盟編纂の入門・初級、国際武術連盟編纂の8式・16式などがある。