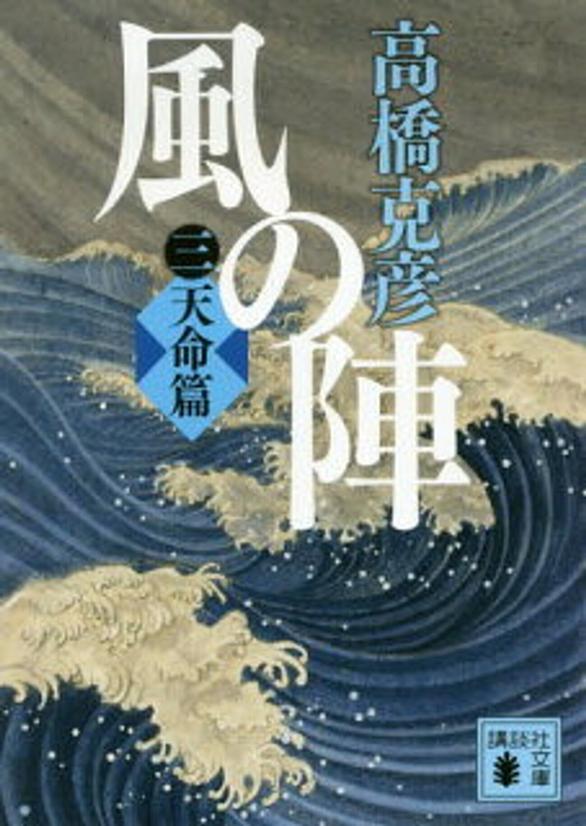宇佐八幡宮神託事件
(社会)
【うさはちまんぐうしんたくじけん】
神護景雲3年(769年)9月25日に称徳天皇が輔治能清麻呂(和気清麻呂)とその姉・法均を讒言の罪で処罰したことについて、道鏡が天皇位を得ようとしたとされる事件。称徳天皇自身の詔では讒言の内容は語られていない。
なお、戦前教育において道鏡が異国の宗教・仏教を広めたのみならず皇位簒奪を企てた大悪人とされていた経緯から一般に皇位簒奪事件として知られているが、『続日本紀』他の道鏡や称徳天皇の扱い方は作為的であり、そもそも道鏡に皇位簒奪の意思があったかどうか議論がある。
孤立した藤原仲麻呂が恵美押勝の乱で討死した後に孝謙上皇は重祚し称徳天皇となるも、不破内親王の処罰など皇族への粛清*1が行われるなど皇位継承問題は解決されないどころか逆にもつれており、また天皇は太政大臣に道鏡、右大臣に吉備真備を任命し弓削氏を重用するなど藤原氏勢に反抗的な姿勢をとっていた。
『続日本紀』による記述
『続紀』神護景雲3年(769年)9月25日、天皇の詔
同日の記述
- 大宰主神・習宜阿曾麻呂が道鏡に媚びて「道鏡が即位すれば天下は太平になるであろう」と言うと道鏡は喜び自信を持った
- 天皇の夢に八幡神の使いがきて法均を遣わすようにと告げたが、天皇は代わりに清麻呂を遣わした
- 道鏡は清麻呂を懐柔しようとしたが、清麻呂は大神の「皇族を太子に立て無道な者は退けよ」との託宣を奉じた
- 道鏡は激昂して清麻呂の本官を解き、因幡員外介に左遷した
- 清麻呂が任国へ着く前に続いて詔があり、官位を剥奪して籍を削り大隅国に配流された
- 法均は還俗させられ備後国に配流された
『続紀』神護景雲4年(770年)8月21日、皇太子(後の光仁天皇)の令旨
- 聞くところによると道鏡は久しく皇位を狙っていたという
- 悪賢い陰謀は発覚したが、先帝の恩を考えるに処刑するのは忍びないので道鏡は造下野国薬師寺別当に派遣する
『続紀』宝亀2年(771年)2月2日、藤原永手没伝
- 道鏡は称徳天皇の恩を私事に利用して権勢を振るった
- 淳仁天皇廃位後は皇族で人望のある者は無実の罪で処罰され皇統が絶えそうになった
- 道鏡は皇位簒奪の野望を抱き始めたが、称徳天皇崩御に及んで永手が光仁天皇を立て国家を安定させた
『続紀』宝亀3年(772年)4月7日、道鏡没伝
- 孝謙上皇は道鏡を崇敬するあまり天子の輿の使用を許し天皇と同じ待遇にした
- 上皇は政務の全てを道鏡に決めさせた
- 大宰主神・習宜阿曾麻呂が宇佐八幡宮の神示と誑かし、道鏡は皇位を狙うようになった
- 先帝の寵愛があったので処刑はしなかったが、葬るときは庶人と同じようにした
『日本後紀』
- 道鏡が人を遣わして清麻呂を殺そうとした
*1:孝謙朝の橘奈良麻呂の乱、淳仁朝の恵美押勝の乱では他の皇族の即位が企てられていた。