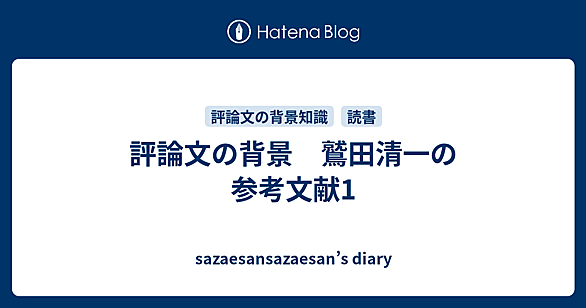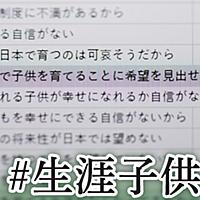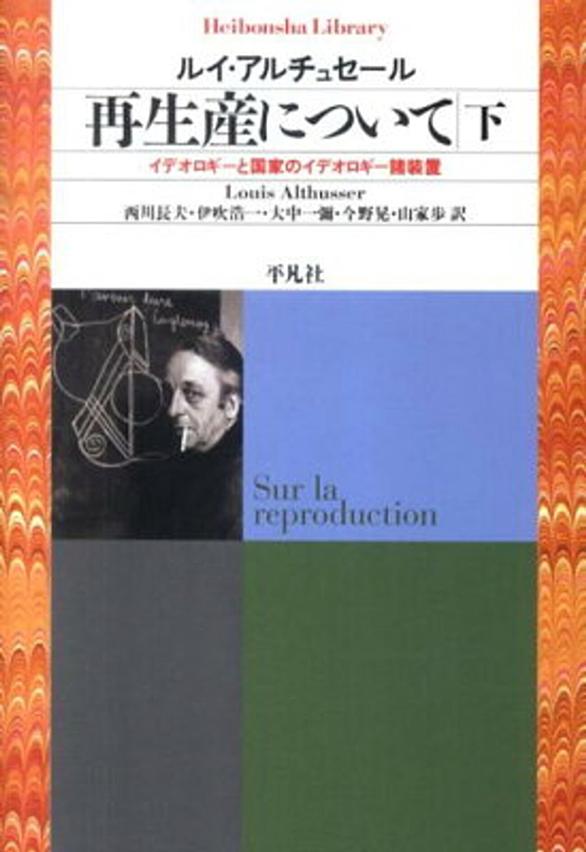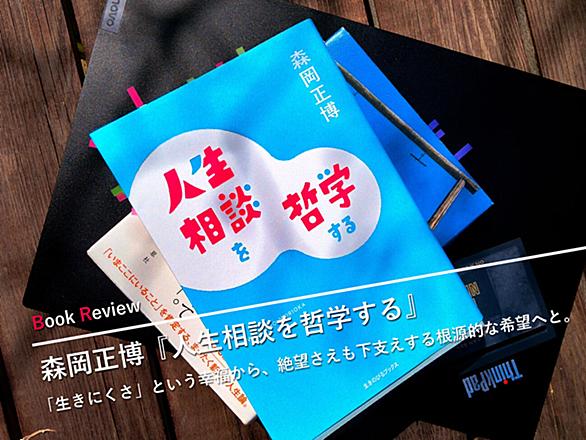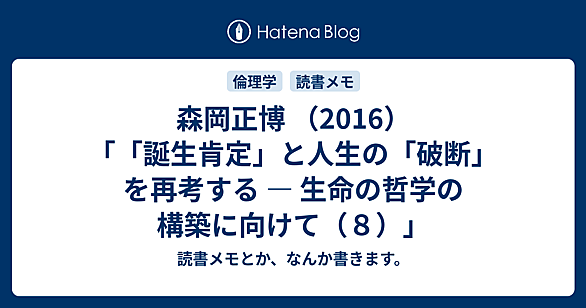森岡正博
(読書)
【もりおかまさひろ】
哲学者。
専門は、現代思想、生命学、倫理学。id:kanjinai。
hatenaでは哲学系チームブログG★RDIASのメンバー。
プロフィール
1958年、高知県生まれ。
1988年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学(倫理学)。
1988年4月、東京大学文学部助手。
1988年10月、国際日本文化研究センター助手。
1997年4月、大阪府立大学総合科学部助教授。
1998年4月、同教授。
2005年4月、大阪府立大学人間社会学部人間科学科教授。