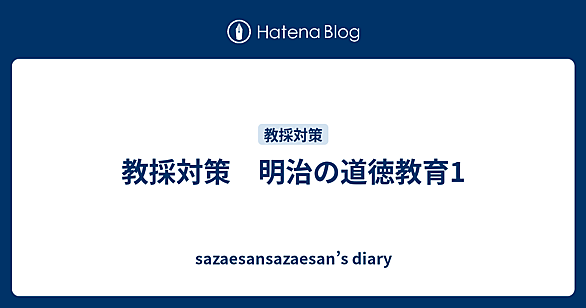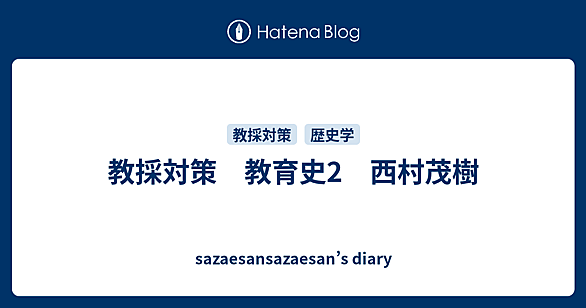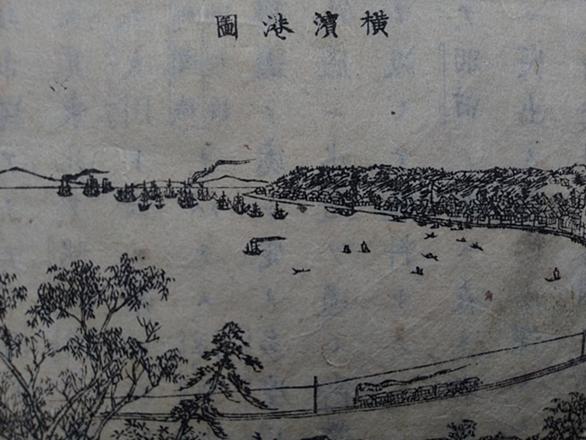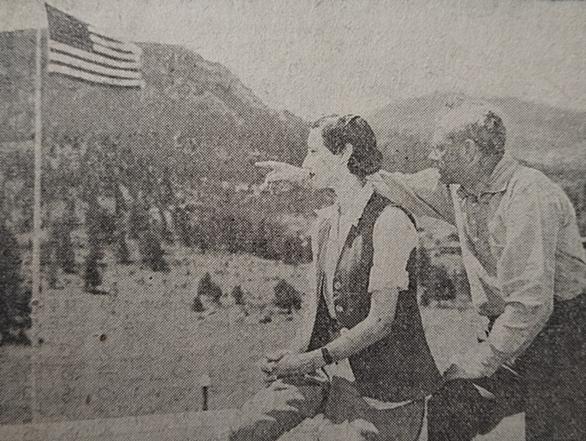森有礼
(一般)
【もりありのり】
1847-1889 薩摩藩出身
明治新政府の外交官、初代文部大臣。明六社の結成メンバーの一人。
http://www.ndl.go.jp/portrait/datas/204.html?c=0
幸福の科学
森有礼・・・(1847~1889年)薩摩藩出身の政治家。初代文部大臣。一橋大学を創設した、明治六大教育家の一人。「良妻賢母教育こそ国是とすべき」と、女子教育にも力を入れた。
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る5ブックマーク八咫鏡(やたのかがみ)と神の御名(み名) - 明治時代の文部大臣 森有礼が唱えた「神鏡ヘブル文字説」の謎に迫る - (疲れた心に強い翼を! -You are loved- あなたは愛されている)「疲れた心に強い翼を! -You are loved- あなたは愛されている」のサイトマップ 伊勢神宮の内宮と,宮中の賢所にあるとされる 八咫鏡[天照大神の御魂代]に書いてある文字の謎に迫る - 明治時代の文部大臣,森 有礼が唱えた「神鏡ヘブル文字説」 - 日本の天皇家に伝わる神宝「八咫鏡」 - 天照大神が皇孫に賜ったもの -... godpresencewithin.web.fc2.com
godpresencewithin.web.fc2.com