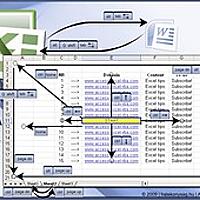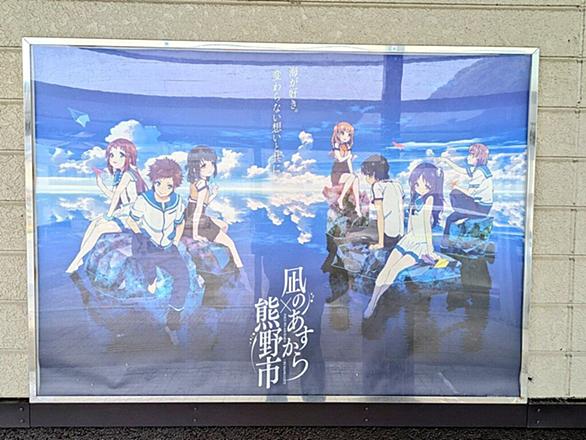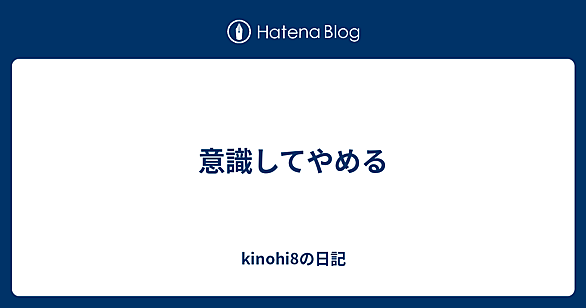熊野
(地理)
【くまの】
和歌山県 新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、古座川町、北山村 さらに三重県熊野市、紀宝町、御浜町 あたり一帯をさす地域。
熊野三山
- 熊野坐(にます)神社(本宮)
- 熊野速玉神社(新宮)
- 熊野那智大社(那智勝浦)
出雲民族との関連が深く、神武天皇は三輪崎(新宮)に上陸し、大和に入っていったという伝説がある。
さらに浄土信仰と結びつき、補陀落信仰、熊野行幸・熊野詣(熊野古道)、修験道などへとつながっていく。
地名の由来には、色々あるが、「隠国・こもりく」→「隠野・こもりの」→「くまの」と転化したという説がある。
隠野とは、黄泉に通じる国という意味。
神武東征以前から、ニシキトベという女性リーダーのもと、独自の文化が開けていたといわれる。
熊野に住む人々にとって、熊野とは、単なる地名ではなく、独自の文化が息づくところという自負と思い入れがあり、自ら熊野人といったりする。
生と死を対立するもの(二元論・要素論)としては捉えず、一体のもの(全体論)と捉える世界観があり、鬱蒼と茂る森がその死につながる世界、甦る世界と捉える。
また、神武東征後反権力の気骨も続いてきた。新宮市は、1910年大逆事件の舞台となった。
ドクトル大石(大石誠之助)を育て、佐藤春夫を育て、中上健次を育てたのも熊野。
熊野詣は、熊野三山にたどり着くことが目的ではなく、一歩一歩自分の足を確かめながら歩くことこそが、修行であると捉える。