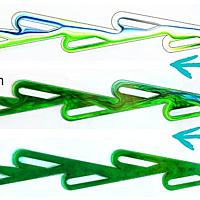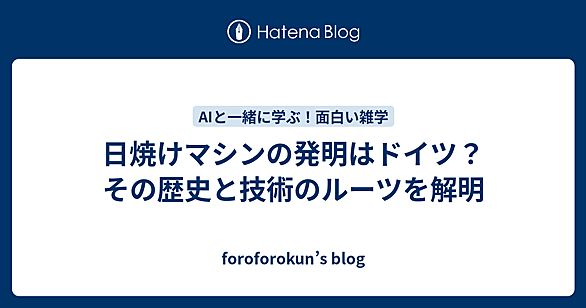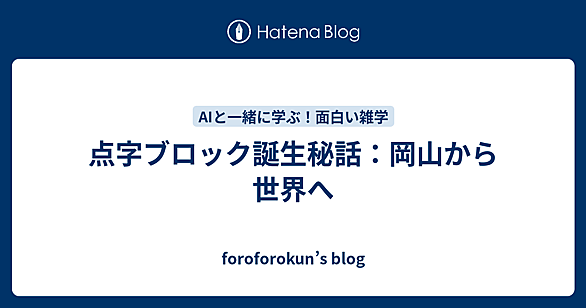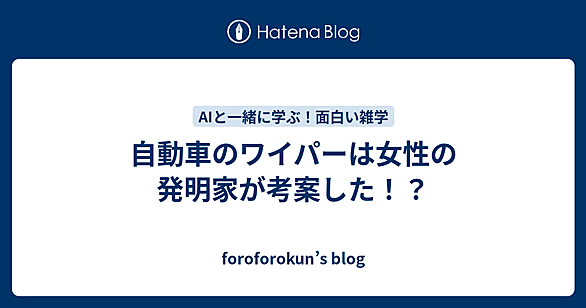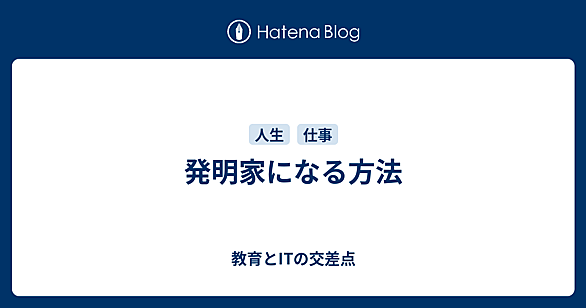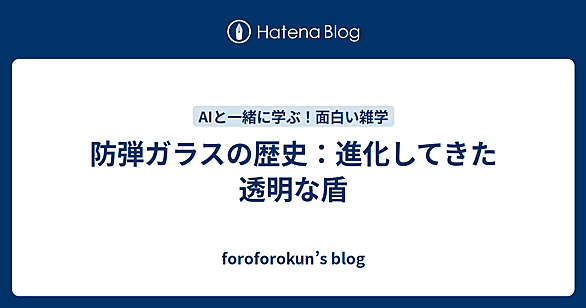発明
(一般)
【はつめい】
今まで世の中になかったような、新しいものや新しい考え方を、思いついたり考え出したり作り出したりすること。
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの(特許法2条1項)
用語説明
- 自然法則 :ニュートンの万有引力の法則、アインシュタインの相対性理論等
- 利用 :利用が要件なため、上記自然法則の発見は発明足りえない
- 技術的思想:技術を駆使するための考え方をいう。熟練を要する技能は含まれない。
- 創作 :思いつき等は含まれない
- 高度 :実用新案との差異を設けたもの
コメント
随分難しそうですが、なんか理系っぽいものだということと、思いつきではだめで、解決課題とその解決方法が示されていないとだめということがわかればOKでしょう。
特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
日本弁理士会ホームページ
http://www.jpaa.or.jp/