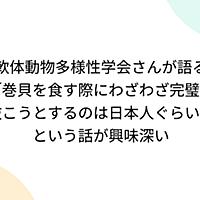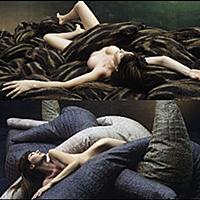軟体動物
(動植物)
【なんたいどうぶつ】
動物分類上の一門。体はやわらかく、頭部・足部・内臓嚢(のう)よりなる。内臓嚢の表皮が伸びてできる外套膜に包まれ、通常、外套膜が分泌する石灰質の殻におおわれるが、退化・欠如する種もある。開放血管系と集中神経系をもつ。海産・淡水産の種は鰓(えら)を、陸産の種は肺をもつ。雌雄同体のものと異体のものとがあり、トロコフォア幼生とベリジャー幼生を経て成体となる場合が多い。無板・多板・単板・腹足・掘足・二枚貝・頭足の七綱に分けられる。貝・ウミウシ・イカ・タコの類。
三省堂提供「大辞林 第二版」より