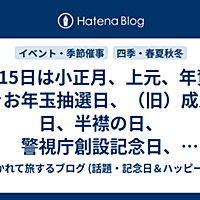小正月
(一般)
【こしょうがつ】
大正月(元日)に対し、旧暦の1月15日、または1月14日〜16日。新暦の1月15日に転じて指すことも。「二番正月」「女正月」とも。
大正月から小正月のまでの間を「松の内」と呼んでいたが、近年、その概念には地域差がある。
小豆粥
江戸時代から伝わる小正月の風習で、1月15日の朝に小豆を入れた粥を焚いて食べ、その年の豊作と無病息災を願うもの。小豆を含む七種の穀物を焚き合わせた粥を「七種粥」と言う。
関連行事
- 若木迎え(初山)
- どんど焼き(左義長)
- まゆ玉(餅花)作り
- 鳥追い
- 嫁つつき
- 地蔵年始
- みそぎ