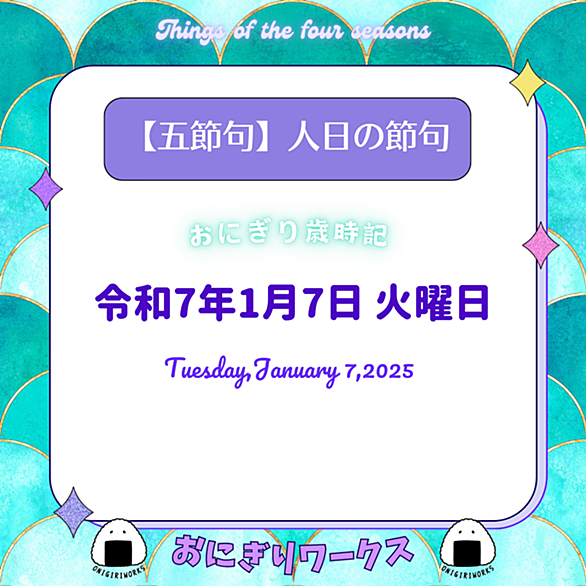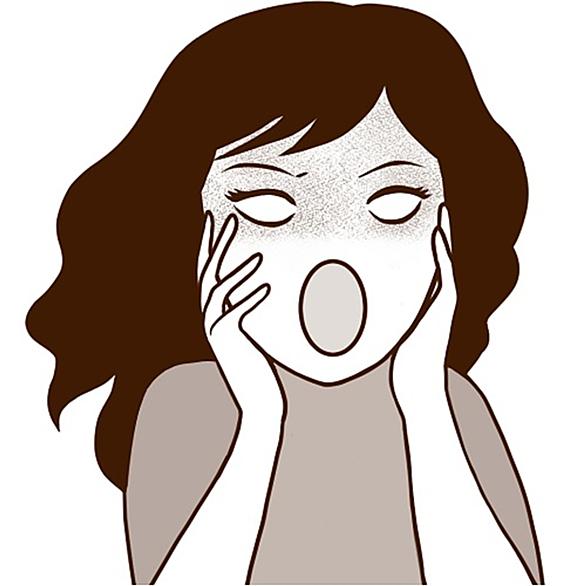五節句
(一般)
【ごせっく】
五節句とは、江戸時代に公式的に法制化された式日である5つの節句のこと。
- 人日(じんじつ,正月七日,七草の節句)→人日の節句
- 上巳(じょうし,三月三日,桃の節句)→上巳の節句
- 端午(たんご,五月五日,菖蒲の節句)→端午の節句
- 七夕(しちせき*1,七月七日,笹の節句)→七夕の節句
- 重陽(ちょうよう,九月九日,菊の節句)→重陽の節句
上巳は別名・女子の節句,端午は別名・男子の節句とも呼ばれる。
現在で特にメジャーなのは、上巳,端午,七夕であり、人日に関しても七草粥の風習が残っている。
一方、重陽に関してはどちらかというと公的な面が強く、あまり一般には定着していない。
*1:節句の名前としては「たなばた」とは読まない。