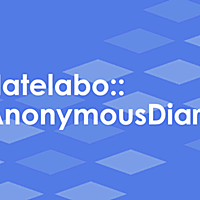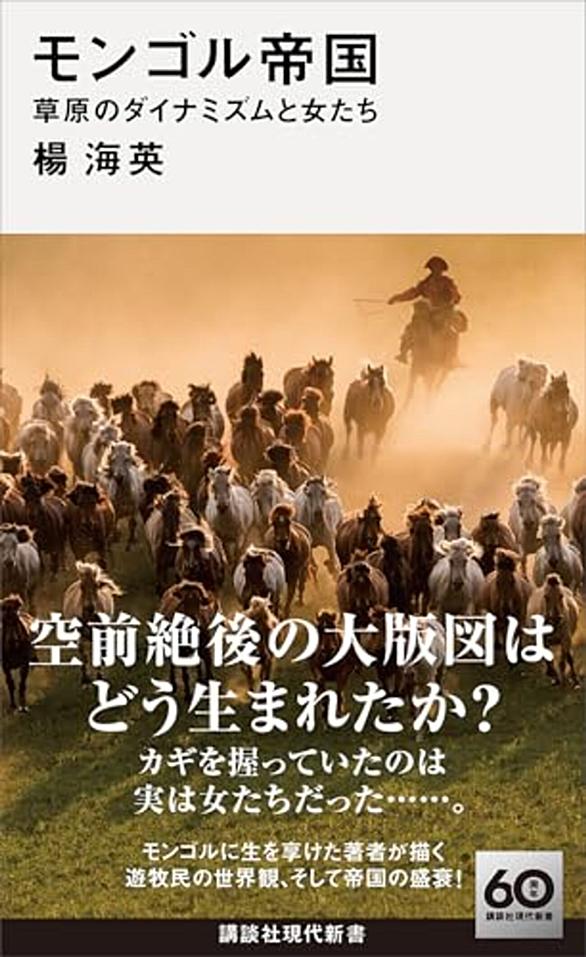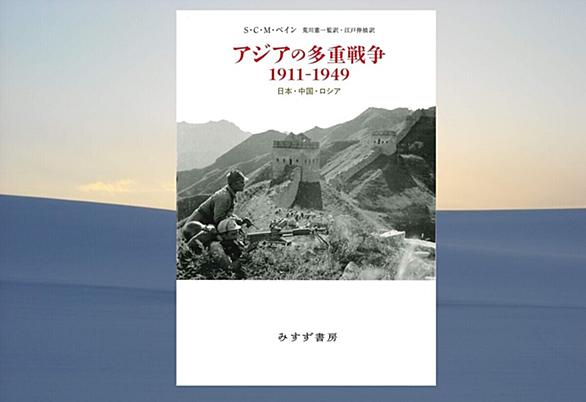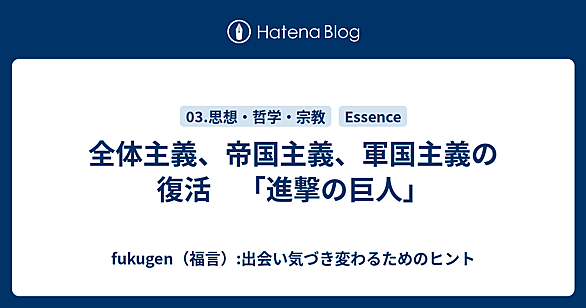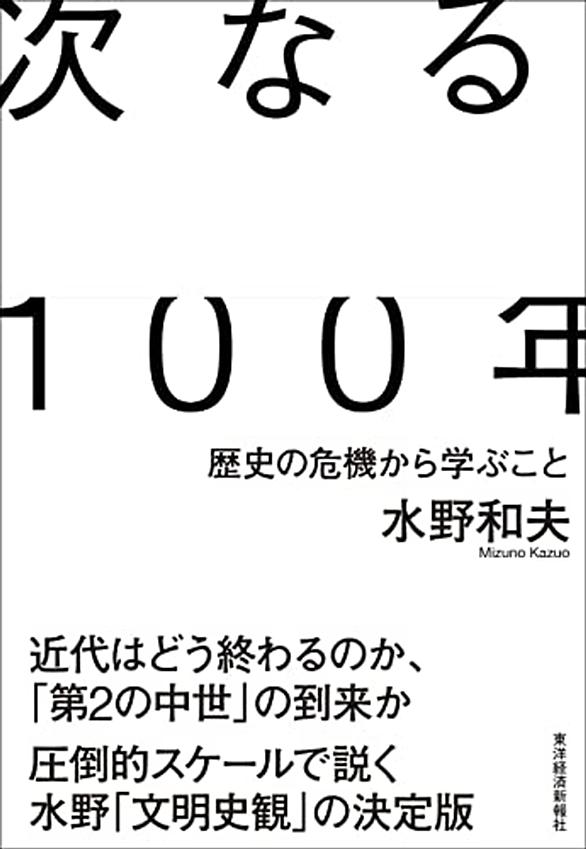帝国
(一般)
【ていこく】
一般的な帝国の意味
国語辞典では「皇帝の統治する国」とか書かれているが、帝国が指し示す意味は必ずしもそうとは限らない。一般的には特定民族が中心になって、他の複数民族を統治する国家を指す。皇帝による専制政治が行われる事が多いがこれに限定されない。
よってアッシリアやバビロニア、アケメネス朝ペルシア、古代エジプトの諸王朝やインカ、アステカ、イスラム諸王朝、チンギス・ハーンのモンゴルなども「帝国」である。場合によって「ペルシア以前の国家を帝国とは呼ばず、ローマ以前の元首を皇帝と呼ばない」などのルールが主張される場合もあるが、それほど厳密なものではない。
ヨーロッパの帝国について
狭義にはローマ帝国→東西ローマ帝国とその後継国家が「帝国」だった。(もちろん理念上のものであって実態とは異なる)
西欧ではローマ帝国の分裂(西ローマ帝国)→カール大帝の加冠(フランク王国)→オットー大帝の戴冠(神聖ローマ帝国)→オーストリア帝国、ぐらいになる*1。ローマ教皇が皇帝を認定できるという微妙な「フィクション」がこの流れの軸になっている。いわゆる「中世普遍帝国理念」などに立ち入るときりがないので省略する。
東欧ではローマ帝国の分裂(東ローマ帝国、ビザンツ帝国)→ロシア帝国、となる*2。ビザンツの皇帝理念(皇帝=教皇など)についても省略する。
ヨーロッパ的な帝国模式図*3
- 帝国(皇帝)
- 王国(王)
- 諸邦(世俗諸侯、聖職諸侯)
- 封土(騎士、郷士)
- 諸邦(世俗諸侯、聖職諸侯)
- 諸邦(宮廷伯、帝国騎士などの帝国直臣)
- 騎士団領(騎士団)
- 帝国都市
- 修道院
- 王国(王)
東アジア(中華圏)における帝国概念
→中華帝国
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る478ブックマーク【緊急報告】NHKスペシャル『ジャニー喜多川 “アイドル帝国”の実像』放送後に入ったテレビ局からの「横槍」電話 - 35produce - 田淵俊彦以前の以下のブログの最後に「ファシズム的な横槍の電話が入った」と記したところ、「どんな横槍か気になる」という多くのコメントをいただいた。https://35produce.com/%e3%80%90%e7%95%aa%e7%b5%84%e8%80%83%e5%af%9f%e3%83%bb%e7%b6%9a%e7%b7%a8%e3%80%91nhk%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%80%8e%... 35produce.com
35produce.com