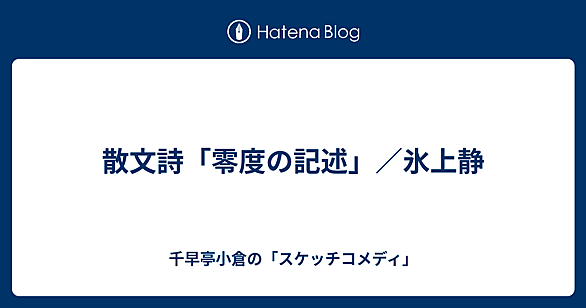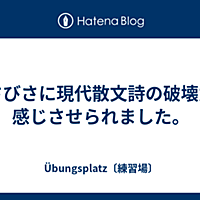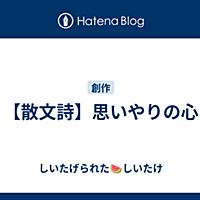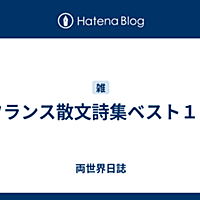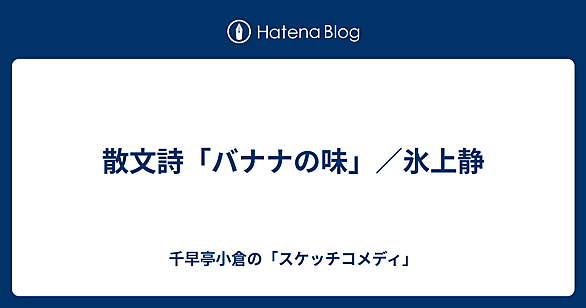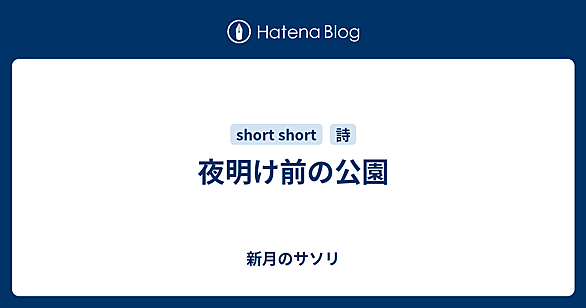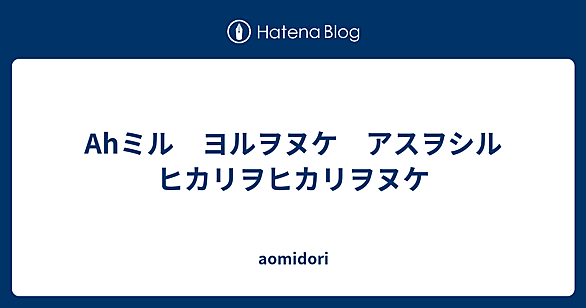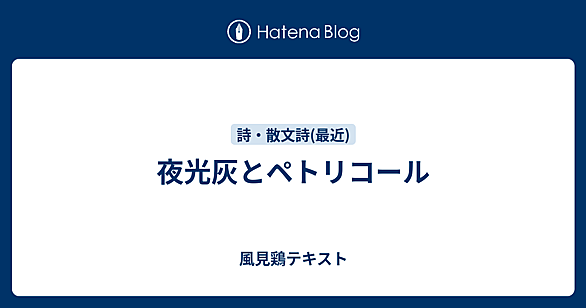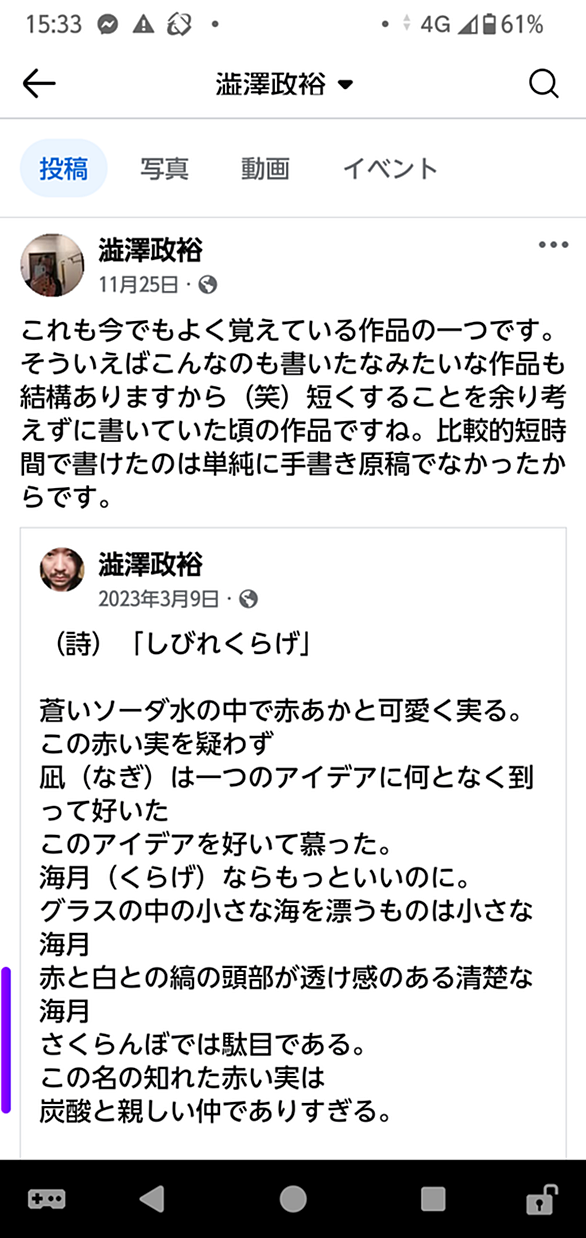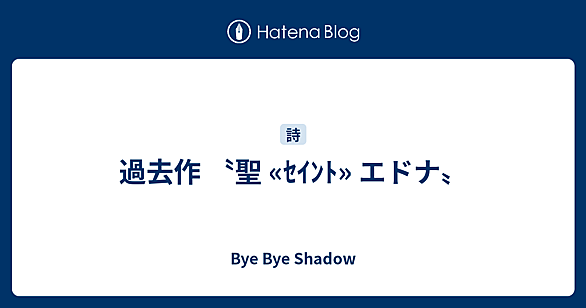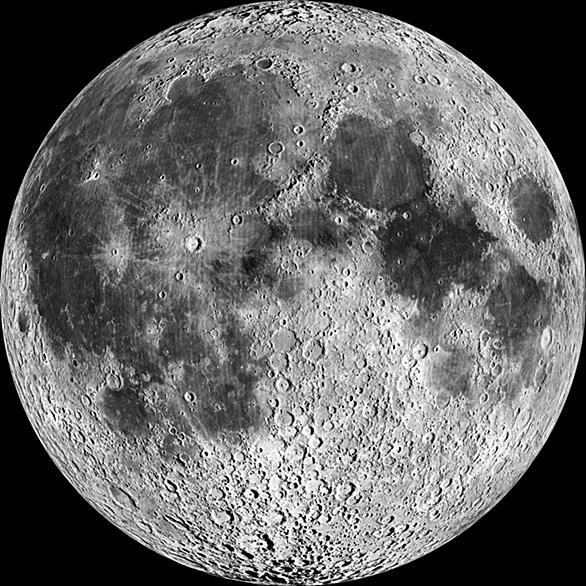散文詩
(一般)
【さんぶんし】
詩の一形式。短いフレーズで、韻を踏む形式は「韻文詩」(verse)と呼ばれるが、一見通常の文章のように見えるのが「散文詩」(prose)である。
ここで注意したいのは、韻を踏んでいても詩とは呼べない文章もあるし、散文で書かれたテクストが詩そのもの、という場合もあることである。「詩」に心があるのなら、それを持ったテクストは詩と呼べるだろう。
有名な散文詩の作品では、フランスのボードレールの「パリの憂鬱」がある。けだし、梶井基次郎の一連の小説は散文詩と呼んで差し支えない。