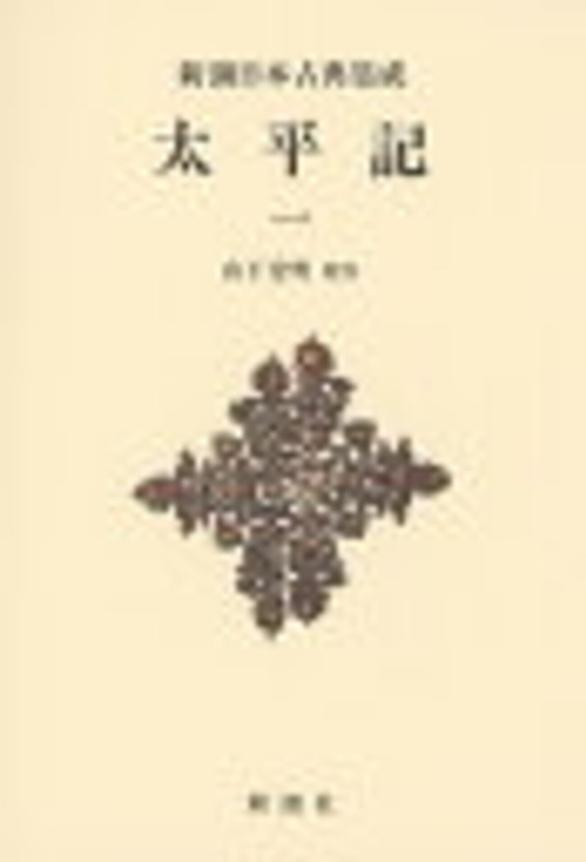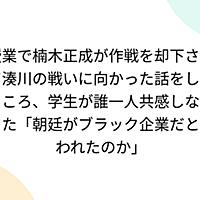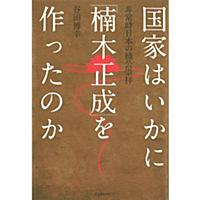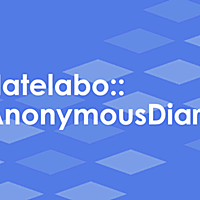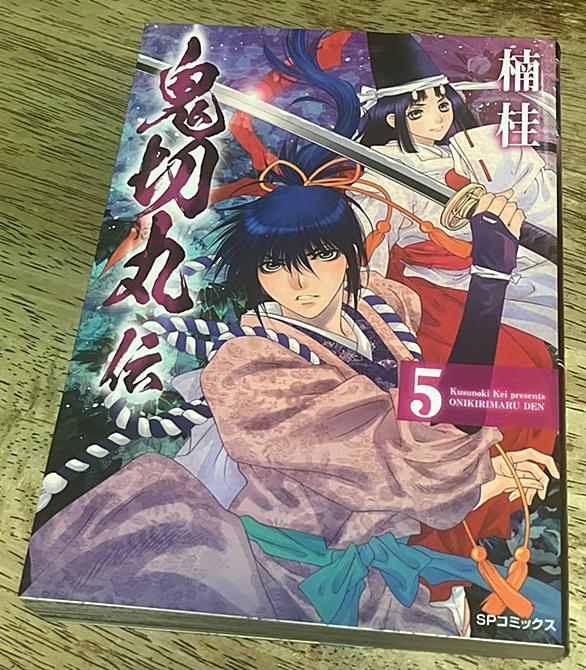楠木正成
(一般)
【くすのきまさしげ】
南北朝時代の武将。河内の悪党とされる。
1331年(元弘1)後醍醐天皇に応じて幕府へ挙兵。
篭城戦で大軍の幕府軍を翻弄。幕府の権威を失墜させるのに成功し足利高氏(後の尊氏)や新田義貞らの謀叛への遠因となる。
戦後建武政権下で河内国司と守護を兼任。和泉守護にもなった。
のち、後醍醐天皇の南朝に反抗し九州から東上する足利尊氏と戦う。
多勢に無勢であったが、天皇の命により出陣。奮戦むなしく湊川の戦いで戦死。
江戸時代より講談の主人公となる。
大楠公(だいなんこう)
1294〜1336。