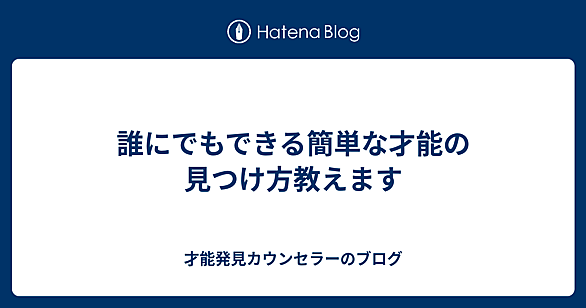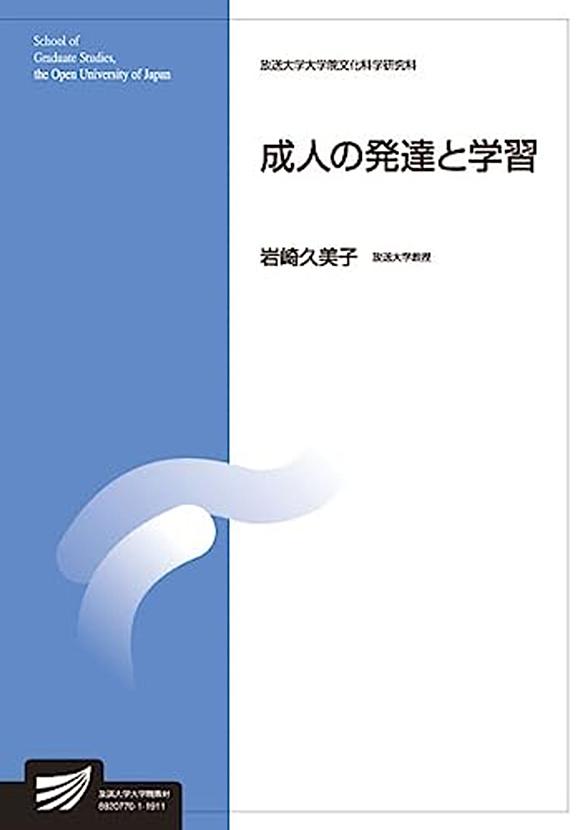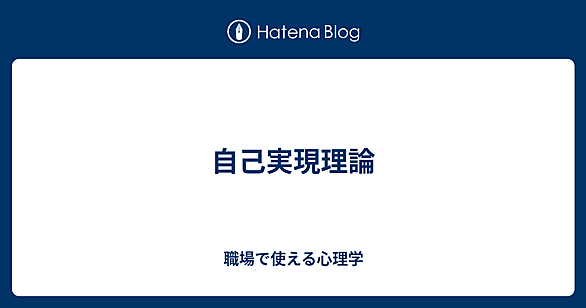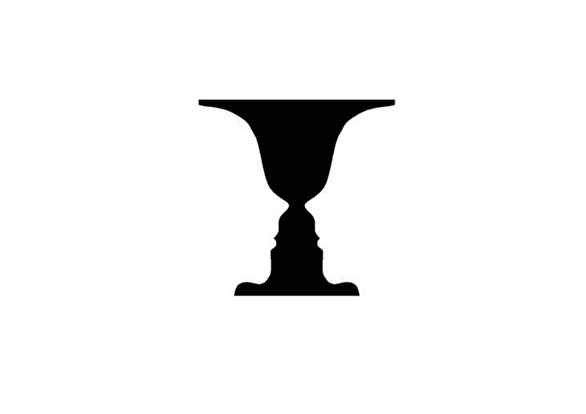自己実現理論
(サイエンス)
【じこじつげんりろん】
アメリカ合衆国の心理学者アブラハム・マズローが、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生きものである」と仮定し、人間の欲求を5段階の階層で理論化したものである。また、これは、「マズローの欲求階層説(欲求段階説)」とも称される。人間性心理学の理論としてマーケティングの分野において広まっているが、普遍的な科学根拠や実証性を欠いている人生哲学に過ぎないという批判も呈されている。
マズローの欲求階層(Maslow's hierarchy of needs)
- 生理的欲求(Physiological needs)
- 安全の欲求(Safety needs)
- 所属と愛の欲求(Social needs / Love and belonging)
- 承認(尊重)の欲求(Esteem)
- 自己実現の欲求(Self-actualization)