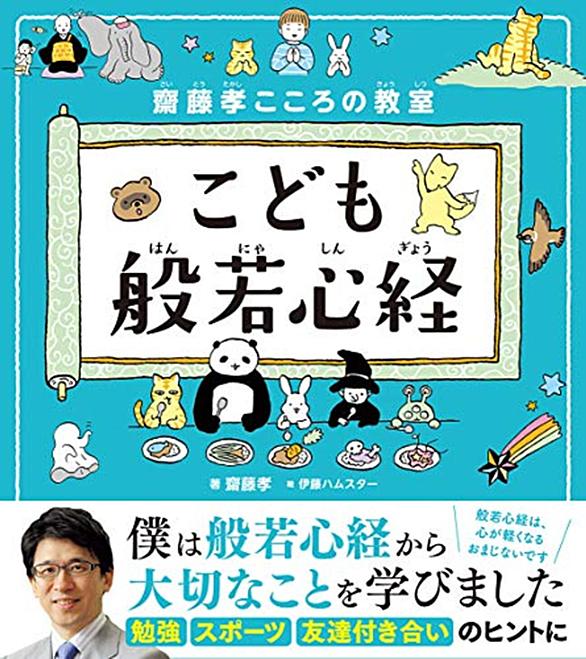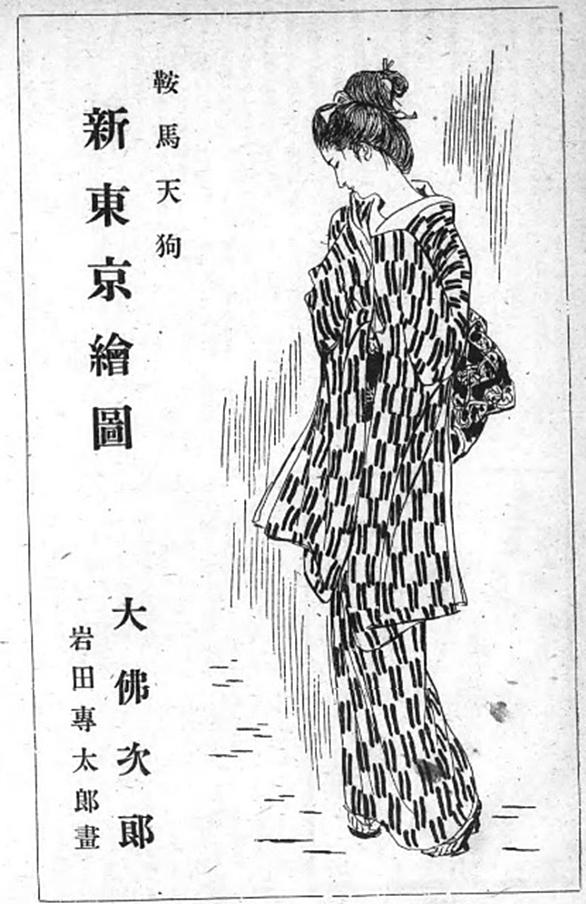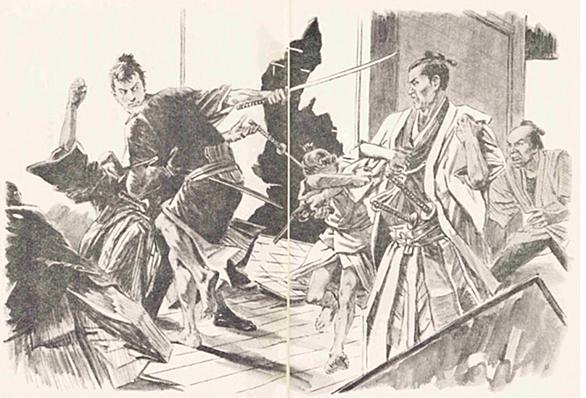鞍馬天狗
(テレビ)
【くらまてんぐ】
リスト::時代劇
テレビ番組 連続時代劇
NHK総合 木曜20:00〜20:45(木曜時代劇枠)
2008年1月17日スタート(全8回)
木曜時代劇の変遷
「風の果て」→「鞍馬天狗」→「オトコマエ!」*1
キャスト
- 鞍馬天狗………野村萬斎
- 白菊……………京野ことみ
- 幾松……………羽田美智子
- 桂小五郎………石原良純
- 黒姫の吉兵衛…徳井優
- 土方歳三………杉本哲太
- 近藤勇…………緒形直人
幕末の京都を舞台に孤高のヒーロー鞍馬天狗の活躍を描く。
![鞍馬天狗 [DVD] 鞍馬天狗 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51NSUDgriPL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: NHKエンタープライズ
- 発売日: 2008/05/23
- メディア: DVD
- 購入: 3人 クリック: 46回
- この商品を含むブログ (1件) を見る
*1:「オトコマエ!」以降、時代劇枠は土曜夜7時半に移動
鞍馬天狗
(映画)
【くらまてんぐ】
大佛次郎が生んだ時代小説のヒーロー。映画では嵐寛寿郎のあたり役。
原作小説は1924年「鬼面の老女」を皮切りに1965年までで長短あわせて47本書かれた。
主な映画
- 鞍馬天狗異聞 角兵衛獅子 (1927年) マキノ(初の映画化、サイレント)
- 出演:嵐長三郎(嵐寛寿郎)
- 鞍馬天狗 角兵衛獅子 (1951年) 松竹(3度目の映画化)
- 原作:大佛次郎 脚色:八尋不二 監督:大曾根辰夫
- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、月形龍之助、川田晴久、山田五十鈴
- 鞍馬天狗 決定版 鞍馬の火祭 (1951年) 松竹
- 原作:大佛次郎 脚色:豊田 栄 監督:大曾根辰夫
- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、入江たか子、岸 惠子、高田浩吉
- 鞍馬天狗 天狗廻状 (1952年) 松竹
- 原作:大佛次郎 脚色:八尋不二 監督:大曾根辰夫
- 出演:嵐寛寿郎、美空ひばり、藤田泰子、北上弥太郎、川田晴久、高田浩吉