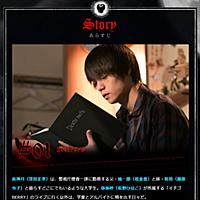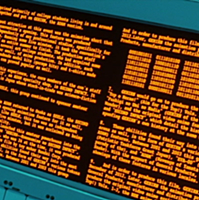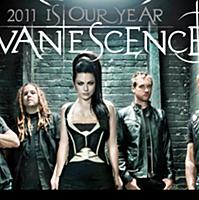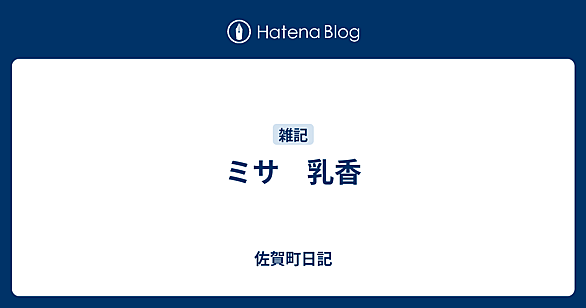ミサ
教会生活の中心をなす典礼であるエウカリスティアの祭儀(感謝の祭儀)。
エウカリスティアとはイエスの最後の晩餐に由来する、キリスト教の中心的祭儀の名称。原語のギリシア語で「感謝」の意。
この祭儀は、教会において、イエスの死と復活の記念祭として当初から現代に到るまで行われている。
聖書には、「主の晩餐」(一コリント11・20)、「パンを裂くこと」(使徒言行録2:42-46;20:7、11)という表現がみられるが、エウカリスティアという名称は2世紀初め頃から用いられている。
ミサとはその西方教会の発展形態と名称。一般にはローマ・カトリック教会の典礼形態をいう。
キリストが弟子たちとの最後の晩餐(一コリント11:23−25、ルカ福音書22:14−20、マルコ福音書14:22−25、マタイ福音書26:26−29)で、パンとぶどう酒による食事の形式をもって、すべての人の罪の贖いとなる自らの死と新しい契約のためにささげる命の記念として行うようこの祭儀を制定した。
東方教会では「聖体礼儀」、プロテスタントでは「聖餐」、日本のカトリック教会では「感謝の祭儀」などの名称が用いられている。
西方教会のラテン語において、ミサがエウカリスティアの祭儀の固有の名称になったのは5世紀末のことで、それ以前はactio(行い)、 oblatio(奉献)、sacramentum(秘儀)などと呼ばれていた。元来は一般の集会で散会、閉会を告げる「イテ・ミサ・エスト」(Ite missa est)などの句から入ったとされる。5世紀初めには一つの祭儀の結びを指す言葉として、やがてその祭式全体を指すために用いられるようになり、ローマ典礼の展開を通じてヨーロッパ諸語に受け継がれている。
- ミサ曲について
ローマ・カトリック教会のミサで歌われる聖歌(ラテン語だけに限らない)のうち、通常式文を組曲風にまとめて作曲した音楽作品のこと。
典型的なミサ曲は、最後のイテ・ミサ・エストを除く以下の五つの部分を指すが、それを含む場合もあり、さらには固有式文をも含めて作曲した例(死者のためのミサ曲:レクイエム)もある。
キリエ(あわれみの賛歌)
グロリア(栄光の賛歌)
クレド(信仰告白)
サンクトゥス(感謝の賛歌)
アニュス・デイ(平和の賛歌)
- 聖飢魔IIにおけるライヴのこと。