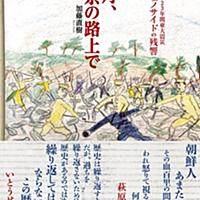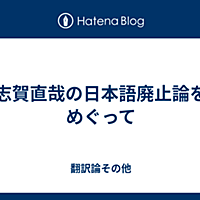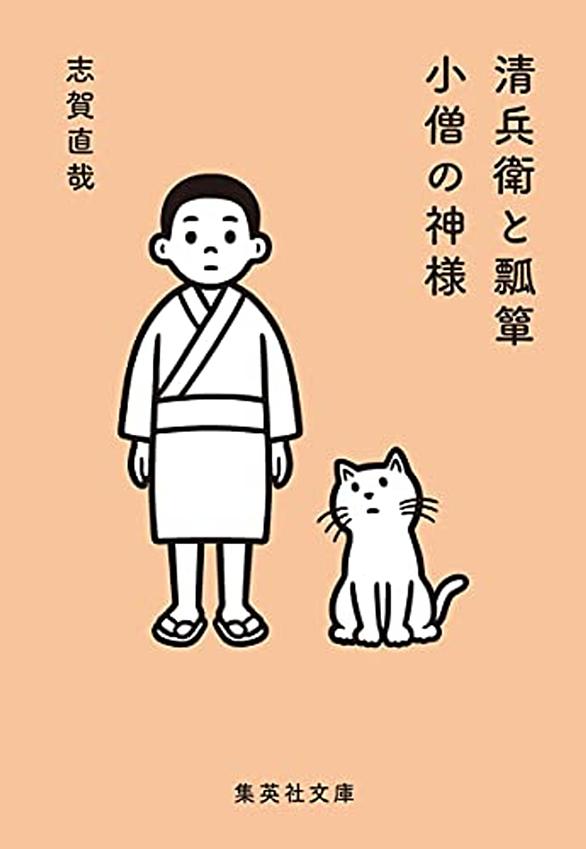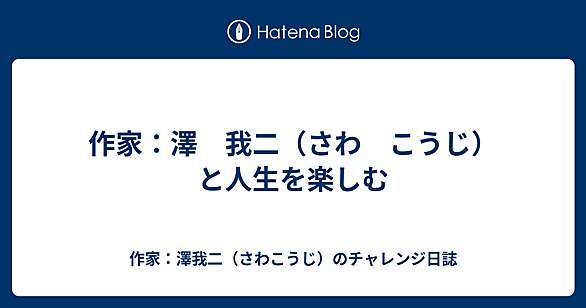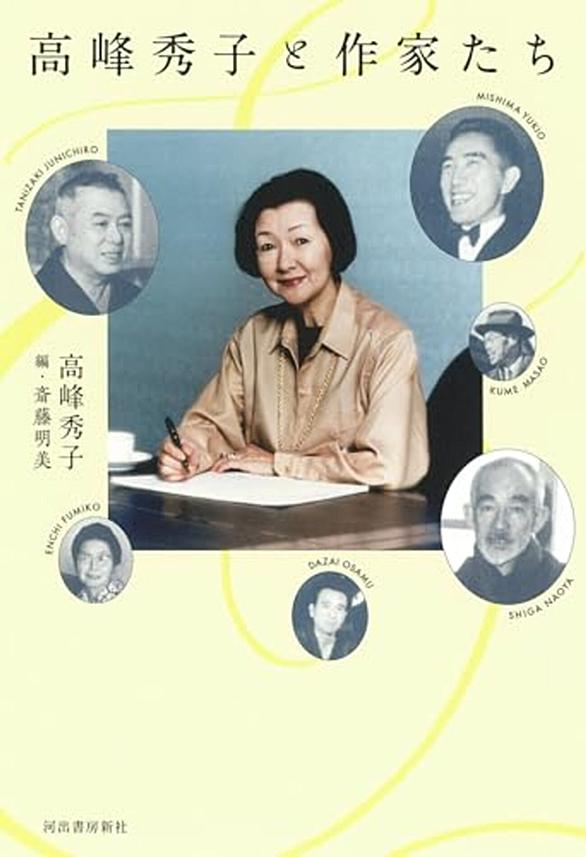志賀直哉
(読書)
【しがなおや】
阿川弘之の「志賀直哉」とその周辺の人物についての記録文学。
野間文芸賞、毎日出版文化賞を受賞。

- 作者: 阿川弘之
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1997/07/30
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 6回
- この商品を含むブログ (7件) を見る

- 作者: 阿川弘之
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1997/07/30
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログ (4件) を見る
志賀直哉
(読書)
【しがなおや】
1883年2月20日宮城県石巻町生まれ。作家。1971年没。父直温、母銀の次男として生まれる。
- 主著
- 『暗夜行路』、『小僧の神様』、『城の崎にて』、『和解』
1910年、武者小路実篤、有島武郎らと「白樺」を創刊。以降「白樺派」として戦前の小説界を牽引する。異名「小説の神様」。自らを題材に採った告白小説・私小説を中心として執筆。太宰治『如是我聞』などでの批判をのらりくらりとかわす。