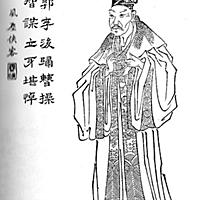賈詡
(社会)
【かく】
中国後漢から三国時代の人物(147年 - 223年)。武威郡姑臧県の人。字(あざな)は文和。
若い頃は一部の者にしか名前が知られていなかったが、智謀に優れた人物で、機転を利かせて難を逃れたこともあったという。
董卓に校尉に取り立てられ、董卓の暗殺後は李傕に進言して王允・呂布から長安を奪取した。
李傕が政権を握ると、尚書となって献帝に仕えた。献帝が洛陽に帰還するため長安を離れると、李傕を見限って長安を離れ、段煨という人物に身を寄せたが、段煨にはその智謀を警戒されたため、張繍を頼って南陽に向かった。張繍には重く用いられ、劉表との同盟を締結するなど手腕を発揮した。
197年、曹操の攻撃を受けると、張繍は曹操に一時は降伏したが、曹操が張繍を軽んじた態度をとったため、張繍と共に密かに曹操を襲撃する計略を立てた。このときには曹操は逃したものの、曹操の子の曹昂と側近の猛将典韋を討ち取る戦果を挙げた。その後も張繍を輔佐して何度か曹操と戦い、適切な進言を行った。
200年、曹操と袁紹が黄河を挟んで決戦することになると、双方の陣営から張繍に味方となるよう誘いがあった。賈詡は張繍に曹操に味方することを勧め、張繍と共に曹操の傘下となった。賈詡は曹操の参謀の1人となり重用され、袁紹との官渡の戦いや、その後の華北での袁氏の残党との戦い、さらに孫権との赤壁の戦いや馬超らとの潼関の戦いにおいて、適切な助言を行った。
曹操の後継者争いでは、曹丕を支持した。曹操の死後、魏(曹魏)の皇帝となった曹丕からは三公の太尉に任命されるなど国家の元勲としての待遇を受けた。223年に77歳で没した。