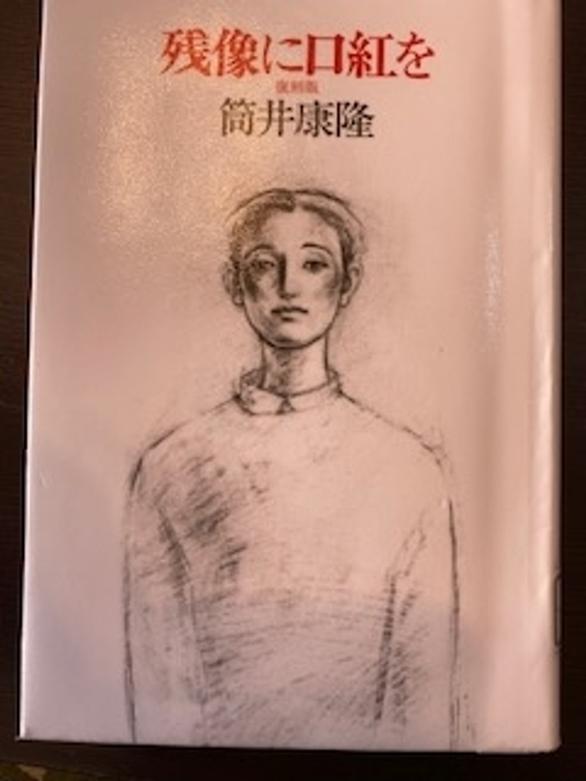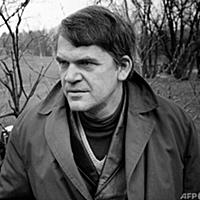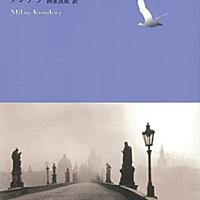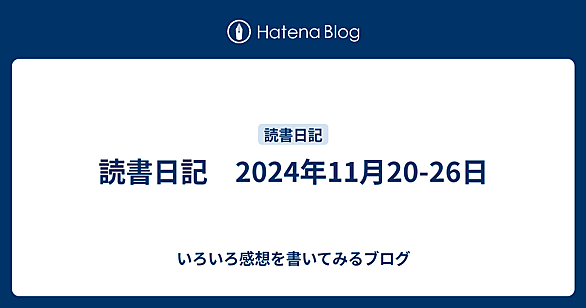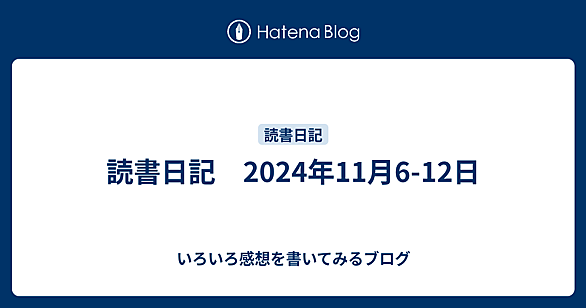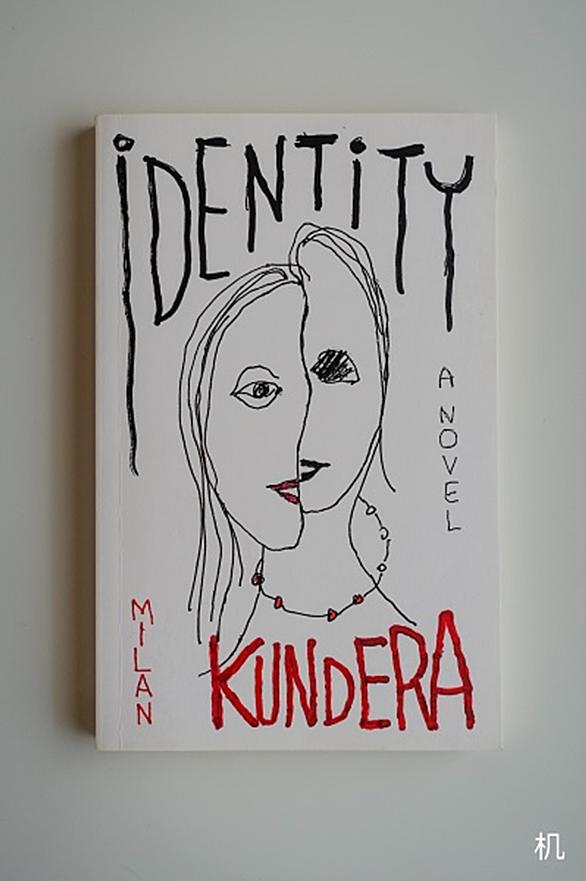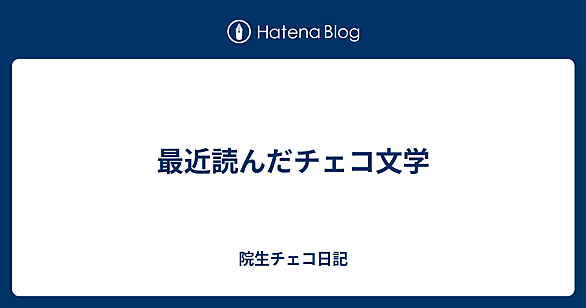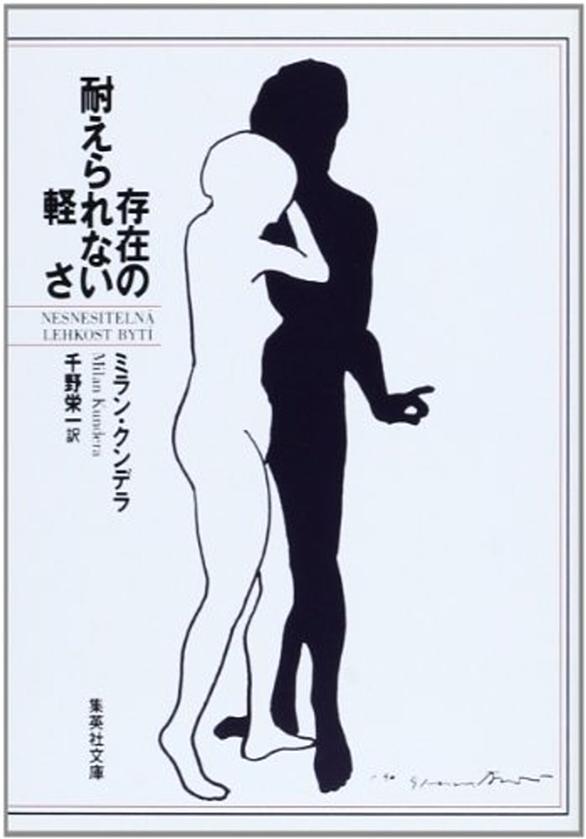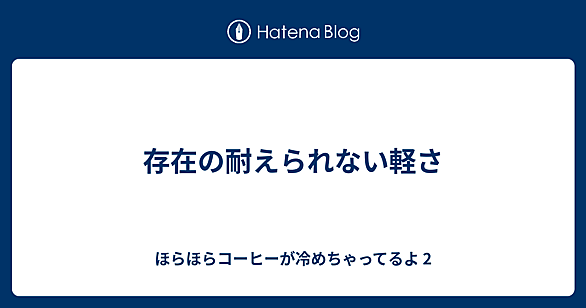ミラン・クンデラ
(読書)
【みらんくんでら】
ミラン・クンデラ(Milan Kundera)
プロフィール
1929年- チェコスロバキア ブルノ生まれ (男)
1952年、プラハの音楽芸術大学映画学部を卒業。
その後同大学で文学を教える。
その頃から詩、評論、短篇小説を発表し、1967年発表の『冗談』で一躍世界の注目を浴びる。
しかし、1968年の「プラハの春」以降教職を失い、すべての著作はチェコ国内で発禁となる。
1975年、フランスに移住。
1981年、フランスの市民権獲得。
作品録
- 「無知」2000年
- 集英社 西永良成訳 四六判 220p \1,900 2001年03月発行 ISBN:4087733408
- 「ほんとうの私」1998年
- 集英社 西永良成訳 四六判 207p \1,900 1997年10月発行 ISBN:4087732614
- 「緩やかさ」1995年
- 集英社 西永良成訳 四六判 201p \1,845 1995年10月発行 ISBN:4087732347
- 「不滅」1990年
- 集英社 菅野昭正訳 文庫判 591p \952 1999年10月発行 ISBN:4087603695
- 集英社 菅野昭正訳 四六判 533p \2,600 1992年02月発行 ISBN:408773143X
- 「小説の精神」1986年
- 法政大学出版局 金井裕、浅野敏夫訳 四六判 202p \2,300 1990年04月発行 ISBN:4588002945
- 「存在の耐えられない軽さ」1984年
- 集英社 千野栄一訳 文庫判 399p \819 1998年11月発行 ISBN:4087603512
- 集英社 千野栄一訳 四六判 365p \2,243 1993年09月発行 ISBN:4087731774
- 「ジャックとその主人」1981年
- みすず書房 近藤真理訳 四六判 143p \1,900 1996年05月発行 ISBN:4622045982
- 「笑いと忘却の書」1978年
- 集英社 菅野昭正訳 四六判 \1,900 ISBN:4087731464
- 「別れのワルツ」1976年
- 集英社 西永良成訳 四六判 316p \1,942 1993年06月発行 ISBN:4087731723
- 「生は彼方に」1973年
- 早川書房 西永良成訳 文庫判 554p \980 2001年07月発行 ISBN:4151200088
- 早川書房 西永良成訳 四六判 333p \2,621 1995年07月改訂 ISBN:4152079320
- 「可笑しい愛」1968年
- 集英社 西永良成訳 文庫判 361p \905 2003年09月発行 ISBN:4087604446
- 集英社 千野栄一他訳 四六判 299p 1992年06月発行 \1,900 ISBN:4087731510
- 「冗談」1967年
- みすず書房 関根日出男、中村猛訳 四六判 380p \2,900 2002年05月発行 ISBN:4622048671(版元品切)
- 「鍵の所有者」1963年(戯曲)
- 「小説の技法」1960年(評論)
- 「モノローグ」1957年(詩集)
- 「最後の五月」1955年(詩集)
- 「人間、この広き庭」1953年(詩集)