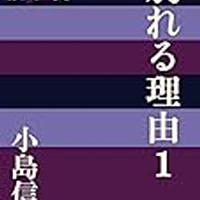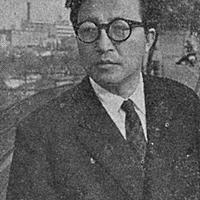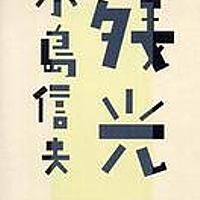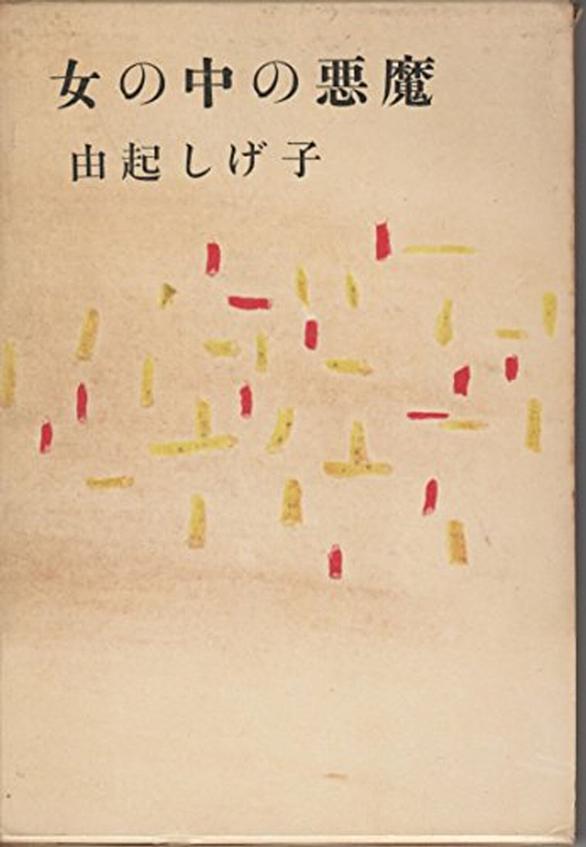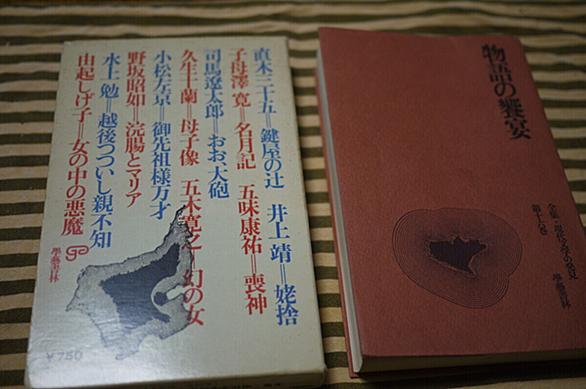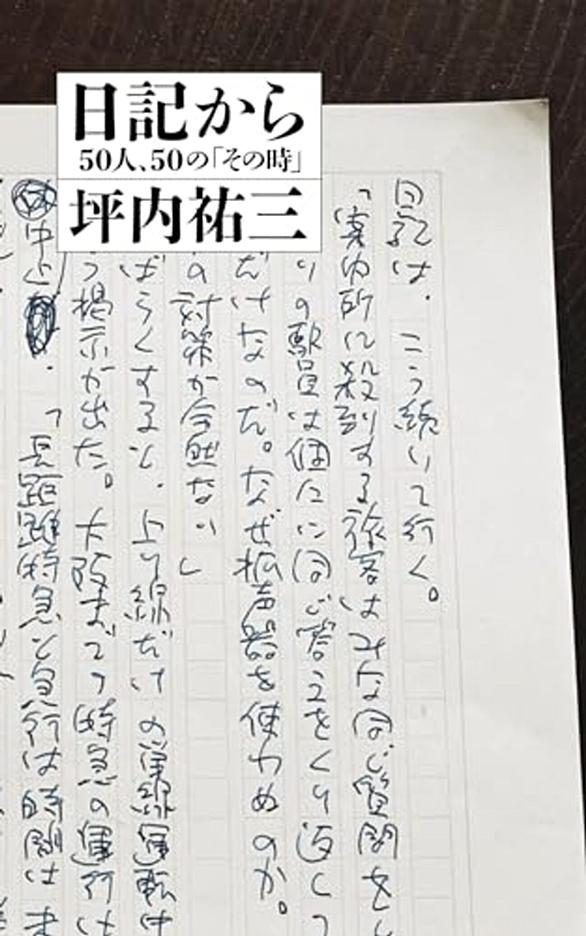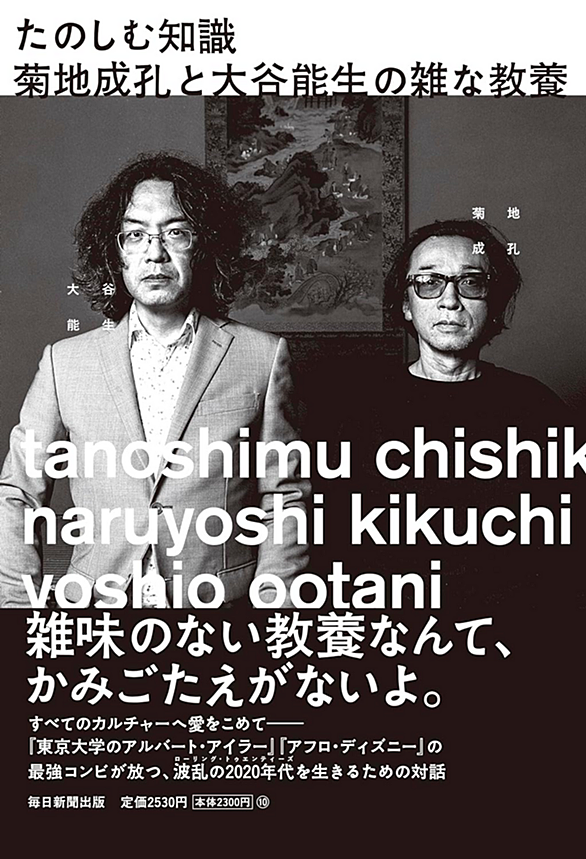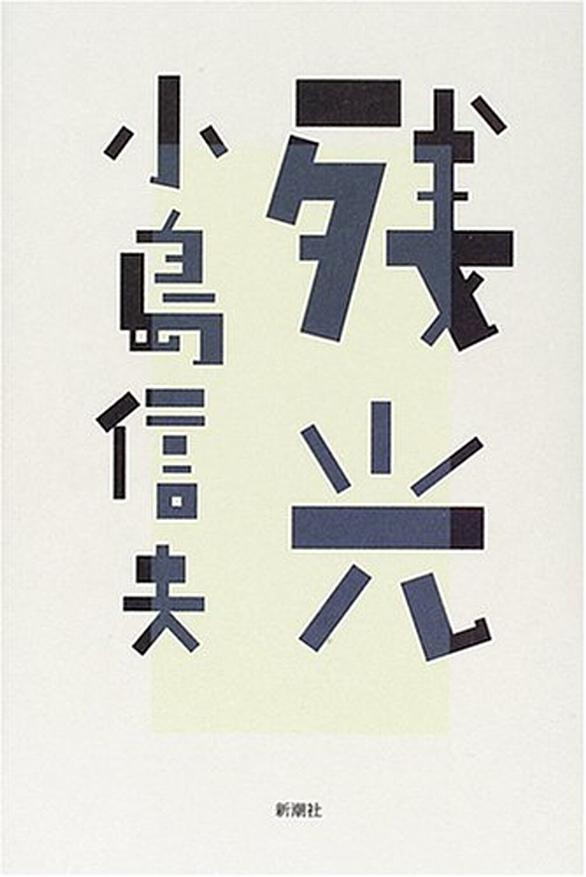小島信夫
(読書)
【こじまのぶお】
作家。1915年(大正4年)2月28日、岐阜県生まれ。
吉行淳之介・遠藤周作・安岡章太郎などと共に第三の新人と称される。
1955年「アメリカン・スクール」で芥川賞。
1966年『抱擁家族』で谷崎潤一郎賞。
1972年『私の作家評伝』で芸術選奨文部大臣賞。
1981年『私の作家遍歴』で日本文学大賞
1982年日本芸術院賞。
1983年『別れる理由』で野間文芸賞。
1998年『うるわしき日々』で読売文学賞。
2006年10月26日歿。
主な著作
長編
- 『島』
- 『裁判』
- 『夜と昼の鎖』
- 『墓碑銘』
- 『女流』
- 『抱擁家族』
- 『美濃』
- 『別れる理由』
- 『菅野満子の手紙』
- 『寓話』
- 『静温な日々』
- 『暮坂』
- 『うるわしき日々』
- 『各務原・名古屋・国立』
- 『残光』
作品集
- 『小銃』
- 『アメリカン・スクール』
- 『微笑』
- 『残酷日記』
- 『チャペルのある学校』
- 『愛の完結』
- 『愉しき夫婦』
- 『弱い結婚』
- 『階段のあがりはな』
- 『異郷の道化師』
- 『ハッピネス』
- 『釣堀池』
- 『女たち』
- 『月光』
- 『平安』
- 『こよなく愛した』
- 『殉教・微笑』
- 『月光・暮坂 小島信夫後期作品集』