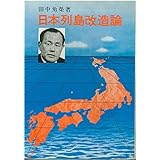これは拙著『〈郊外〉の誕生と死』でも記しておいたことだが、一九五〇年代から六〇年代にかけて、私はずっと農村に住んでいた。当時の村は商品経済、つまり消費生活とは無縁に近く、それらはかなり離れた町で営まれているものに他ならず、何かを買うためには駅のある町まで出かけなければならなかった。ようやく六〇年代になって、村のはずれに小さな雑貨屋ができたけれど、そうした事情はほとんど変わっていなかった。

そうした商品経済だけでなく、水は井戸、火はかまどによっていて、道路は舗装されておらず、電信柱も木であった。そのような生活環境が少しずつ変わっていくのは六〇年代に入ってからであり、それはテレビの出現に象徴されていた。だが全体的な変化を肌で感じるようになったのは六七、八年頃だったと思われる。それは田や畑だったところに、新しい住人のためのマイホームやアパートが建てられ、またそれらの住居に続いて、周辺にいくつもの新興住宅地が開発され、またこれもいくつかの大きな工場が出現していった。その事実はこれまで農地、すなわち田や畑でしかなかった土地が、住宅地や工場用地として、農地よりも高く売れる時代が到来したことを意味していた。私に限っていえば、この事柄を抜きにして大学進学を語れないだろう。そうして七〇年代に至り、郊外の誕生と混住社会の出現を見ることになったのである。
かつてはこれが高度成長期の帰結だと見ることもできたけれど、このような戦後の農村の変容も、一九五〇年の国土総合開発法を起点とし、六二年から始まる全国総合開発計画(一全総)、六九年の新全国総合開発計画(二全総)が密接にリンクしていたとわかる。それに後者の二全総には、七二年に首相の座についた田中角栄の日本列島改造論も併走していた。
その七二年に田中は『日本列島改造論』(日刊工業新聞社)を上梓し、それは同年のベストセラーとなり、八五万部に達している。田中はその「序にかえて」で、昭和三十年代に始まる日本経済の高度成長によって、東京や大阪などの太平洋ベルト地帯に産業や人口が過剰に集中し、日本は世界に例を見ない高密度社会となり、逆に農村は若者が減り、高齢化してしまったと述べ、次のように記している。
明治百年をひとつのフシ目にして、都市集中のメリットは、いま明らかにデメリットへ変わった。国民がいまなにより求めているのは、過密と過疎の弊害の同時解消であり、美しく、住みよい国土で将来に不安なく、豊かに暮していけることである。そのためには都市集中の奔流を大胆に転換しえ、民族の活力と日本経済のたくましい余力を日本列島の全域に向けて展開することである。工業の全国的な再配置と知識集約化、全国新幹線と高速自動車道の建設、情報通信網のネットワークの形成などをテコにして、都市と農村、表日本と裏日本の格差は必ずなくすことができる。(中略)
その意味で、日本列島の改造こそはこんごの内政のいちばん重要な課題である。私は産業と文化と自然とが融和した地域社会を全国土におし広め、すべての地域の人びとが自分たちの郷里に誇りをもって生活できる日本社会の実現に全力を傾けたい。
そして田中はこの『日本列島改造論』が六八年にまとめた「都市政策大綱」に基づく「国土総合改造大綱」であることを明言し、その五つの重点項目を挙げているので、その目的を方法、具体的な政策、プロジェクトを要約して示す。
1 新しい国土計画の樹立とその達成のための法体系の刷新、開発行政体制の改革 / 全国各地を結ぶ鉄道新幹線の建設と国土開発総合研究所の設置。 2 大都市の住民の住宅難、交通戦争、公害からの解放 / 職住近接の原則に基づく立体化高層化による都市の再開発と近郊市街化、ニューシティの建設。地下鉄の強化。 3 広域ブロック拠点都市の育成、大工業の基地の建設を中心とする地方開発の推進 / これらの拠点と背後地の都市、農村を結びつけるためと道路などの産業や生活基盤の先行的建設、及び二次、三次産業の地方配置と高収益の農業を拡大することによる魅力的で近代的農村の育成。 4 公益優先の基本理念のもとでの土地利用計画と手法の確立 / 都市における工業適地、優良農地の確保、市街化地域、用途別地区の指定、土地区画整理方式の活用、土地委員会設置による有効な土地利用の推進。 5 国土改造のための国民全体の資金と蓄積の活用 / 利子補給制度の採用による民間資金の導入、及び国土改造拠点金融機関を創設し、長期低利資金の大幅な供給。
先の「序にかえて」の引用部分とこれらの五つの重点項目が『日本列島改造論』の眼目であり、以下はその補論と注釈と見なせるだろう。また田中は同書において、「私がこれまで手がけた国土開発の政策づくりの軌跡をたどると、戦後間もない昭和二十五年、国土政策の礎石として国土総合開発法をつくったことが思い出される」と記している。そして続けて八十項目に及ぶ「戦後国土開発計画の歩み」の一覧を示し、「私の半生における四分の一世紀は、まさしく戦後の国土開発の足どりとおもに歩んだ」とも述べている。
しかしいくら田中角栄であっても、一九四七年に初当選したばかりだし、またGHQ占領下にあったわけだから、国土総合開発法の成立はニューディール政策の影響下にあったと見なすべきで、田中がそれなりに関係していたにしても、「国土政策の礎石としての国土総合開発法をつくった」とは思われない。だがよくあるはったりと大風呂敷の政治家の言説として処理すべきではないし、ひょっとすると、このようなアメリカを無視する言説がロッキード事件へとつながっていったのかもしれない。
それはともかく、この日本列島改造論は全国開発計画の提出に他ならず、当然のように土地投機が生じ、インフレが進行した。さらに七三年にはオイルショックが起き、トイレットペーパー、洗剤、砂糖などの生活必需品をめぐるパニックが出来し、その後には「狂乱物価」に襲われた。それに続き、翌年には「田中金脈」問題によって内閣総辞職となり、日本列島改造論も終わりを告げたように思われた。同時に高度成長も終焉に向かったけれど、七〇年代前半の日本は第三時産業就業人口が五割を超えるという消費社会へと転換し、工業を中心とする地域開発も見直さざるを得ない状況へと追いやられたはずだった。
しかし六六年都市政策大綱、六九年の新全国総合開発計画(二全総)、七二年の日本列島改造論は都市や地域開発の基本チャートとして根を張り、延命し、七七年の第三次全国総合開発計画(三全総)、八七年の第四次全国総合開発計画(四全総)、九八年の21世紀の国土グランドデザイン(五全総)へと継承されていった。それは五全総下に進行した大都市の立体化高層化による再開発に象徴されていよう。これこそは日本列島改造論の目玉であったのだ。その他にもこれに類する事柄はいくつも挙げられるだろう。
本間義人は『国土計画を考える』(中公新書)の中で、二全総は田中の列島改造論とイメージが重なり、高度成長を前提とした最も開発志向が強い国土計画だったと述べ、次のように書いている。

それだけに、この国土計画がもたらしたリアクションも大きかった。一全総につづく地域の開発にともなって環境破壊が続出したが、何よりも大きいのは全国で地価が高騰しつづけ、土地神話を定着させたことである。大規模公共投資はまた、政・官財界の構造的癒着の土壌となり、金券体質を生むことことにつながった。
一方で、計画期間中の七三年には国際的な石油ショックに見舞われ、各地でトイレットペーパーや洗剤の買い占め騒ぎが起こる。そして従来の高度成長路線は破綻して、低成長を余儀なくされることになるのである。結果的には、まさに狂乱の七〇年代の国土のグランドデザインが、この二全総であった。
この二全総や列島改造論のかたわらで、先述したような農村の変化、すなわち郊外化と混住社会化が起きていたのである。それは「大きな物語」としての高度成長の終焉に伴うようなかたちで表出してきた、個人の「小さな物語」としてのマイホーム幻想をベースとするもので、出現しつつあった消費社会はそれを「大きな物語」として育て上げようとした。列島改造論とパラレルに住宅ローン専門の金融会社が設立され、ハウスメーカーも成長し始める。
そして何よりもインフレーションは続き、国土計画と列島改造論は「全国で地価が高騰しつづけ、土地神話を定着させた」のである。だがそれは一方で、農地が住宅地として売れることで農村に思いがけない現金収入をもたらし、またマイホームを購入した側も、地価が上昇することによって、これも賃金のベースアップを上回る財産の獲得を意味していた。そのために郊外はさらにスプロール化し、都市の外側へと拡散し、混住社会だけでなく、新興住宅地が形成されていった。そのことによって、都市でも地方でもない、あるいは村でも町でもない郊外が全国的に出現していったのだ。
その郊外化と連鎖するように、ロードサイドビジネスも誕生していく。これは駐車場を備えた郊外型商業店舗の総称で、七〇年代前半におけるファミリーレストランを先駈けとし、当初はストリートビジネスとして始まったコンビニエンスストアやファストフードも含め、八〇年代になってありとあらゆる業種がビジネスの郊外化を図ったために、郊外消費社会の成立をも見ることになったのであり、それは全国各地の風景を均一化する装置としても機能していたことになる。このロードサイドビジネスもほとんどが田や畑だったところに出現していったのである。
そのような郊外化の動向は、第三次全国総合開発計画(三全総)にも反映されていったと考えられる。七七年にスタートした三全総は、七八年に発足した大平内閣の田園都市国家構想とリンクしている。それは「都市に田園のゆとりを、田園に都市の活力をもたらし、両者の活発で安定した交流を促し、地域社会と世界を結ぶ、自由で、平和な開かれた社会、そうした国づくりを目指す」というもので、田中の列島改造論とは異なるイメージを帯びている。これは本連載59や72でもしばしば言及してきたハワードや、明治時代の日本の内務省の田園都市構想への回帰という側面も指摘できようが、日本近代史において、郊外がかつてないかたちでせり上がってきたことの影響を受けてのもののようにも思われる。
これは国土開発という「大きな物語」と郊外と混住社会、及びロードサイドビジネスからなる郊外消費社会化という「小さな物語」の交差を意味していよう。そしてそれらの交差が、八七年から始まる中曽根内閣の第四次全国総合開発計画(四全総)のバブル経済の時代を生み出していったことになろう。