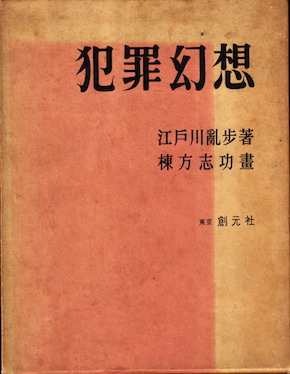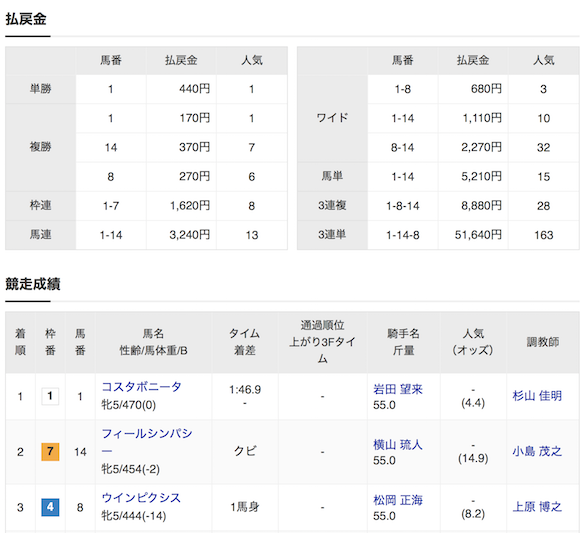60年代初頭「世界残酷物語」でモンド映画の元祖で王者となったヤコペッティ監督の作品ゆえこんな邦題になってしまったが、原作は荒俣宏絶賛の風刺ファンタジー、ヴォルテールの「カンディード」👍パンフ400円💴岩波文庫150円💴セット500円(=^ェ^=) pic.twitter.com/1oaxaSa2Py
— 浅羽通明の古書窟/BAKENEKOBOOKS ふるほんどらねこ堂(犬派のきみには狂狷舎) (@Doranekodo) 2024年5月1日
simmel20.hatenablog.com▼水林章東京外国語大学教授の『『カンディード』〈戦争〉を前にした青年』(みすず書房)は、古典的作品の読み方を各専門の学者がポイントを絞って講義する《理想の教室》シリーズの一冊である。この著者は、思想史的問題をあまりに現代に引きつけ過ぎる傾向があり、この本でもそこに引っかかるが、解読の過程は、スリリングで面白い。
ヴォルテールのこの作品には、「オプティミズム(最善説)」という副題がついている。岩波文庫版(植田祐次訳)の巻末訳注によれば、この言葉は、「たとえ細部においてこの世の合目的性が人間の理解を超えているにせよ、あらゆる出来事は人間の善のために組織されており、したがって可能な限り最善であることになる」と説く「哲学上の立場」をさし、「ドイツのライプニッツやイギリスのポープらによって説かれた」とある。「全き言葉」の支配を暗示する「パングロス」という「最善説」の哲学者の「洗脳」から、「白さ=ナイーヴさ」を暗示する「カンディード」青年が、いかにして解放されていくかを物語った、「一風変わった教養小説(ビルドゥングス・ロマン=ロマン・ダプランティサージュ)」が、この作品なのだということになる。
カンディードの育てられた伯父男爵の城は、ドイツのウエストファリアに位置していることから、三十年戦争の帰結としてのウエストファリア条約の記憶がこの作品には刻印され、さらに1759年発刊のこの作品の背景には、1756〜63年の最初の世界戦争といわれる七年戦争があると推察される。城を追放されたカンディードは、戦争の現実に遭遇するのである。ところが、パングロスから与えられた「最善説」の知識によって、戦争も戦場も美的な対象としてのイメージで捉えられた。やがてカンディードは、その視点から移行して、解剖学的な部分に分解された、「筆舌に尽くしがたい苦痛を強いられた身体」が死体として散乱する戦場の現実に直面することになる。彼の成長とはこのような意味においてである。
なお戦場の場面以外にも『カンディード』には、断片化される身体のイメージが執拗に現われるが、著者は巻末に補講の頁を設けて、女性の身体が快楽の道具として、細分化・断片化されて捉えられることと、産業的効率性をめざして、「労働する身体」が分解され細分化されることとは、並行した事象であり、どちらも「18世紀以降確立しつつあった産業の世界における商品関係的論理との関係において理解」されるべきだそうである。
ともあれ、『カンディード』とは、著者によれば、こうまとめられる。
……あるひとつの世界秩序のなか置かれている人間の意識の、当の世界秩序を正当化し存立せしめている言語的な体制に対する無自覚的な服従からの自由を描くことによって、まさに世界秩序の転換ー近代世界の誕生を告知する作品である、と。……▼