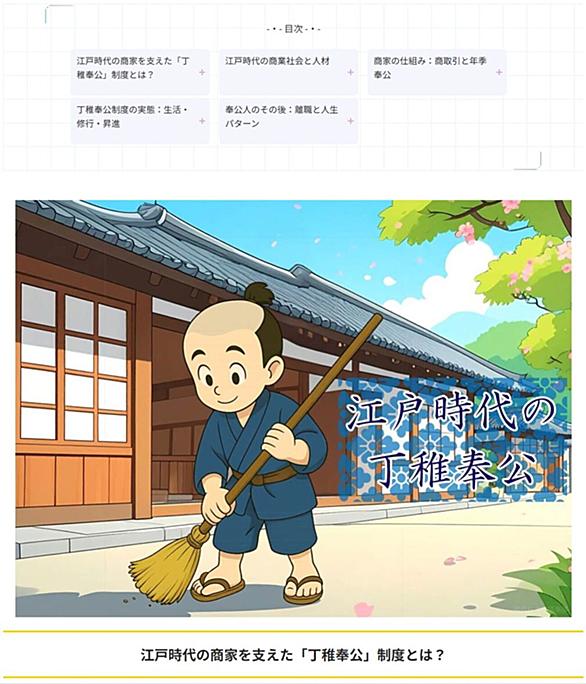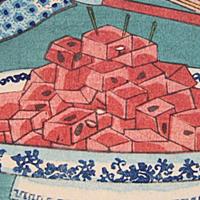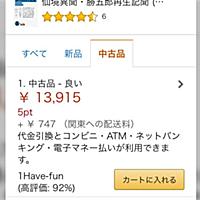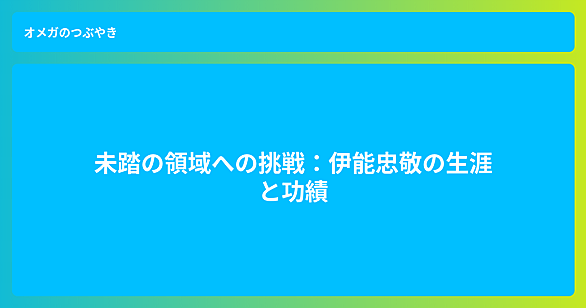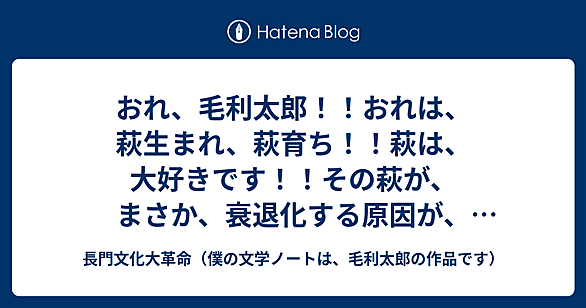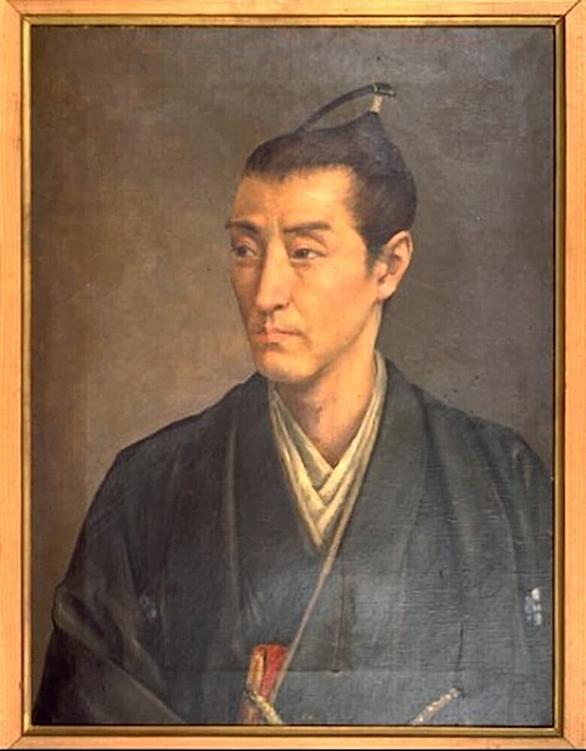江戸時代
(社会)
【えどじだい】
徳川家康による天下統一と江戸幕府開府から、明治維新までの期間。
1603年の江戸幕府開府から1867年の大政奉還迄の265年間をさす。
主な出来事
- 1603年 江戸幕府開府
- 1612年 大阪夏の陣
- 豊臣家滅亡
- 1637年 島原の乱
- 1639年 ポルトガル船来航禁止
- 鎖国体制の完成
- 1837年 大塩平八郎の乱
- 1853年 ペリー来日
- 1854年 日米和親条約締結
- 開国
- 1858年 日米修好通商条約締結
- 1867年 大政奉還
- 江戸幕府滅亡
文化
戦乱が収まり貨幣経済の発達による経済活動の活発化により、町人の発言力が強くなり町人文化が形成され、学問、宗教、文芸、芸術などで著しい文化的発展をみせる。
- 学問
- 朱子学、国学、蘭学、陽明学、心学など
- 宗教
- 伊勢参り、善光寺参り、天理教、金光教など
- 文芸
- 松尾芭蕉、小林一茶、十返舎一九、良寛、近松門左衛門、滝沢馬琴など
- 芸術(絵師)
- 葛飾北斎、狩野探幽、写楽、菱川師宣、歌川広重など
- 芸術(その他)
- 本阿弥光悦、市川団十郎、尾形光琳、野々村仁清など