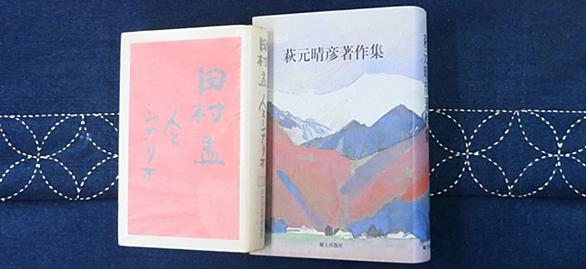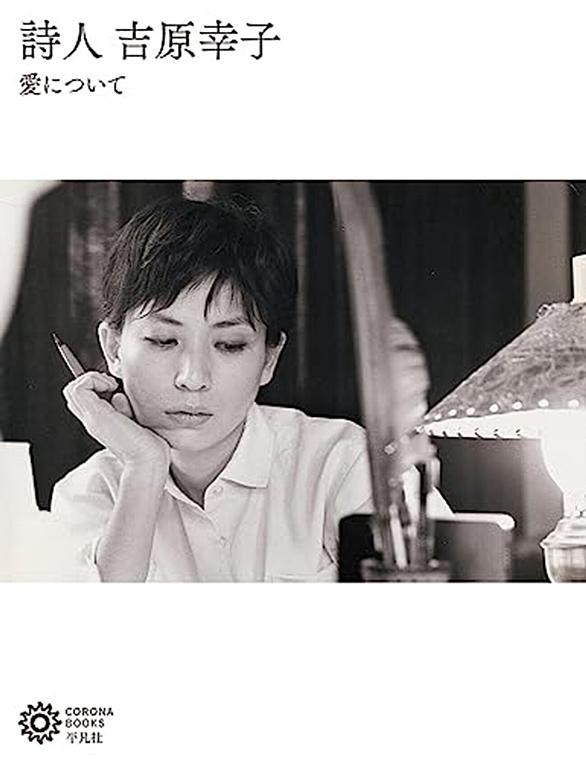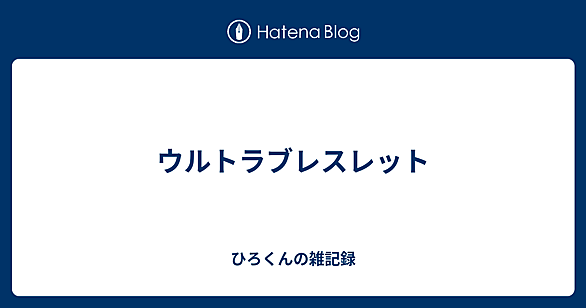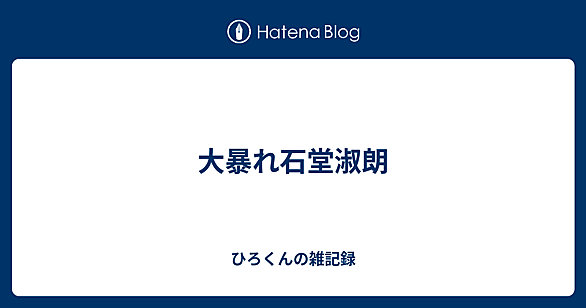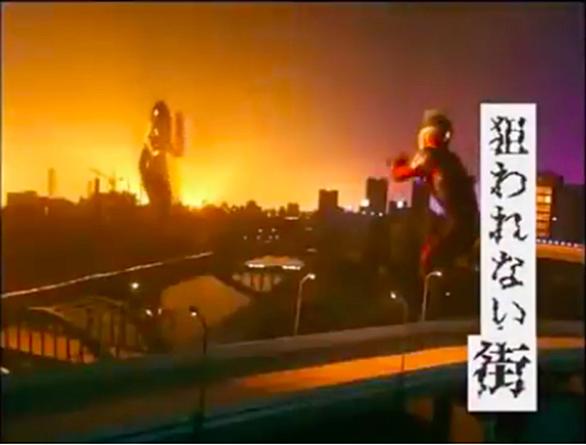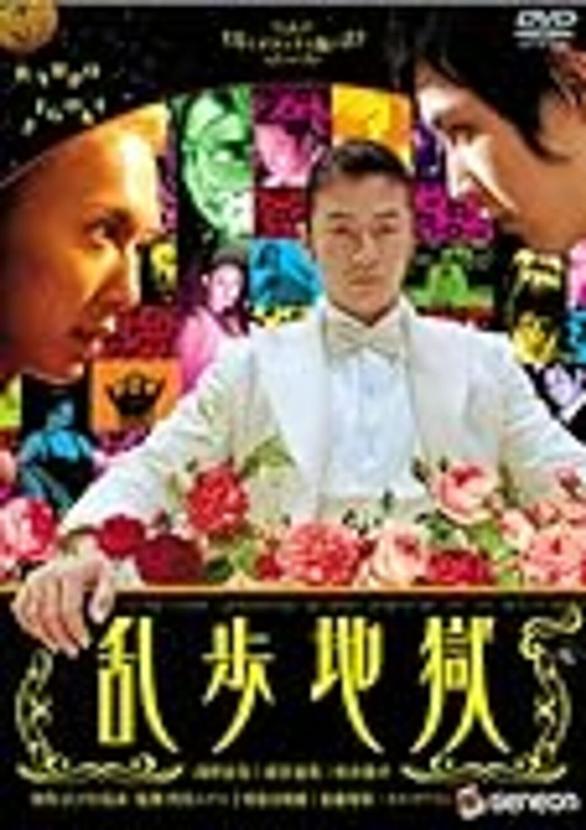石堂淑朗
(映画)
【いしどうとしろう】
脚本家、評論家。1932年7月17日、広島県生まれ。
東京大学文学部卒業後、松竹に入社。シナリオ執筆、助監督を務めた後、独立。
大島渚との共同脚本の『太陽の墓場』で第12回シナリオ賞受賞。映画『黒い雨』で日本アカデミー賞脚本賞受賞。
日本映画学校校長、近畿大学教授を歴任。
2011年11月1日、膵臓癌により死去。享年79。
脚本作品
映画
- 『太陽の墓場』(1960)
- 『非行少女』(1963)
- 『無常』(1970)
- 『黒い雨』(1989)
など多数
テレビ
- 『マグマ大使』(1966、フジテレビ)
- 『帰ってきたウルトラマン』(1971、TBS)
- 『必殺仕掛人』(1972、朝日放送)
- 『ウルトラマンタロウ』(1973年、TBS)
- 『復讐するは我にあり』(1984年、TBS)
など多数