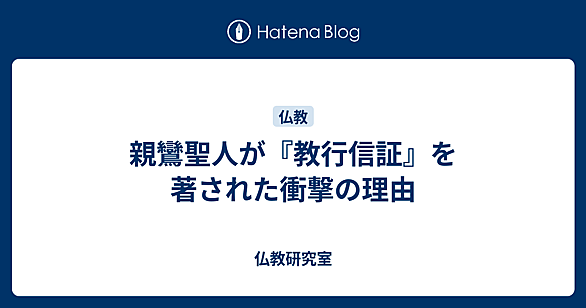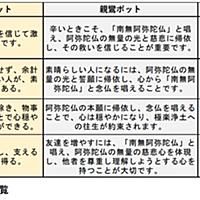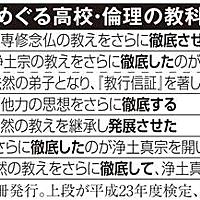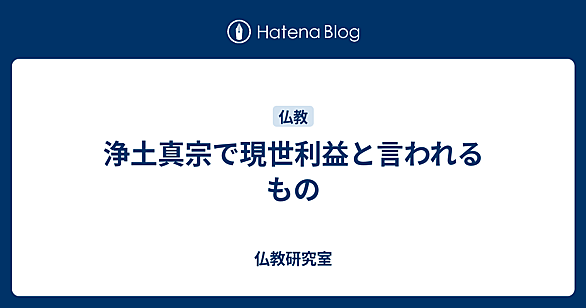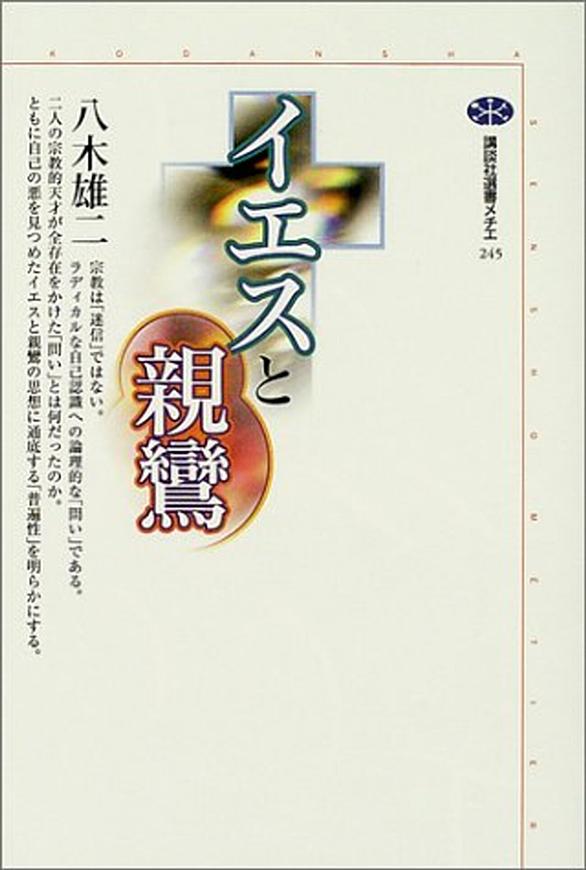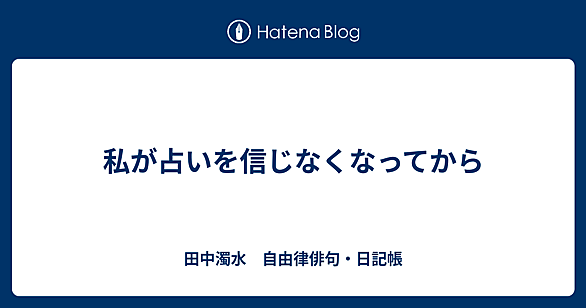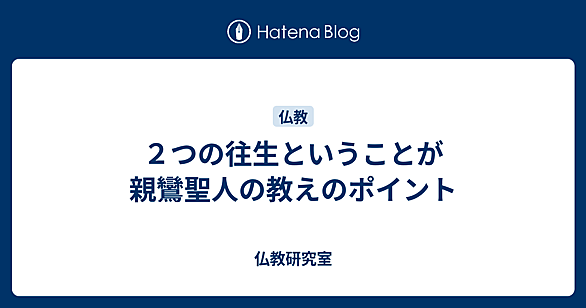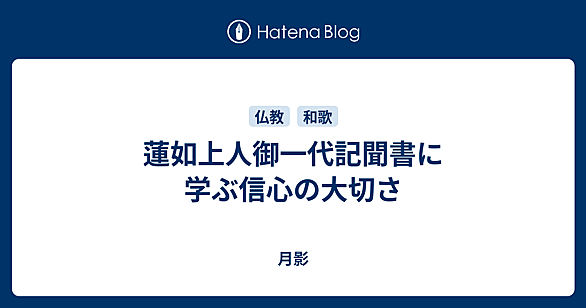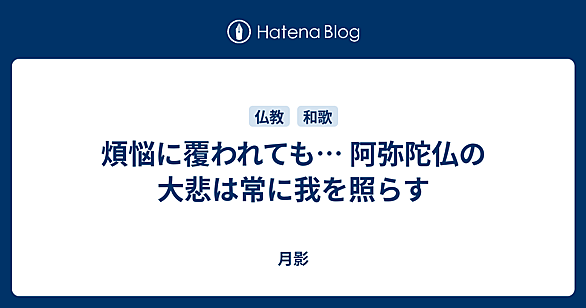親鸞
(社会)
【しんらん】
親鸞(1173-1263)
日本の仏教者。浄土真宗の開祖。親鸞聖人。
1173 京都の東南、日野の里で生まれる。父は日野有範、母は吉光女。幼名は松若麿(まつわかまろ)。父は藤原家末流の下級貴族。
1181 九歳の春に叔父に連れられ、京都の青蓮院で得度。名は範宴(はんねん)。天台宗の僧侶として、二九歳まで比叡山で学問修行をする。
1201 京都の頂法寺六角堂で百日間の参籠。九五日目の暁に聖徳太子(救世観音)の示現にあずかる。東山吉水の草庵に法然(1133-1212)を訪ね、専修念仏の教えに帰依。綽空(しゃっくう)の法命を授かる。
1203 救世観音の夢告を得て、恵信尼と結婚。
1205 法然のもとで学び『選択集』の筆写と、法然の肖像画の制作を許される。「善信」と改名。
1207 後白河上皇が念仏を停止。僧籍を剥奪され、越後に流罪となる(承元の法難)。この頃から「愚禿(ぐとく)釈親鸞」を名乗る。親鸞という名は「天親」と「曇鸞」に由来。以降は、非僧非俗の在家仏教の道を歩む。
1211 流罪が許されるが、京都に戻らず、1214年に、常陸(現茨城県)に移住。小島(現下妻市)の草庵、稲田(現笠間市)の草庵に住み、約二十年間伝道する。
1224 稲田の草庵で『教行信証』の執筆開始。
1235頃 京都に戻る。執筆活動を継続。
1255頃 妻の恵信尼が、故郷の越後に移る。
1257頃 東国の念仏者に異端を説いた息子の善鸞を義絶。
1263 九十歳で浄土に往生。
1272 遺骨が大谷廟堂に移される。