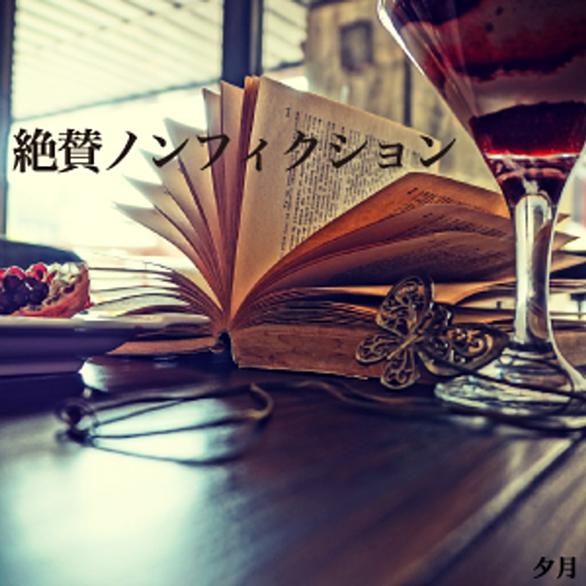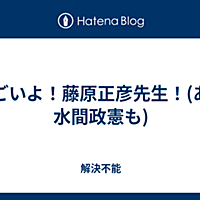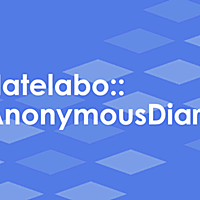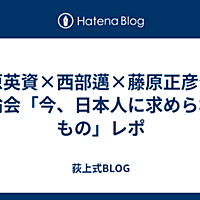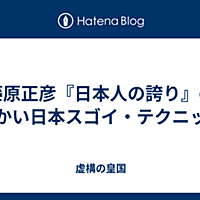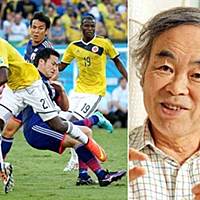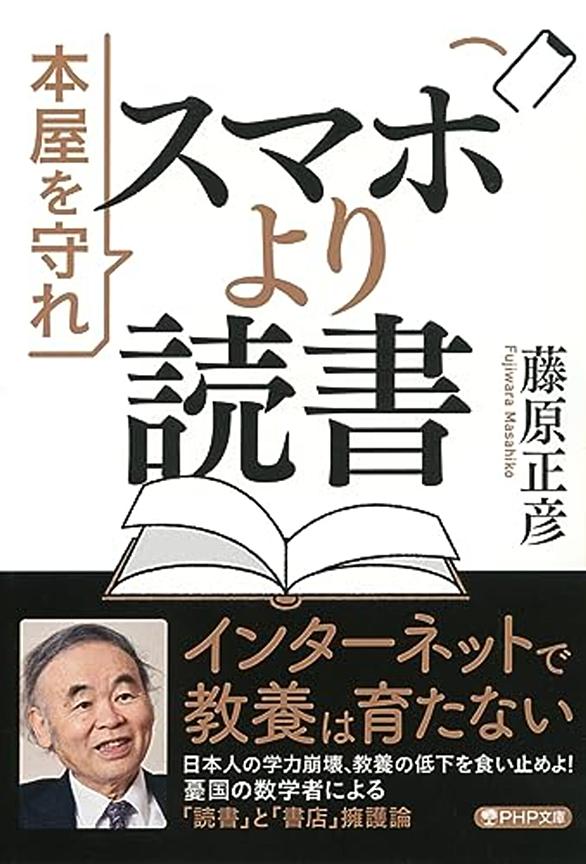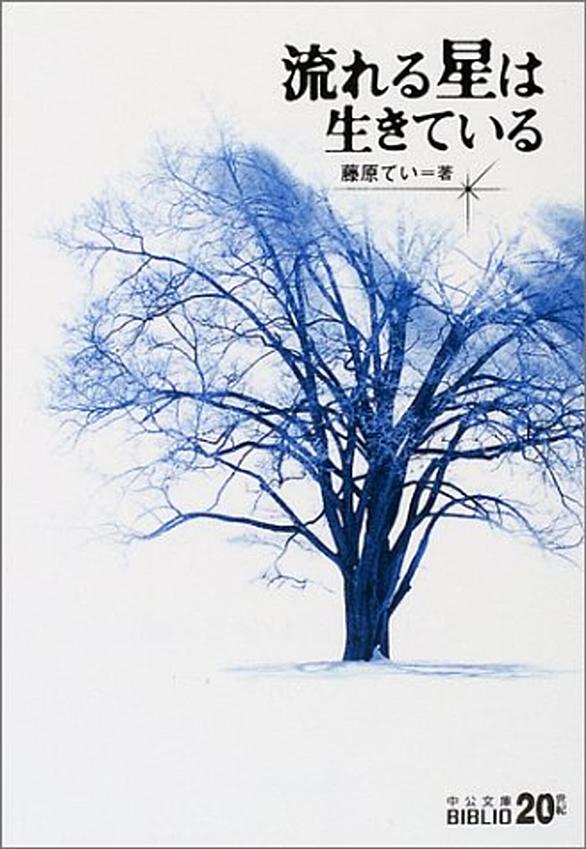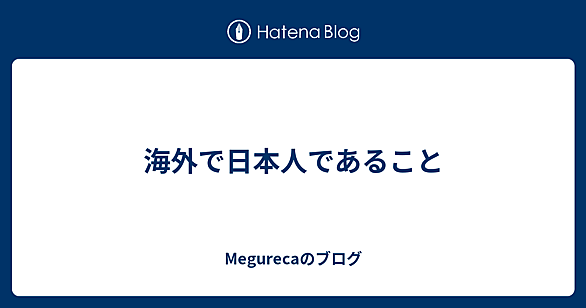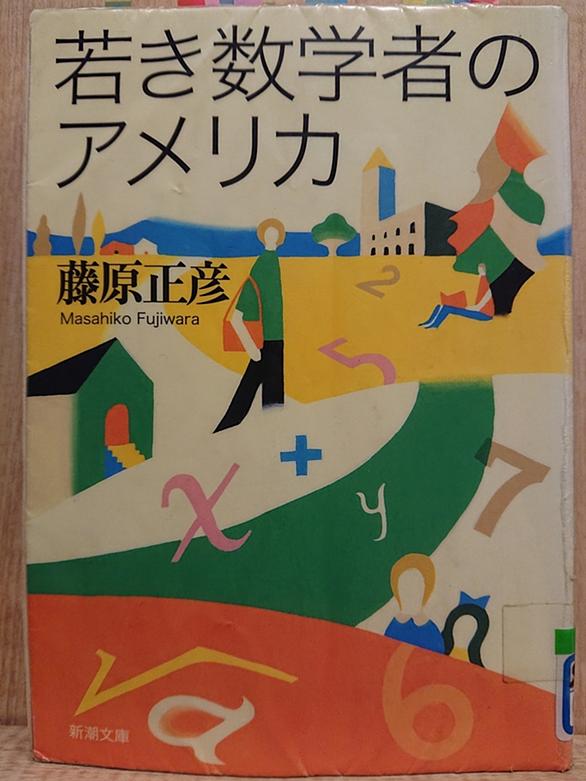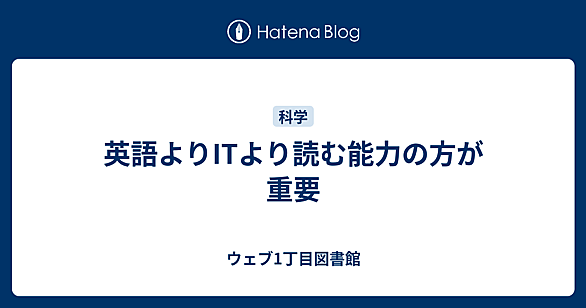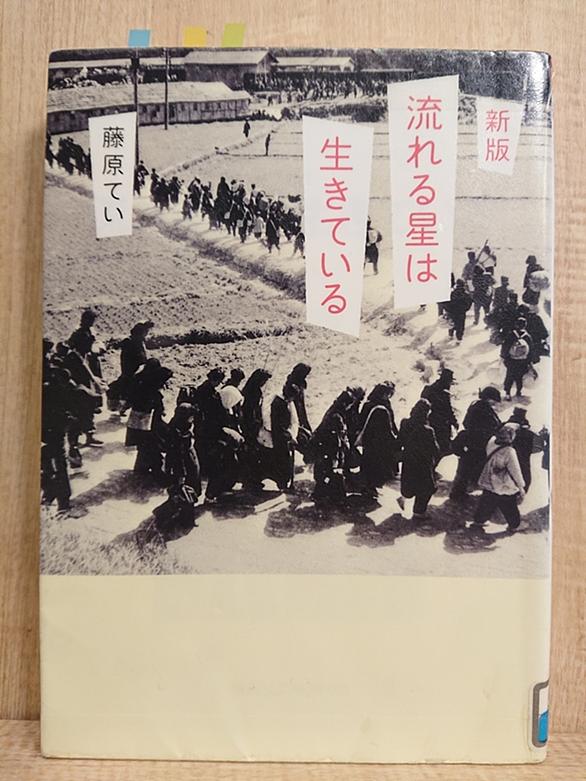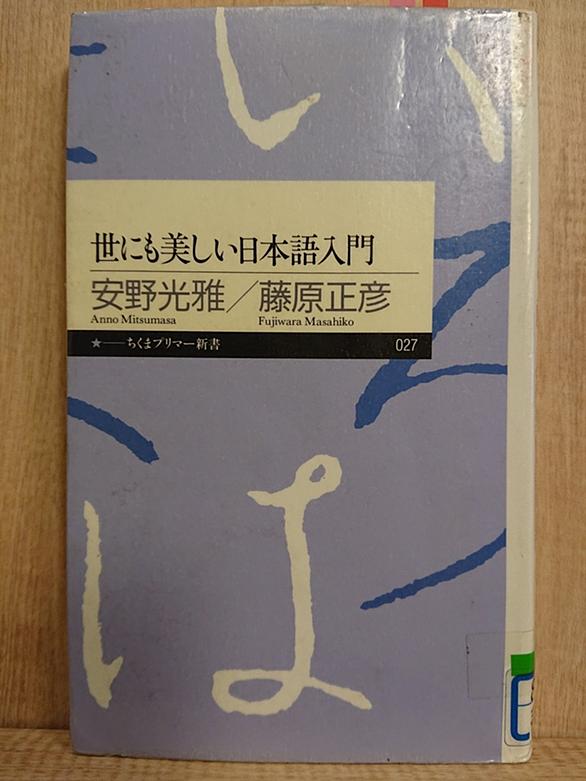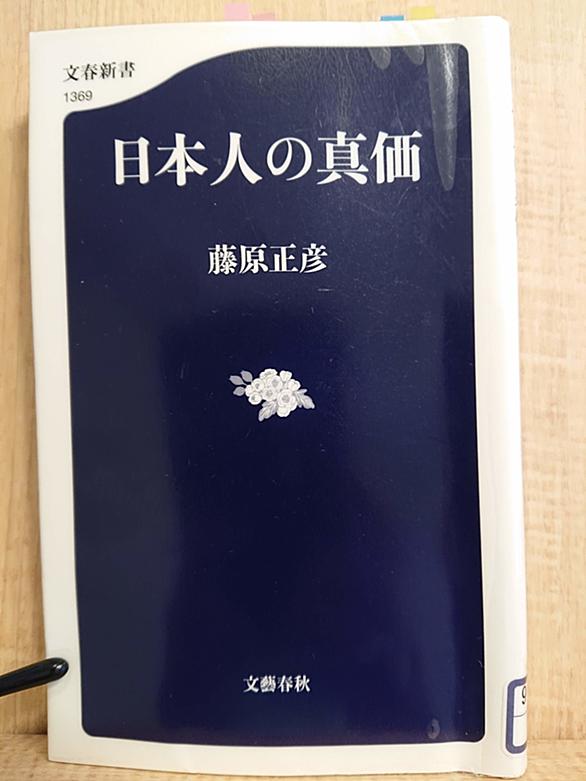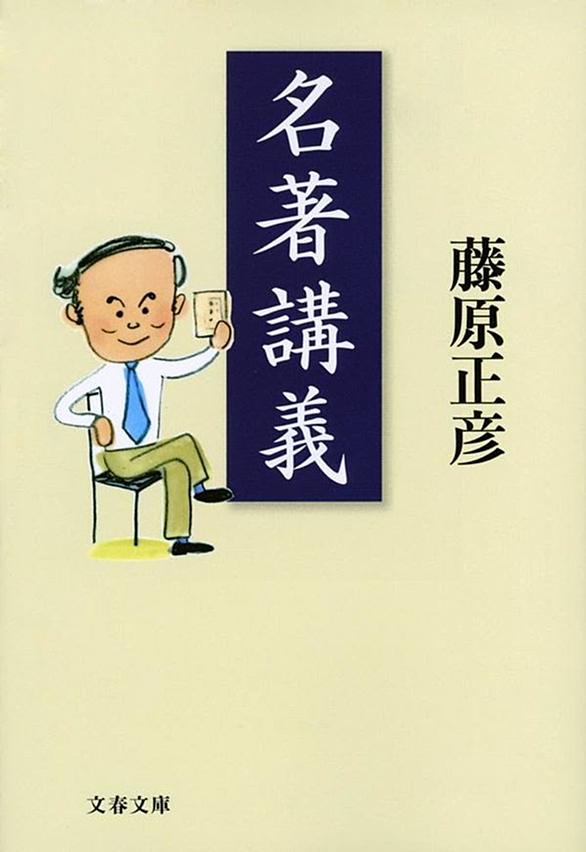藤原正彦
(読書)
【ふじわらまさひこ】
[プロフィール]
1943年7月 旧満州新京生まれ。
父:新田次郎氏(直木賞作家。『孤高の人』、『八甲田山死の彷徨』など)
母:藤原てい氏(『流れる星は生きている』)
東京大学理学部卒業。東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。理学博士。
現在、お茶の水女子大学理学部数学科教授。
2000年からお茶の水女子大学附属図書館長も兼任。
専門は数論。哲学科の土屋賢二と並ぶお茶大の看板教授。
[著書]
-
- 『若き数学者のアメリカ』
- 『遙かなるケンブリッジ』
- 『数学者の休憩時間』
- 『父の威厳 数学者の意地』
- 『古風堂々数学者』
- 『心は孤独な数学者』
- 『天才の栄光と挫折―数学者列伝』
- 『祖国とは国語 』
- 『若き数学者のアメリカ』
- 『数学者の言葉では』
- 『父の旅 私の旅』
- 『国家の品格』
リスト::数学関連