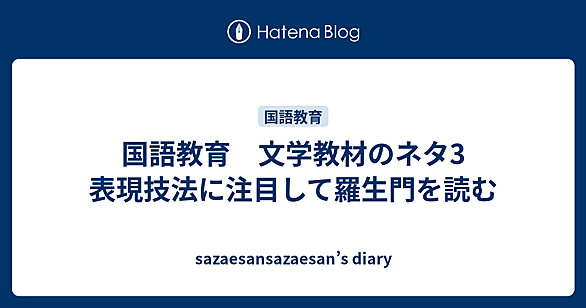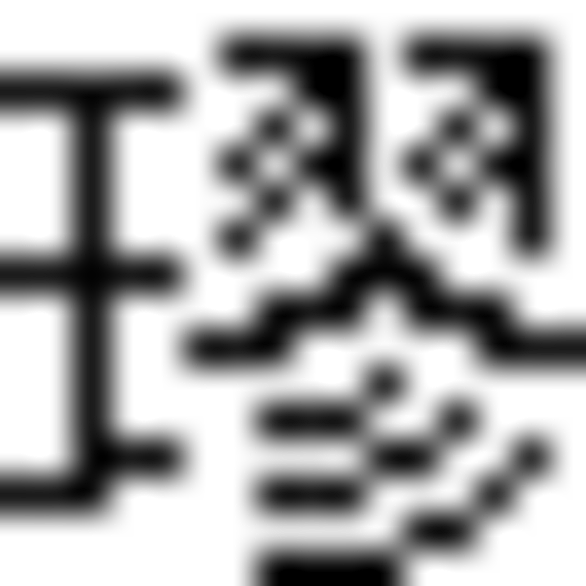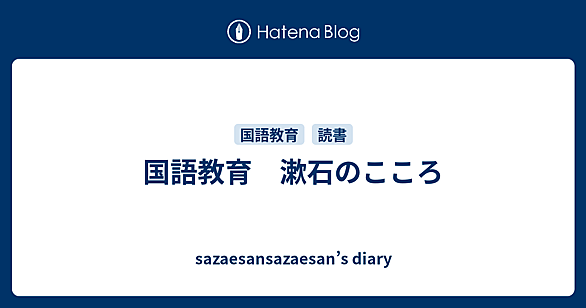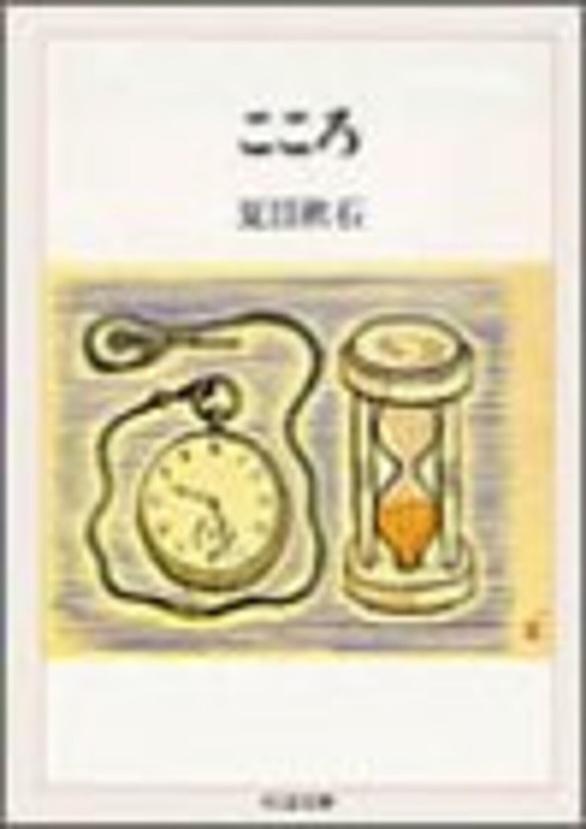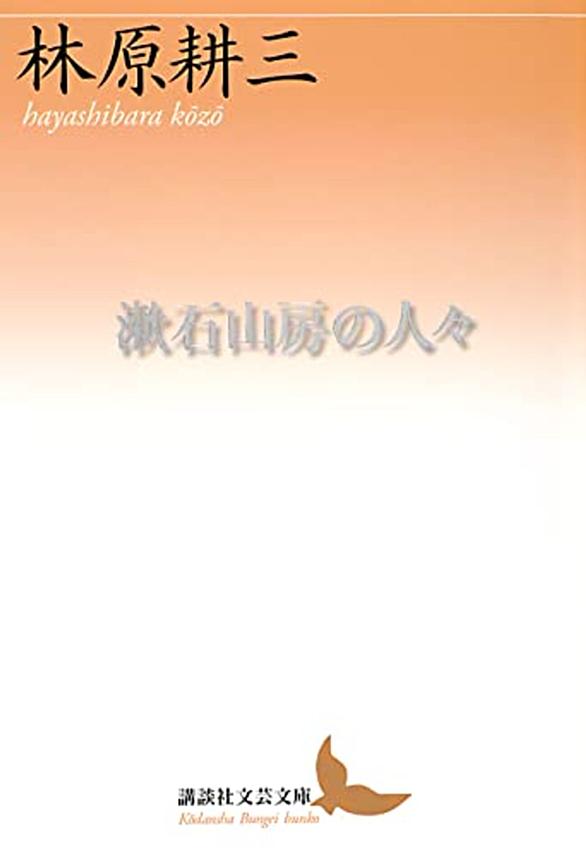石原千秋
(読書)
【いしはらちあき】
1955年生まれ。
成城大学大学院文学研究科国文学専攻博士課程中退。
東横学園女子短期大学助教授、成城大学文藝学部教授を経て、現在早稲田大学教育学部教授。
専攻は日本近代文学。
現代思想を武器に文学テクストを分析、時代状況ともリンクさせた斬新な読みを提出する。
また、一人息子の中学受験を機に、国語教育、とくに入試の「国語」についても問題提起を開始する。
著書
- 夏目漱石. 3 / 日本文学研究資料刊行会. -- 有精堂出版, 1985.7. -- (日本文学研究資料叢書)
- 夏目漱石 / 石原千秋. -- 有精堂出版, 1990.4. -- (日本文学研究資料新集 ; 14)
- 読むための理論 / 石原千秋. -- 世織書房, 1992.3
- 中上健次全集. 3 / 柄谷行人. -- 集英社, 1995.5
- 中上健次全集. 6 / 柄谷行人. -- 集英社, 1995.11
- 中上健次全集. 7 / 柄谷行人. -- 集英社, 1995.12
- 中上健次全集. 10 / 柄谷行人. -- 集英社, 1996.3
- 中上健次全集. 12 / 柄谷行人. -- 集英社, 1996.5
- 反転する漱石 / 石原千秋. -- 青土社, 1997.11
- 徳田秋聲全集. 第5巻 / 徳田秋聲. -- 八木書店, 1998.5
- 漱石を語る. 1 / 小森陽一,石原千秋. -- 翰林書房, 1998.12. -- (漱石研究叢書)
- 漱石を語る. 2 / 小森陽一,石原千秋. -- 翰林書房, 1998.12. -- (漱石研究叢書)
- 秘伝中学入試国語読解法 / 石原千秋. -- 新潮社, 1999.3. -- (新潮選書)
- 漱石の記号学 / 石原千秋. -- 講談社, 1999.4. -- (講談社選書メチエ ; 156)
- 教養としての大学受験国語 / 石原千秋. -- 筑摩書房, 2000.7. -- (ちくま新書)
- 小説入門のための高校入試国語 / 石原千秋. -- 日本放送出版協会, 2002.4. -- (NHKブックス)
- 大学受験のための小説講義 / 石原千秋. -- 筑摩書房, 2002.10. -- (ちくま新書)
- テクストはまちがわない / 石原千秋. -- 筑摩書房, 2004.3.9