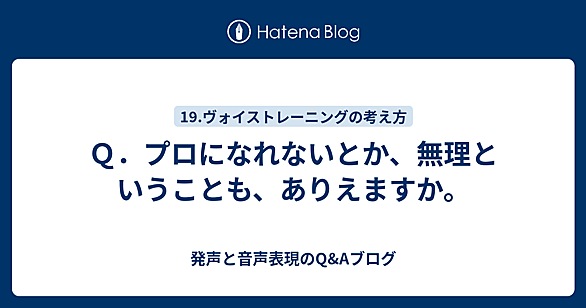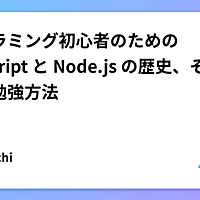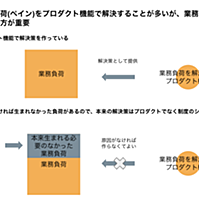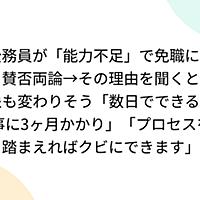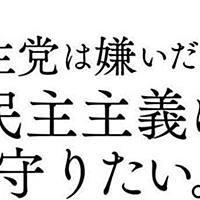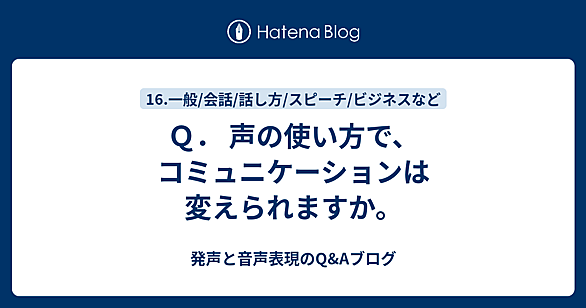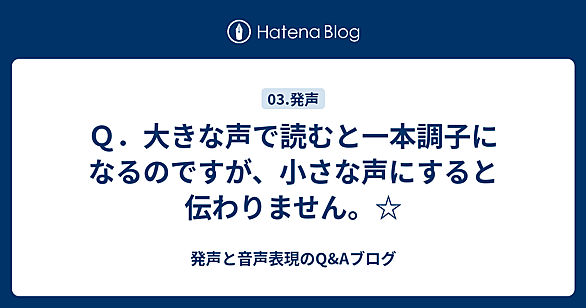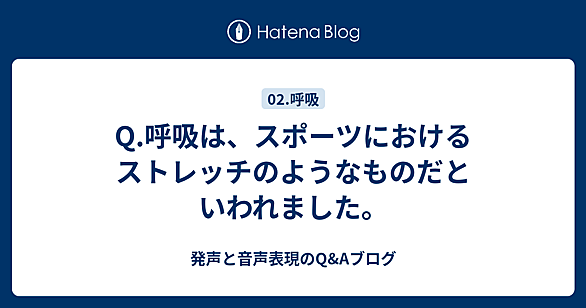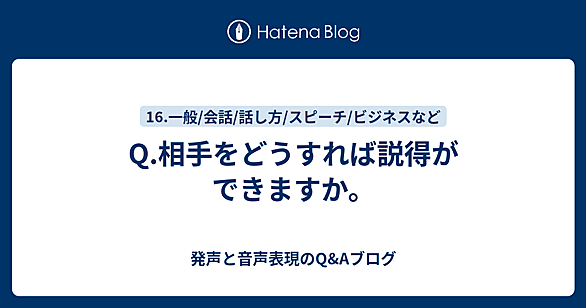踏まえ
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
ネットで話題
もっと見る862ブックマーク[PDF] 5 月 11 日に逝去された著名人の報道に関して 『自殺報道ガイドライン』に反する報道・放送が散見されることを踏まえ、 再度、自殺報道に関する注意喚起をさせていただきます。問合せ先:厚生労働大臣指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」広報室 press@jscp.or.jp / Tel. 03-6272-9446 / Fax. 03-6272-9447 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター 厚生労働省 令和 4 年 5 月 11 日 再度の注意喚起 メディア関係者各位 タレントの上島竜兵さんが 5 月 1... www.mhlw.go.jp
www.mhlw.go.jp