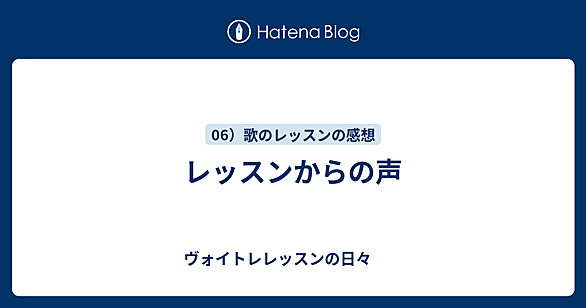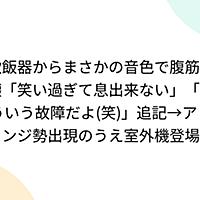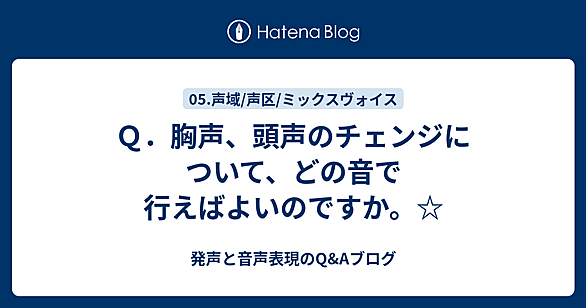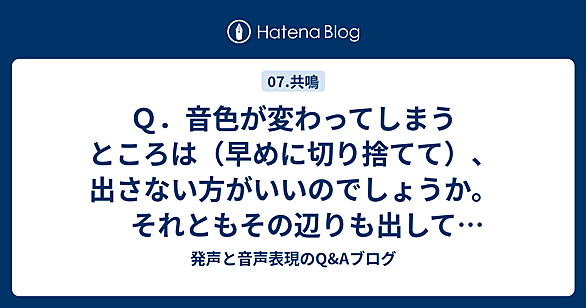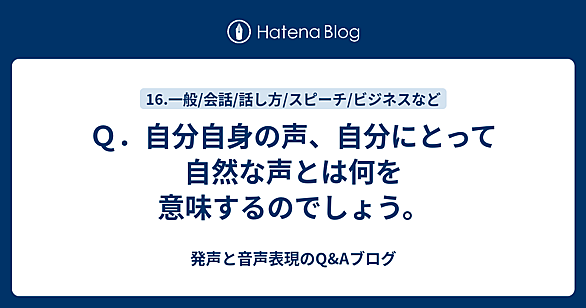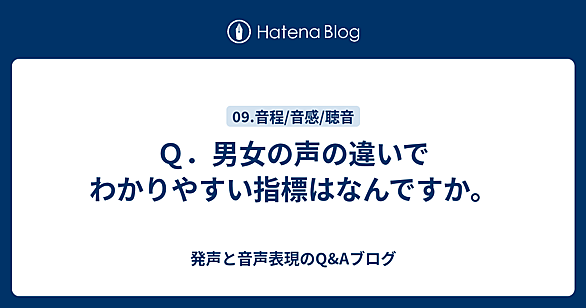音色
(音楽)
【ねいろ】
「おんしょく」とも。
オシロスコープなどの波形装置で観察すると、音声信号は複数の位相や周波数を持つ正弦波の組み合わせで構成されていることがほとんどである。この場合、基本周波数のn倍の音(倍音)が含まれる割合により、たとえば同じ周波数の音声であっても、それは人の声として・あるいはピアノの音や金管楽器・打楽器・または生活騒音などの音として、人間は判別して「聞き分ける」ことができる。
- ねいろ:主として旋律の動きまでもを含めた、曲中におけるその音の「質感」および感情的要素に関して言及する際に使われる。
- おんしょく:旋律などの動きを排し、その音が有する質感についてのみ言及する際に限定的に使われることが多い。