動かす
このタグの解説について
この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ
レッスンからの声
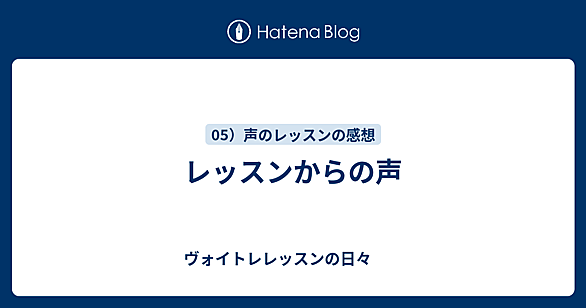
aは開いてしまう、iが浅い。開いたら動かせない。ある意味、閉じて、狭くして、それを息で動かす。息が足りてない。身体についている部分と浮いているところと、そこを螺旋でつないで動いていく。
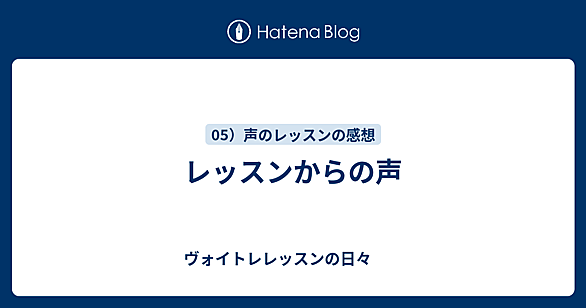
aは開いてしまう、iが浅い。開いたら動かせない。ある意味、閉じて、狭くして、それを息で動かす。息が足りてない。身体についている部分と浮いているところと、そこを螺旋でつないで動いていく。