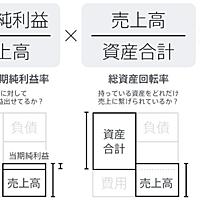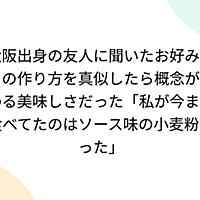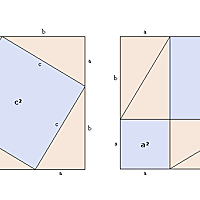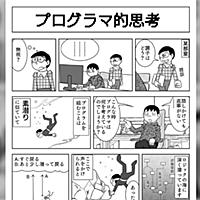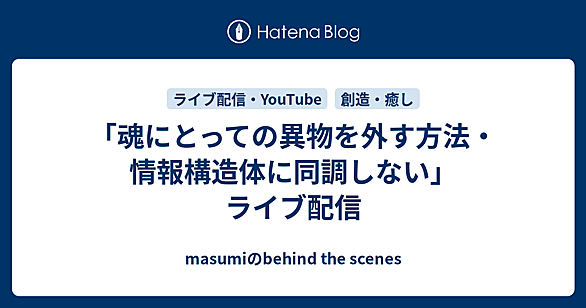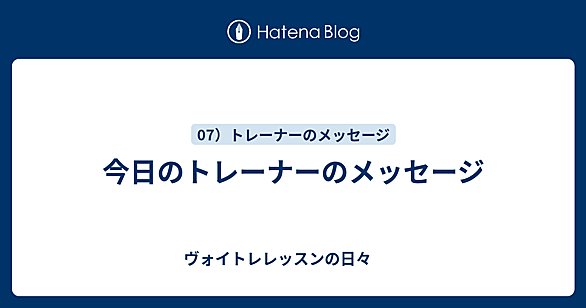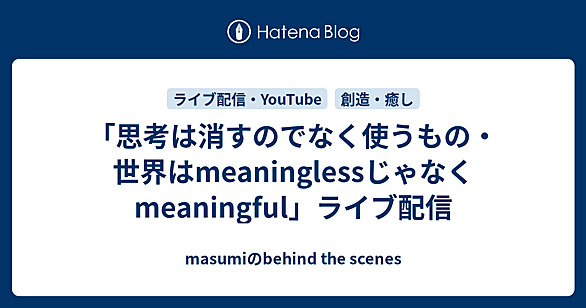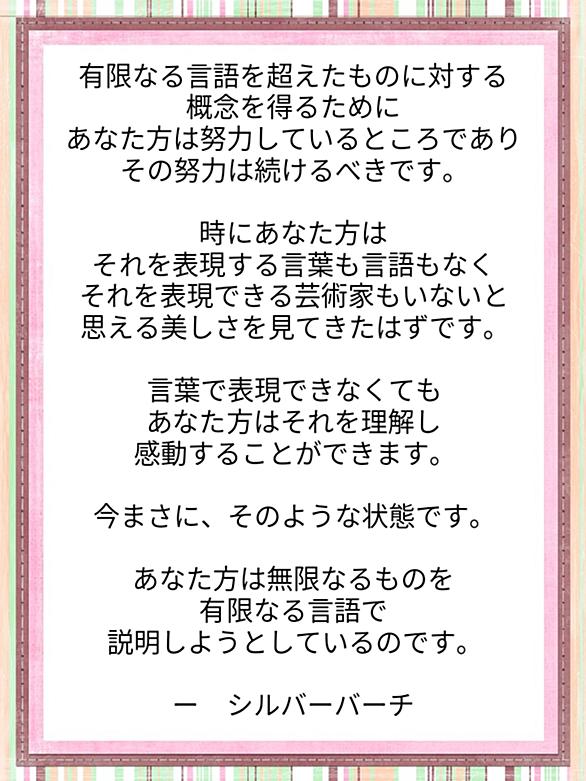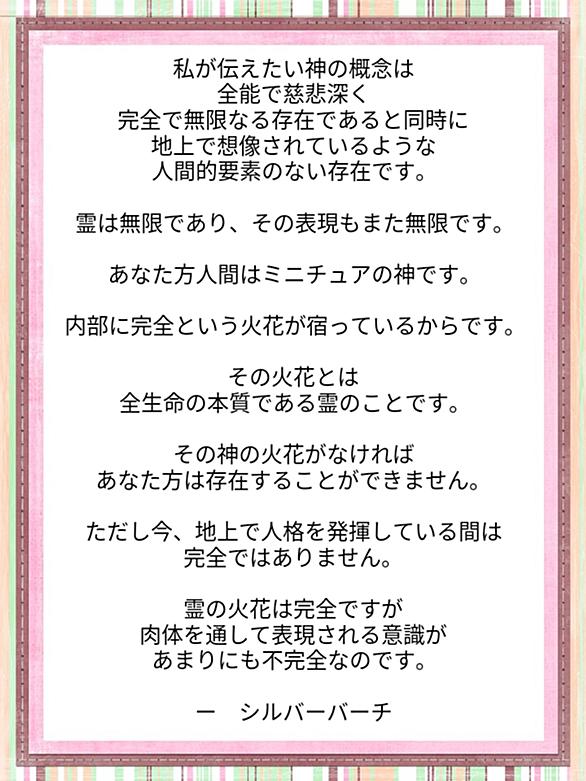概念
M-1グランプリ2005に出場している現役NSC生コンビ。
概念
(1)事物の本質をとらえる思考の形式。事物の本質的な特徴とそれらの連関が概念の内容(内包)。概念は同一本質をもつ一定範囲の事物(外延)に適用されるから一般性をもつ。例えば、人という概念の内包は人の人としての特徴であり、外延はあらゆる人々である。しかし、個体(例えばソクラテス)をとらえる概念(個体概念・単独概念)もある。概念は言語に表現され、その意味として存在する。概念の成立については哲学上いろいろの見解があって、経験される多くの事物に共通の内容をとりだし(抽象)、個々の事物にのみ属する偶然的な性質をすてる(捨象)ことによるとするのが通常の見解で、これに対立するものが経験から独立した概念(先天的概念)を認める立場。
(2)大まかな意味内容。
岩波書店広辞苑第五版には上記のとおりに書かれている。
また、講談社類語大辞典には「ある物事や言葉についてのこういう内容・意味のものであるという、だいたいの考え」との説明がある。
法の「概念」という使い方をした場合、法というものの定義、性質だけでなく、法のとるシステムまでを指す。このことから、ある物事や言葉が表す、本質的な性質や本質的な理論構造について述べたものであると考えられる。
Conceptの訳語。哲学タームとしての意味と一般的な用法がある。ちなみに、訳を当てたのは西周である。
哲学のタームとしては、哲学者によって定義に違いがあるが、一般的に言うと、語の意味の抽象的で形式的な本質的部分をさす。すなわち、その語がその対象に適用されるかどうかを決める最低限の形式的規定であり、その語のさまざまな使用のなかでつねに共有される基礎的な意味内容の形式的特徴。語の意味が反省され、その本質的で偶発的でない恒常的な部分が抽象されたとき、これを概念と呼ぶ。
一般的な用法としては、その語からイメージされる(多くは実地に見聞される以前の)漠然とした意味内容、だいたいのありようについての予期。
例)「0歳児には数の概念がない」
参考URL:Wikipedia「概念」 http://ja.wikipedia.org/wiki/概念
関連語:二文字キーワード